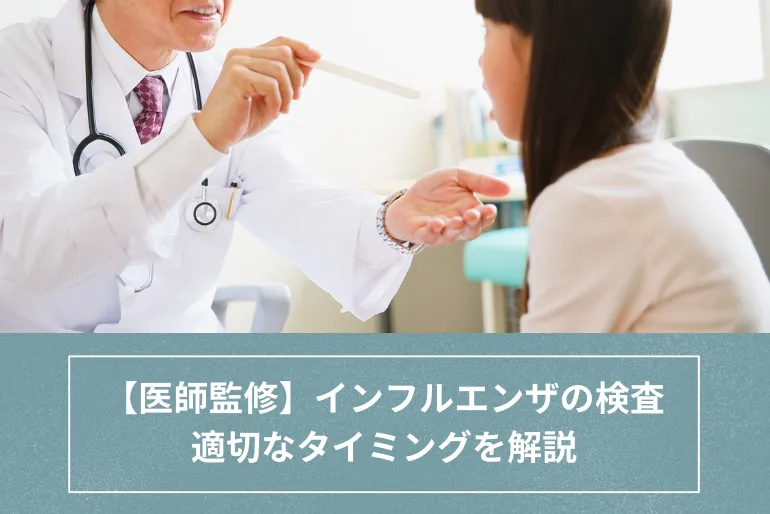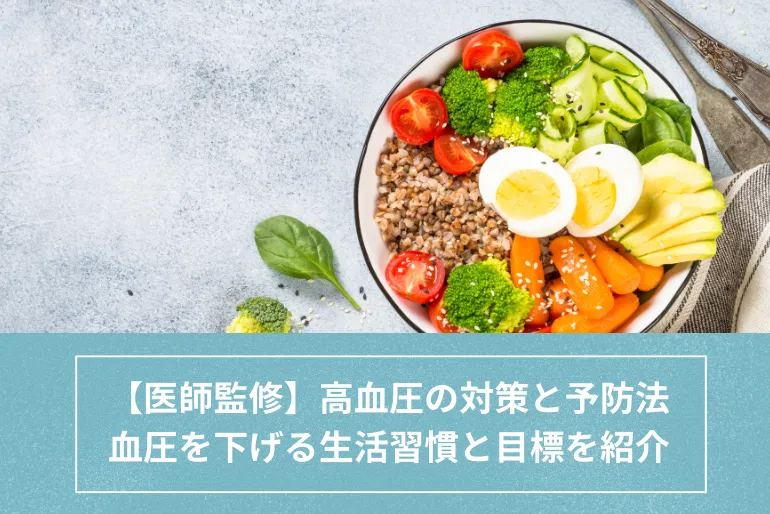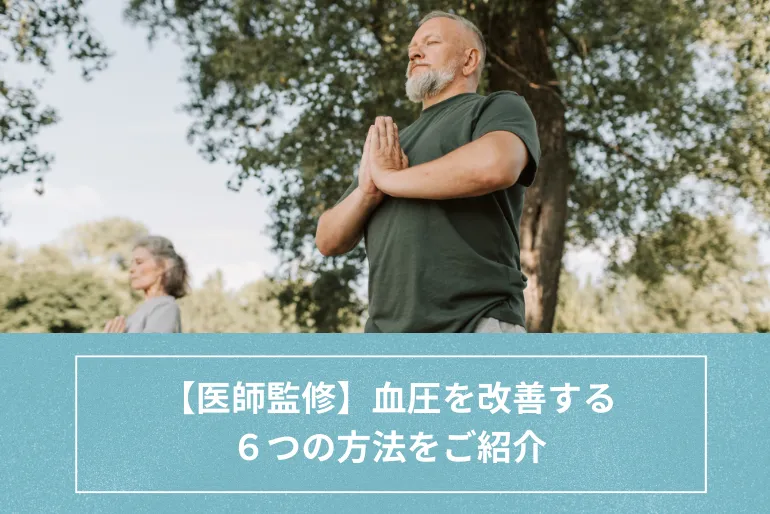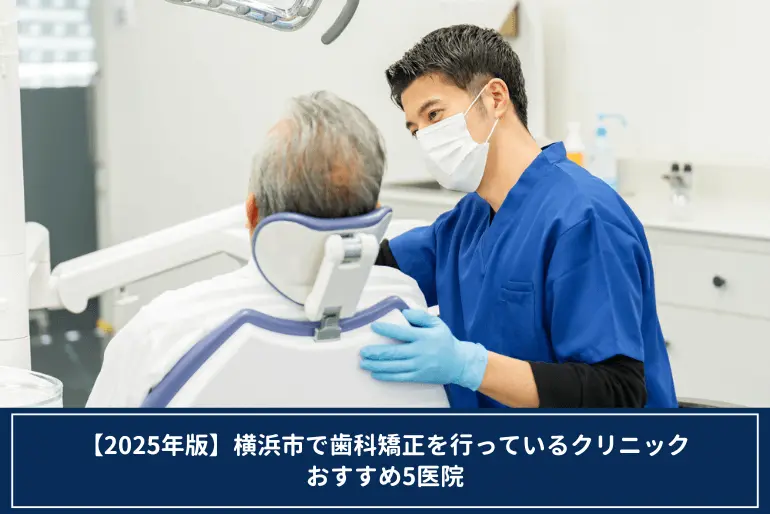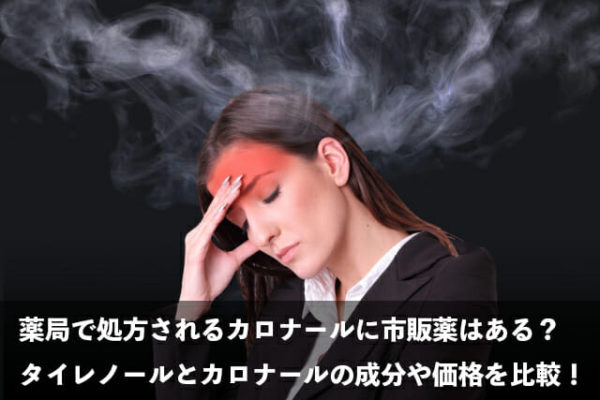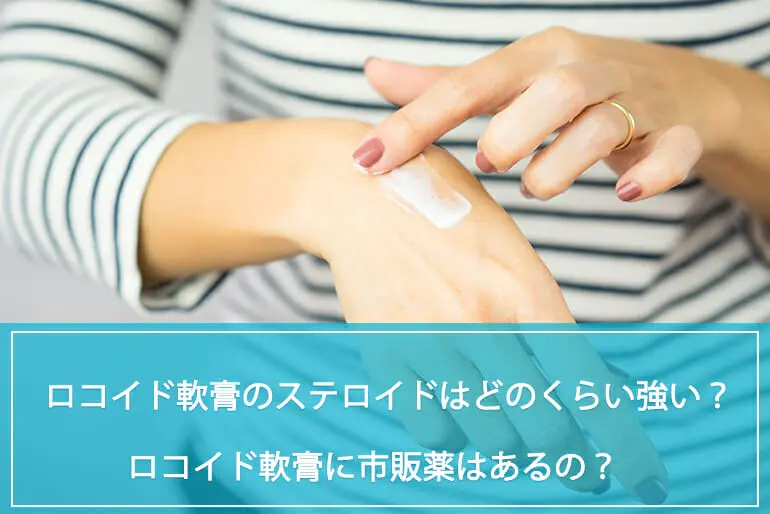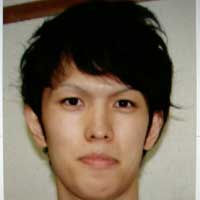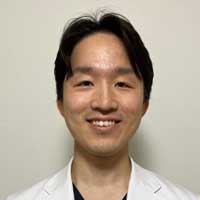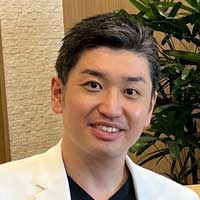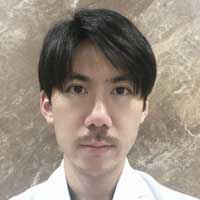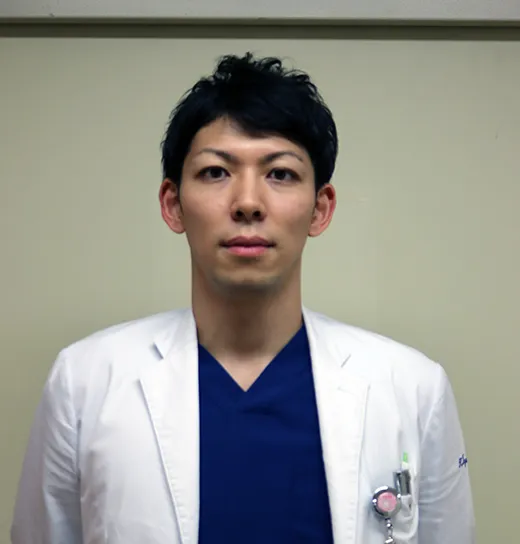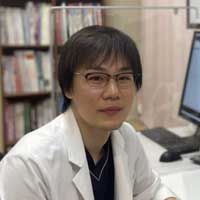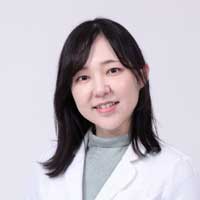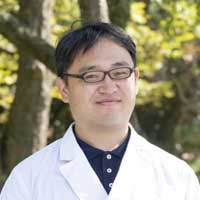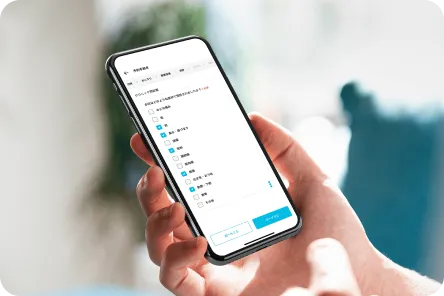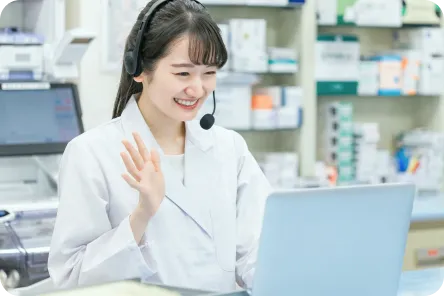春だけじゃない!秋花粉の特徴や原因について詳しく解説
春だけじゃない!秋花粉の特徴や原因について詳しく解説
秋に起こる花粉症とは?
花粉症は、春に限らず一年中発症する可能性があるアレルギー症状です。多くの人がスギ花粉症を思い浮かべますが、実は日本には50種類以上の花粉が原因で花粉症が起こります。特に春と秋に花粉症に悩む人が増えます。スギ花粉症のある人は秋の花粉症も発症しやすいため、秋の花粉に注意してください。
秋の花粉症は、秋に多い植物の花粉が原因です。夏の終わりから10月にかけて、目のかゆみや鼻水などの症状が現れることがあります。原因となる植物によって症状は異なる場合があります。
秋花粉の時期と症状
秋花粉の原因であるブタクサ、ヨモギ、カナムグラの花粉が飛散する期間は、8月から10月です。飛散量のピークは9月ですが、いずれも東北や関東で多く飛びます。関東ではブタクサの花粉が飛ぶ期間は長く、12月頃まで飛散することもあります。
花粉症の症状は、その原因となる植物によって異なるため注意してください。たとえば、春に飛び交うスギ花粉は比較的大きな粒子で構成されているため、鼻の中に留まりやすく、鼻水やくしゃみといった症状が主に現れます。これは、大きな粒子が鼻の粘膜で捕らえられやすいためです。
一方で、秋に問題となるブタクサの花粉は粒子が小さいため、鼻を通り抜けて気管に達することがあります。これにより、気管での刺激が喘息を引き起こすことがあります。花粉症は、季節や環境に応じて適切な対策を取ることが大切です。
秋花粉の原因
秋に花粉症の症状を引き起こす主な植物は、イネ科に属する草本やキク科に分類されるブタクサやヨモギなどの雑草です。
ブタクサ
ヨモギ
ハウスダストの可能性も
日常生活でできる秋花粉の対策法
秋の花粉症の原因になる植物は、それほど大きくありません。そのため、花粉が遠くまで飛散しないことが特徴です。秋の花粉症対策としては、以下のものが考えられます。
花粉を飛散している植物に近づかないようにする
帰宅したら衣服の花粉をはらい落とす
小まめに部屋の掃除をする
花粉症の治療薬を服用する
秋花粉が辛い場合は早めに耳鼻科にかかりましょう。
花粉症の症状が辛い場合は我慢せずに、早期に耳鼻科を訪れて検査を受けることが大切です。医師はアレルギーの原因となる花粉を特定し、適切な治療法を提案してくれます。症状が軽いうちに対処することで、病状の悪化を防げます。
日々の忙しさで病院に行く時間が取れない場合には、オンライン診療が便利です。インターネットを通じて、自宅やオフィスからでも医師の診察を受けられます。予約から診察まで、オンラインで完結するため、時間を有効に使えるでしょう。花粉症の対策として、このサービスを活用してみてください。
まとめ
花粉症は春だけではなく秋にも多いことが特徴です。そのため、花粉が多く飛散する場所を避けること、そして家に帰ったら衣服から花粉を払い落とすことが、小まめに掃除することが対策にもなります。
また、症状が辛いときは自己判断せずに、医療機関を受診しましょう。忙しくて時間がとれない場合には、オンライン診療がおすすめです。
SOKUYAKUでは、花粉症に関するオンライン診療を提供しています。症状でお困りの方や、予防策を講じたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒

花粉による鼻炎は、春のスギやヒノキが有名です。
春の訪れと共に、花粉症の季節が始まると多くの方が思うかもしれません。
実は春だけではなく、秋には異なる種類の花粉が飛び交い、花粉症を引き起こします。
秋の花粉症は、特に咳が多いのが特徴です。
風邪と間違えやすいため、注意してください。
この記事では秋の花粉症について特徴や原因について詳しく解説します。
秋に花粉症で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
春だけじゃない!秋花粉の特徴や原因について詳しく解説
秋に起こる花粉症とは?
花粉症は、春に限らず一年中発症する可能性があるアレルギー症状です。多くの人がスギ花粉症を思い浮かべますが、実は日本には50種類以上の花粉が原因で花粉症が起こります。特に春と秋に花粉症に悩む人が増えます。スギ花粉症のある人は秋の花粉症も発症しやすいため、秋の花粉に注意してください。
秋の花粉症は、秋に多い植物の花粉が原因です。夏の終わりから10月にかけて、目のかゆみや鼻水などの症状が現れることがあります。原因となる植物によって症状は異なる場合があります。
秋花粉の時期と症状
秋花粉の原因であるブタクサ、ヨモギ、カナムグラの花粉が飛散する期間は、8月から10月です。飛散量のピークは9月ですが、いずれも東北や関東で多く飛びます。関東ではブタクサの花粉が飛ぶ期間は長く、12月頃まで飛散することもあります。
花粉症の症状は、その原因となる植物によって異なるため注意してください。たとえば、春に飛び交うスギ花粉は比較的大きな粒子で構成されているため、鼻の中に留まりやすく、鼻水やくしゃみといった症状が主に現れます。これは、大きな粒子が鼻の粘膜で捕らえられやすいためです。
一方で、秋に問題となるブタクサの花粉は粒子が小さいため、鼻を通り抜けて気管に達することがあります。これにより、気管での刺激が喘息を引き起こすことがあります。花粉症は、季節や環境に応じて適切な対策を取ることが大切です。
秋花粉の原因
秋に花粉症の症状を引き起こす主な植物は、イネ科に属する草本やキク科に分類されるブタクサやヨモギなどの雑草です。
ブタクサ
ブタクサは、私たちの身近な場所によく生息する植物で、キク科に分類されます。日常よく歩く道端や川辺、公園などで見かけ、1〜2メートルの高さに成長します。夏の終わりから秋にかけて、小さな黄色い花を咲かせるのが特徴です。花自体は約2ミリと小さいですが、多数が集まって長い穂を形成します。
ブタクサは7月頃から花を咲かせ始め、8月から10月にかけて花粉が飛散します。ただし、地域によって飛散のピークや期間には差があるため、注意してください。
ブタクサの花粉は、スギ花粉の約半分の大きさで、その小ささが体内深くまで侵入することが可能です。スギ花粉は鼻毛で捕らえられることが多いのに対し、ブタクサ花粉は鼻毛を通り抜け、気管支に到達しやすいのです。気管支に達した花粉は、粘膜を刺激して咳を引き起こすことがあり、喘息を持つ人には症状を悪化させることもあります。
ブタクサ花粉症の症状には、目のかゆみやくしゃみ、鼻水、鼻詰まりがありますが、特に咳が出やすいのが特徴です。また、肌荒れなどの症状が出る方もいます。
ヨモギ
ヨモギは、夏の終わりから秋にかけて、その茎を天に向かって伸ばし、50cmから120cmの高さまで成長します。地味なため植物に詳しくないと、他の雑草と区別がつきません。ヨモギの花粉は、8月から10月にかけて空中に舞い上がりますが、住んでいる地域によって時期は少し変わります。
ヨモギの花粉が飛ぶ範囲は数十メートルと限られています。これは、スギのような木の花粉が数十キロメートル、時には数百キロメートルも飛ぶこととは対照的です。しかし、ヨモギは身近な存在で、私たちの周りによく生えているため、触れる機会は意外と多くなります。
もしヨモギがどこに生えているかを知っていれば、近づかないようにすることで、花粉による影響を避けられます。
ヨモギの花粉症は、くしゃみや鼻水、鼻詰まりといったアレルギー性鼻炎、目のかゆみや充血、涙目といったアレルギー性結膜炎が主な症状です。しかし、ヨモギの花粉は比較的小さく、吸い込むと気管支にまで達してしまうことがあり、咳や喘息の症状を引き起こすことがあるため、注意が必要です。
ハウスダストの可能性も
家の中でアレルギーの症状がひどくなる場合、それは花粉症だけが原因ではないかもしれません。実は、ハウスダストもアレルギー反応を引き起こす一因です。ハウスダストとは、家の中にあるホコリやダニの死骸、ペットの毛、人間の髪の毛やフケ、そしてカビなど、さまざまな微粒子のことを指します。
特に夏の暑い時期にはダニが増え、秋になるとその多くが死んでしまいます。しかし、ダニの死骸は非常に小さく軽いため、わずかな空気の動きで簡単に舞い上がり、これがアレルギーの症状を引き起こす原因となります。ダニによるアレルギーは、鼻の不快感だけでなく、喘息を引き起こすこともありますので、注意が必要です。
もし花粉症の対策をしていても症状が改善されない場合、または外出せずとも症状が現れる場合は、ハウスダストが原因かもしれません。その場合は、部屋の掃除を入念に行い、ハウスダストを減らす工夫をすることが大切です。
日常生活でできる秋花粉の対策法
秋の花粉症の原因になる植物は、それほど大きくありません。そのため、花粉が遠くまで飛散しないことが特徴です。秋の花粉症対策としては、以下のものが考えられます。
花粉を飛散している植物に近づかないようにする
原因となる植物に近寄らないようにしましょう。見分けることは難しいかもしれませんが、雑草が多い場所は避けてください。たとえば、草原や川辺などには注意です。
帰宅したら衣服の花粉をはらい落とす
帰宅した際には、外から持ち込んだスギ花粉を家の中に入れないようにしましょう。玄関で靴を脱ぐときに、衣服や髪の毛についた花粉も払い落とすことが大切です。この行動で、花粉によるアレルギーのリスクを減らせます。
小まめに部屋の掃除をする
花粉症の季節には、家の中を清潔に保つことが大切です。衣服についた花粉は、粘着ローラーでサッと取り除けます。また、玄関には空気清浄機を設置して、外から持ち込まれる花粉を減らしましょう。掃除機をかける際は、畳の線に沿ってゆっくりと動かすことで、効果的に花粉を吸い取れます。
花粉は空気中を舞うため、掃除する際には「拭き掃除」が効果的です。これにより、花粉を空中に舞い上がらせずに取り除けます。掃除機では取りきれない布製品には、粘着シートを使って花粉をしっかりと取り除きましょう。
花粉症の治療薬を服用する
市販されている花粉症の薬には、さまざまな種類があり、それぞれ異なる作用があります。
・抗ヒスタミン薬
アレルギー反応を引き起こすヒスタミンの働きをブロックします。
第1世代と第2世代があり、第1世代は眠気を引き起こすことがありますが、第2世代はその副作用が少ないことが特徴です。
・血管収縮薬
鼻粘膜のうっ血を改善し、鼻詰まりを解消します。
・副交感神経遮断薬
鼻水の分泌を抑える効果があります。
・抗アレルギー薬
アレルギー反応自体を抑えることで、症状の発生を防ぎます。
・抗炎症薬
鼻粘膜や目の炎症を抑える効果があります。
花粉症の治療薬は錠剤やシロップ、点鼻薬、点眼薬など、さまざまな形態で提供されています。症状や好みに合わせて選びましょう。症状が改善されない場合は、他の病気が原因かもしれません。早めに医療機関を受診し、医師の診察を受けることをお勧めします。
秋花粉が辛い場合は早めに耳鼻科にかかりましょう。
花粉症の症状が辛い場合は我慢せずに、早期に耳鼻科を訪れて検査を受けることが大切です。医師はアレルギーの原因となる花粉を特定し、適切な治療法を提案してくれます。症状が軽いうちに対処することで、病状の悪化を防げます。
日々の忙しさで病院に行く時間が取れない場合には、オンライン診療が便利です。インターネットを通じて、自宅やオフィスからでも医師の診察を受けられます。予約から診察まで、オンラインで完結するため、時間を有効に使えるでしょう。花粉症の対策として、このサービスを活用してみてください。
まとめ
花粉症は春だけではなく秋にも多いことが特徴です。そのため、花粉が多く飛散する場所を避けること、そして家に帰ったら衣服から花粉を払い落とすことが、小まめに掃除することが対策にもなります。
また、症状が辛いときは自己判断せずに、医療機関を受診しましょう。忙しくて時間がとれない場合には、オンライン診療がおすすめです。
SOKUYAKUでは、花粉症に関するオンライン診療を提供しています。症状でお困りの方や、予防策を講じたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。