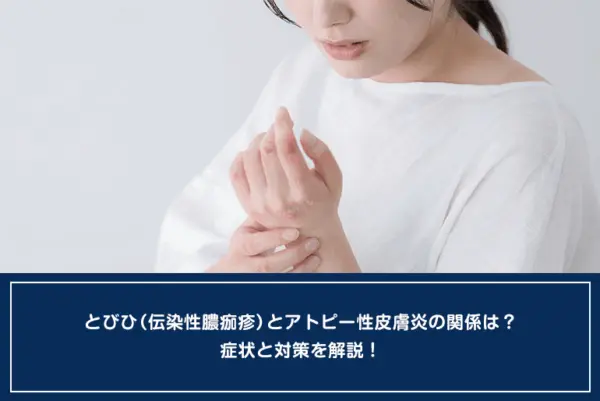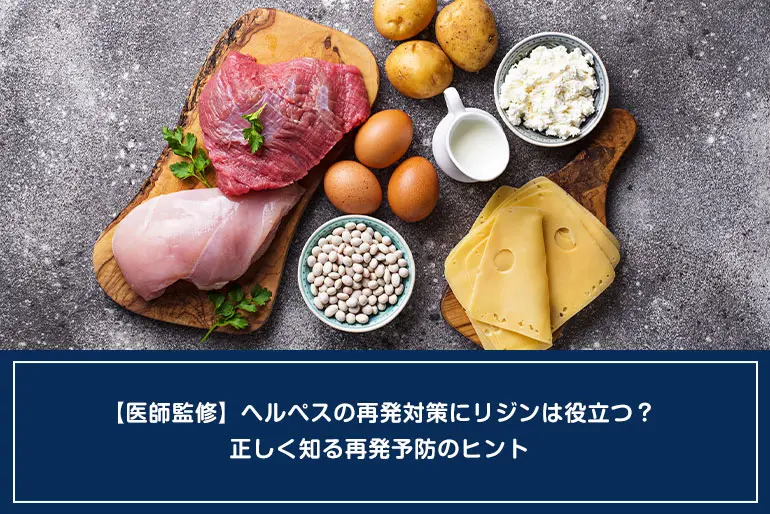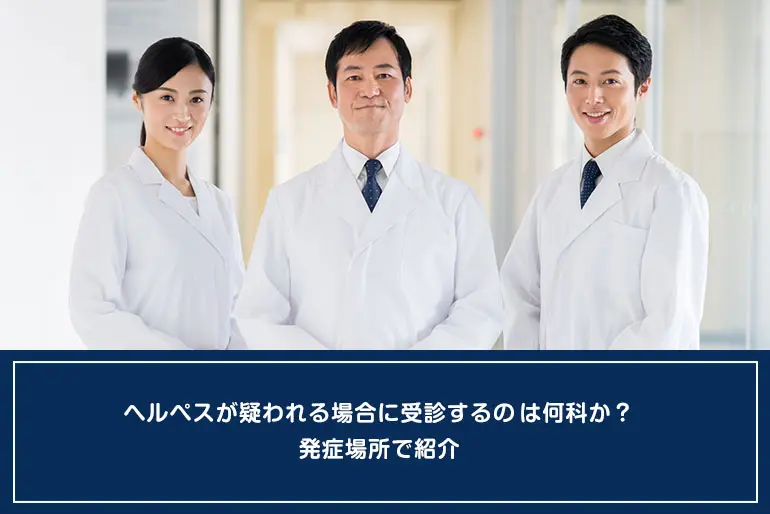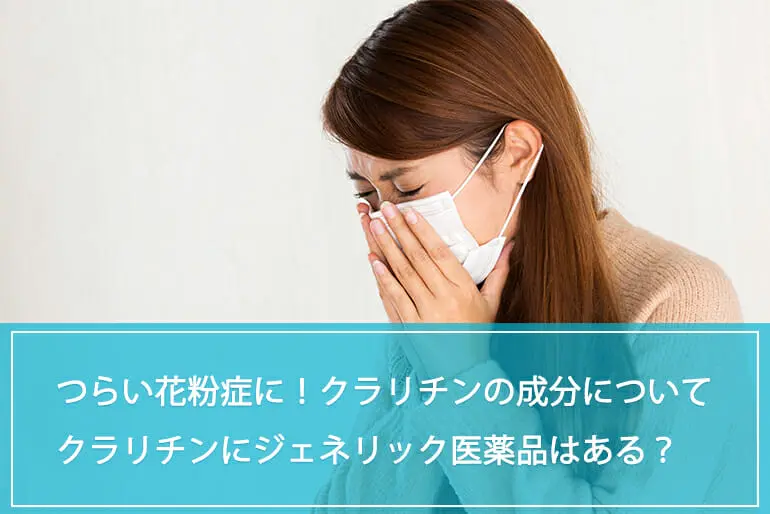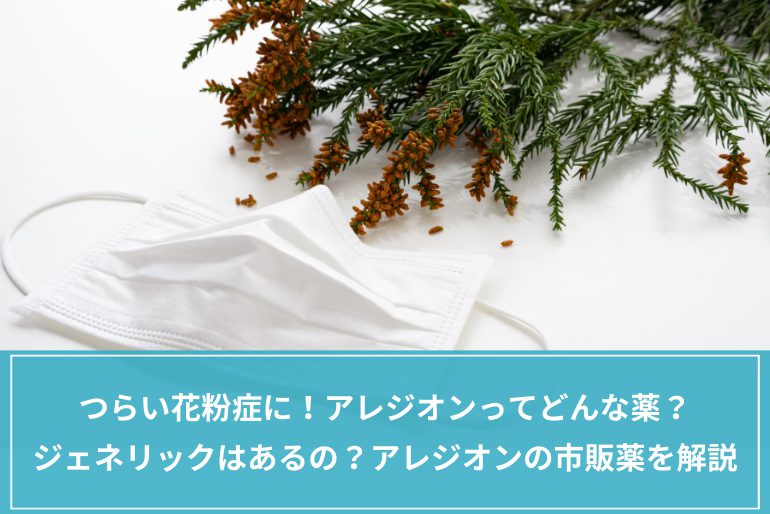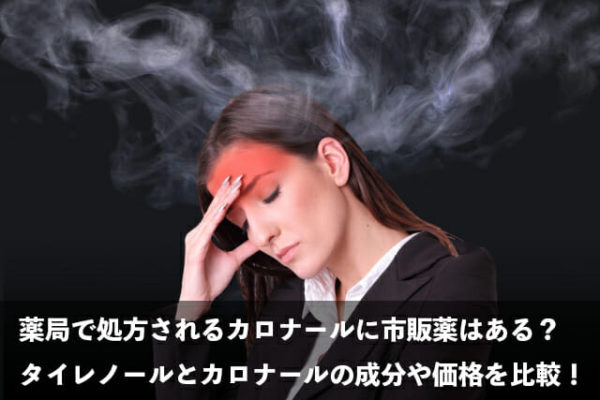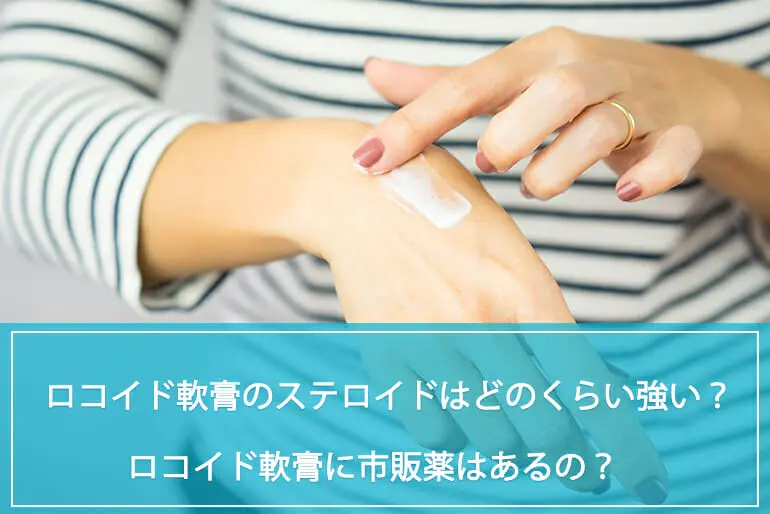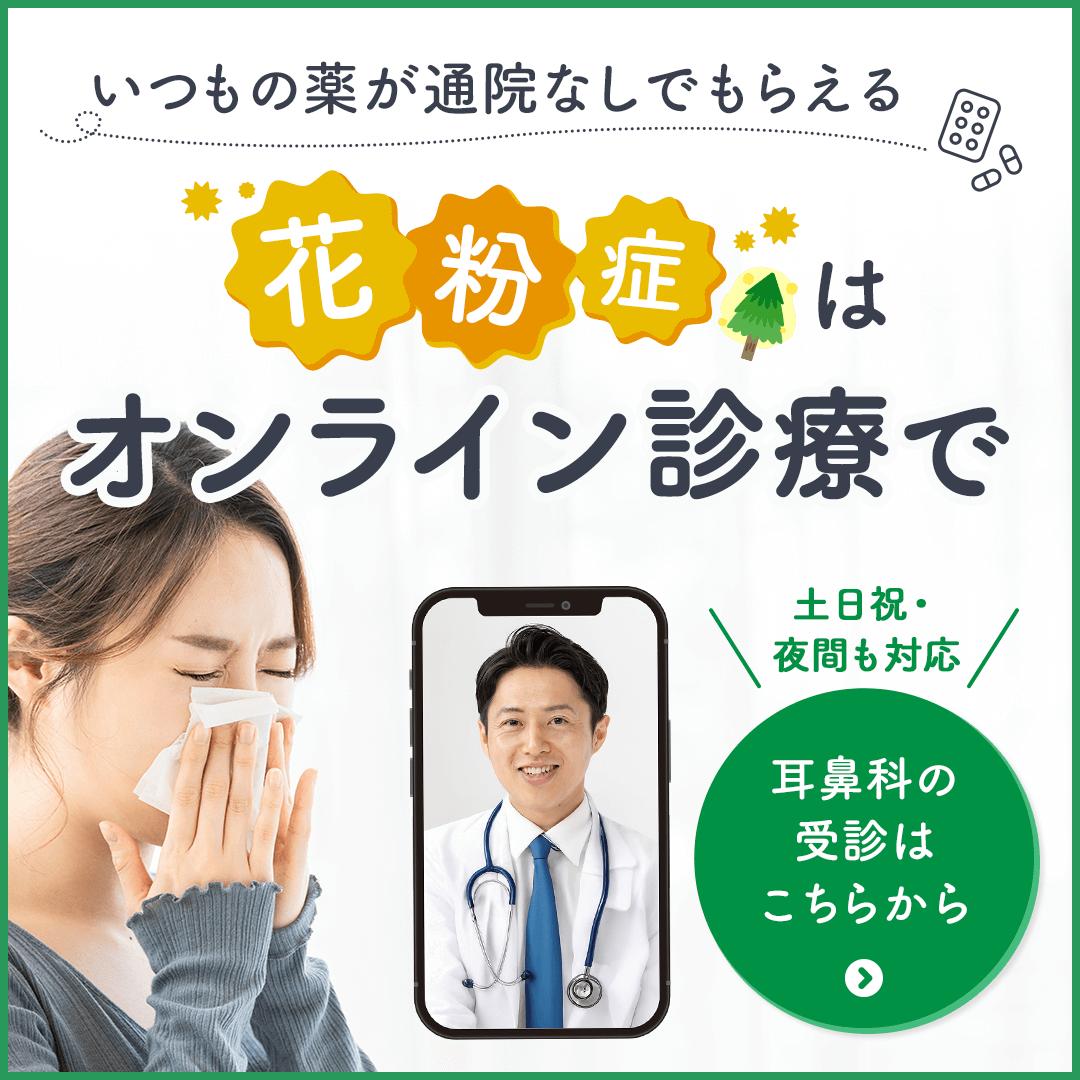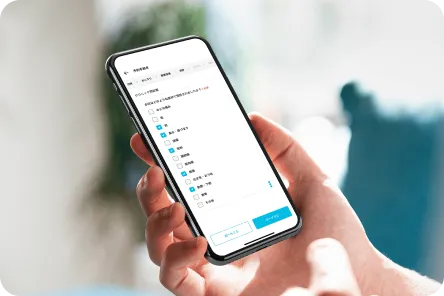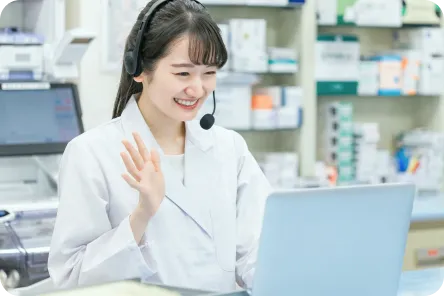とびひ(伝染性膿痂疹)とアトピー性皮膚炎の関係は?症状と対策を解説!
アトピー性皮膚炎は感染を起こしやすい
アトピー性皮膚炎の肌は、健康な肌と比べて皮膚のバリア機能が弱くなっています。本来、皮膚は外部からの刺激や異物が体内に侵入するのを防ぎ、同時に体内の水分を保持する役割を果たしています。しかし、アトピー性皮膚炎の方の肌は乾燥しやすく、そのバリア機能が低下しているため、外部の刺激に対する抵抗力が弱くなっているのです。
黄色ブドウ球菌とアトピー性皮膚炎の関係
アトピー性皮膚炎の方の皮膚からは、黄色ブドウ球菌が高頻度に検出されます。アトピー性皮膚炎の方の肌で黄色ブドウ球菌は増殖しやすく、症状を悪化させる要因となります。
黄色ブドウ球菌とは
黄色ブドウ球菌は、自然界に広く存在し、人や動物の皮膚や粘膜にも常在している細菌です。その名前は、顕微鏡で観察するとブドウの房のように見える形から付けられました。健康な人の鼻や皮膚にも一定の割合で存在していますが、多くの場合は特に問題を引き起こしません。しかし、黄色ブドウ球菌はさまざまな毒素を産生し、免疫力が低下した人や傷口のある皮膚に感染すると、深刻な病気を引き起こすことがあります。
黄色ブドウ球菌が出す毒素がアトピー性皮膚炎を悪化させる
1.常在菌のバランスの崩れ
黄色ブドウ球菌が異常に増殖すると、皮膚の常在菌のバランスを崩し、角質層の細胞を傷つけることで炎症を引き起こす
2.皮膚バリアの破壊
産生する毒素や酵素が、皮膚の角質層を傷つけ、バリア機能を低下させる
3.免疫反応の過剰刺激
分泌する毒素が免疫系を過剰に刺激し、かゆみや炎症を悪化させることがある
4.皮膚の脂質分解
黄色ブドウ球菌が作り出す酵素が皮膚の脂質を分解し、乾燥やバリア機能の低下を引き起こすことがある
これらの要因が複合的に作用し、「負のスパイラル」を形成します。これが、黄色ブドウ球菌によってアトピー性皮膚炎が悪化する理由です。
遺伝的要因によって、皮膚バリアがさらに弱くなっている方では、黄色ブドウ球菌がより定着しやすくなり、感染のリスクが高まります。また、黄色ブドウ球菌はバイオフィルムと呼ばれる保護膜を作ることで、抗生物質や免疫細胞の攻撃から身を守るため、一度感染すると慢性化しやすく、治療が難しくなることもあります。
とびひ(伝染性膿痂疹)の原因
とびひは、主に水疱性膿痂疹と痂皮性膿痂疹の2種類があります。
黄色ブドウ球菌が原因の水疱性膿痂疹
黄色ブドウ球菌が原因で、乳幼児に多く見られます。虫刺されやあせも、アトピー性皮膚炎、すり傷などで皮膚のバリア機能が低下した部分に感染しやすく、高温多湿の夏に多発します。接触感染によって広がるため、幼稚園や保育所、学校での集団感染も起こりやすいことが特徴です。
溶連菌が原因の痂皮性膿痂疹
A群β溶血性連鎖球菌(溶連菌)が原因で、黄色ブドウ球菌が混合感染している場合もあります。季節や年齢を問わず発症し、子どもだけでなく大人にも見られます。アトピー性皮膚炎を持つ人に合併して起こることが多く、黄褐色のかさぶたができるのが特徴です。
とびひ(伝染性膿痂疹)の症状は
それぞれのタイプにわけて症状を紹介します。
かゆみの強い水疱ができる水疱性膿痂疹
水疱がかゆみを伴い、皮膚に小さな水疱が集まります。水疱は、数日で大きくなり、破れると赤いびらん(ただれた状態)になります。これにより、感染が広がりやすく、患部をかいた手で他の部位に触れると、新たな水疱ができてさらに広がることが特徴です。
黄褐色の厚いかさぶたが特徴の痂皮性膿痂疹
最初に小さな発赤が現れ、膿を含んだ膿疱ができ、最終的に黄褐色の厚いかさぶたに変わり、押すと膿が出ることがあります。また、リンパ節の腫れや発熱、のどの痛みを伴う場合もあります。
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群に要注意!
黄色ブドウ球菌の毒素が血液中に入り込むと、全身に強い症状が現れることがあります。皮膚が真っ赤に腫れ、やけどのようにただれる症状が全身に広がり、発熱や悪寒、体のだるさが伴います。この場合は、早急な治療が必要です。
とびひ(伝染性膿痂疹)になった時の対処法
とびひに感染した場合には、次のことに注意しましょう。
モノを共有しないように注意
使用したタオルや衣類、寝具は家族で共用しないようにしましょう。ドアノブや手すりなど、手が触れる場所は特に注意が必要です。触れた場所や物は、こまめに消毒を行ってください。
患部を触らない
とびひは、患部を触った手で他の部分に広がることがあるため、患部を触れないように注意しましょう。患部をしっかりとガーゼで覆い、掻かないようにすることが重要です。
医療機関を受診する
抗生物質を使用しないと治らないため、早期の医療機関の受診が重要です。小さな水疱を見つけた際には、自己判断せず、すぐに皮膚科や小児科を受診しましょう。自己判断で薬を塗ると、症状が悪化する恐れがあります。
とびひ(伝染性膿痂疹)の治療方法
とびひの治療は、主に外用薬と内服薬を使用します。
外用薬
抗生物質の軟膏(例:ゲンタマイシン、フシジン酸)は、患部に塗ることで、細菌を直接退治し、炎症を和らげる効果があります。1日数回塗布してください。
消毒作用のある液体(例:イソジン)は、細菌を殺菌し、感染の広がりを防ぎます。しかし、消毒薬は健康な皮膚にも刺激があるため、使用時には注意が必要です。
内服薬
広範囲に広がっている場合や全身症状を伴う場合は抗生物質を使用し、体内から細菌を退治します。代表的な内服薬は、セファクロルなどがあります。
とびひ(伝染性膿痂疹)の予防法は
予防には、日常的なケアと注意が必要です。ここでは、とびひを防ぐための基本的な対策を紹介します。
皮膚を清潔にする
皮膚や手指を常に清潔に保つことが重要です。虫刺されや湿疹、あせもなどの痒みがある場合、掻かないように注意し、辛い場合は早めに皮膚科を受診しましょう。
掻きむしらない
掻くことで症状が悪化し、細菌が広がりやすくなるため、掻かないように注意してください。爪を短く切ることで、掻いて皮膚を傷つけるリスクを減らしましょう。
鼻をいじらない
鼻を触る癖があると、鼻の周囲からとびひが始まることがあります。さらに、その手であせもや虫刺されを掻いてしまうと、細菌が感染し、とびひを引き起こす可能性があります。そのため、鼻を触らないように意識しましょう。
爪は短く切っておく
爪が長いと皮膚を傷つけやすく、細菌が入り込む可能性が高くなります。爪は常に短く切っておくことで予防に繋がります。
とびひは抗菌薬を使わないと治りにくいため、水疱ができたら皮膚科を受診しよう
放置すると感染が広がり、体のあちこちに症状が広がる可能性があります。とびひは、細菌による感染症のため、抗菌薬を使わないと治癒が遅れることがあります。症状を悪化させないためには、早めに皮膚科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ
症状が軽度な場合や時間が取れない場合には、オンライン診療を利用して対処することもおすすめです。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットを利用して、自宅で医師の診察を受けられるサービスです。スマートフォン、タブレット、またはパソコンを使って、ビデオチャットで医師と直接コミュニケーションを取れます。予約から問診、診断、処方箋の発行、支払いまで、すべてオンラインで完結できるため、忙しい方や外出が難しい方でも健康管理がしやすくなります。
SOKUYAKUとは
オンライン診療をよりスムーズに行えるサービスです。アプリを操作して、予約から薬の受け取りまで、すべてのステップを簡単に行えます。専門スタッフによるサポートや、クリニックや薬局の登録機能があり、お薬手帳をデジタル化することも可能です。また、全国どこでも(※一部離島を除く)当日または翌日に薬を受け取れます。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒
まとめ
アトピー性皮膚炎の人は、黄色ブドウ球菌が皮膚に増殖しやすいため、「とびひ(伝染性膿痂疹)」を発症しやすい傾向があります。とびひには、かゆみを伴う水疱が現れる「水疱性膿痂疹」や、かさぶたが厚くなる「痂皮性膿痂疹」などがあり、重症化すると「ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群」を引き起こすこともあるため注意が必要です。
予防するためには皮膚を清潔に保ち、皮膚を傷つけないようにしましょう。水疱が現れた場合は、放置せず早期に皮膚科を受診し、適切な治療を受けてください。
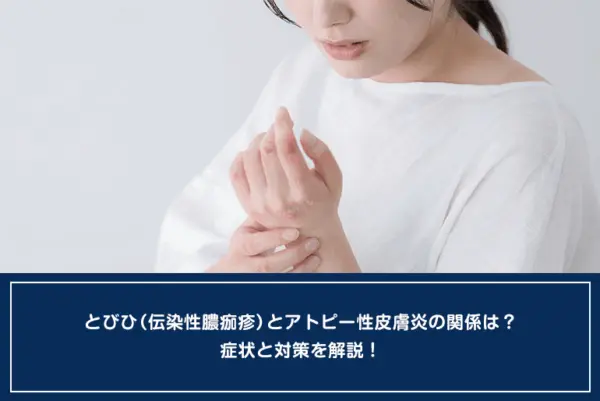
アトピー性皮膚炎のある人は、皮膚のバリア機能が低下しているため、感染症にかかりやすい傾向があります。「とびひ」は、皮膚の感染症で、強いかゆみや水疱、かさぶたができることが特徴です。とびひは掻き壊した傷口から菌が広がることで悪化しやすいため、注意しないといけません。今回は、アトピー性皮膚炎ととびひの関係、そして症状や対策について詳しく解説します。
アトピー性皮膚炎は感染を起こしやすい
アトピー性皮膚炎の肌は、健康な肌と比べて皮膚のバリア機能が弱くなっています。本来、皮膚は外部からの刺激や異物が体内に侵入するのを防ぎ、同時に体内の水分を保持する役割を果たしています。しかし、アトピー性皮膚炎の方の肌は乾燥しやすく、そのバリア機能が低下しているため、外部の刺激に対する抵抗力が弱くなっているのです。
黄色ブドウ球菌とアトピー性皮膚炎の関係
アトピー性皮膚炎の方の皮膚からは、黄色ブドウ球菌が高頻度に検出されます。アトピー性皮膚炎の方の肌で黄色ブドウ球菌は増殖しやすく、症状を悪化させる要因となります。
黄色ブドウ球菌とは
黄色ブドウ球菌は、自然界に広く存在し、人や動物の皮膚や粘膜にも常在している細菌です。その名前は、顕微鏡で観察するとブドウの房のように見える形から付けられました。健康な人の鼻や皮膚にも一定の割合で存在していますが、多くの場合は特に問題を引き起こしません。しかし、黄色ブドウ球菌はさまざまな毒素を産生し、免疫力が低下した人や傷口のある皮膚に感染すると、深刻な病気を引き起こすことがあります。
黄色ブドウ球菌が出す毒素がアトピー性皮膚炎を悪化させる
1.常在菌のバランスの崩れ
黄色ブドウ球菌が異常に増殖すると、皮膚の常在菌のバランスを崩し、角質層の細胞を傷つけることで炎症を引き起こす
2.皮膚バリアの破壊
産生する毒素や酵素が、皮膚の角質層を傷つけ、バリア機能を低下させる
3.免疫反応の過剰刺激
分泌する毒素が免疫系を過剰に刺激し、かゆみや炎症を悪化させることがある
4.皮膚の脂質分解
黄色ブドウ球菌が作り出す酵素が皮膚の脂質を分解し、乾燥やバリア機能の低下を引き起こすことがある
これらの要因が複合的に作用し、「負のスパイラル」を形成します。これが、黄色ブドウ球菌によってアトピー性皮膚炎が悪化する理由です。
遺伝的要因によって、皮膚バリアがさらに弱くなっている方では、黄色ブドウ球菌がより定着しやすくなり、感染のリスクが高まります。また、黄色ブドウ球菌はバイオフィルムと呼ばれる保護膜を作ることで、抗生物質や免疫細胞の攻撃から身を守るため、一度感染すると慢性化しやすく、治療が難しくなることもあります。
とびひ(伝染性膿痂疹)の原因
とびひは、主に水疱性膿痂疹と痂皮性膿痂疹の2種類があります。
黄色ブドウ球菌が原因の水疱性膿痂疹
黄色ブドウ球菌が原因で、乳幼児に多く見られます。虫刺されやあせも、アトピー性皮膚炎、すり傷などで皮膚のバリア機能が低下した部分に感染しやすく、高温多湿の夏に多発します。接触感染によって広がるため、幼稚園や保育所、学校での集団感染も起こりやすいことが特徴です。
溶連菌が原因の痂皮性膿痂疹
A群β溶血性連鎖球菌(溶連菌)が原因で、黄色ブドウ球菌が混合感染している場合もあります。季節や年齢を問わず発症し、子どもだけでなく大人にも見られます。アトピー性皮膚炎を持つ人に合併して起こることが多く、黄褐色のかさぶたができるのが特徴です。
とびひ(伝染性膿痂疹)の症状は
それぞれのタイプにわけて症状を紹介します。
かゆみの強い水疱ができる水疱性膿痂疹
水疱がかゆみを伴い、皮膚に小さな水疱が集まります。水疱は、数日で大きくなり、破れると赤いびらん(ただれた状態)になります。これにより、感染が広がりやすく、患部をかいた手で他の部位に触れると、新たな水疱ができてさらに広がることが特徴です。
黄褐色の厚いかさぶたが特徴の痂皮性膿痂疹
最初に小さな発赤が現れ、膿を含んだ膿疱ができ、最終的に黄褐色の厚いかさぶたに変わり、押すと膿が出ることがあります。また、リンパ節の腫れや発熱、のどの痛みを伴う場合もあります。
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群に要注意!
黄色ブドウ球菌の毒素が血液中に入り込むと、全身に強い症状が現れることがあります。皮膚が真っ赤に腫れ、やけどのようにただれる症状が全身に広がり、発熱や悪寒、体のだるさが伴います。この場合は、早急な治療が必要です。
とびひ(伝染性膿痂疹)になった時の対処法
とびひに感染した場合には、次のことに注意しましょう。
モノを共有しないように注意
使用したタオルや衣類、寝具は家族で共用しないようにしましょう。ドアノブや手すりなど、手が触れる場所は特に注意が必要です。触れた場所や物は、こまめに消毒を行ってください。
患部を触らない
とびひは、患部を触った手で他の部分に広がることがあるため、患部を触れないように注意しましょう。患部をしっかりとガーゼで覆い、掻かないようにすることが重要です。
医療機関を受診する
抗生物質を使用しないと治らないため、早期の医療機関の受診が重要です。小さな水疱を見つけた際には、自己判断せず、すぐに皮膚科や小児科を受診しましょう。自己判断で薬を塗ると、症状が悪化する恐れがあります。
とびひ(伝染性膿痂疹)の治療方法
とびひの治療は、主に外用薬と内服薬を使用します。
外用薬
抗生物質の軟膏(例:ゲンタマイシン、フシジン酸)は、患部に塗ることで、細菌を直接退治し、炎症を和らげる効果があります。1日数回塗布してください。
消毒作用のある液体(例:イソジン)は、細菌を殺菌し、感染の広がりを防ぎます。しかし、消毒薬は健康な皮膚にも刺激があるため、使用時には注意が必要です。
内服薬
広範囲に広がっている場合や全身症状を伴う場合は抗生物質を使用し、体内から細菌を退治します。代表的な内服薬は、セファクロルなどがあります。
とびひ(伝染性膿痂疹)の予防法は
予防には、日常的なケアと注意が必要です。ここでは、とびひを防ぐための基本的な対策を紹介します。
皮膚を清潔にする
皮膚や手指を常に清潔に保つことが重要です。虫刺されや湿疹、あせもなどの痒みがある場合、掻かないように注意し、辛い場合は早めに皮膚科を受診しましょう。
掻きむしらない
掻くことで症状が悪化し、細菌が広がりやすくなるため、掻かないように注意してください。爪を短く切ることで、掻いて皮膚を傷つけるリスクを減らしましょう。
鼻をいじらない
鼻を触る癖があると、鼻の周囲からとびひが始まることがあります。さらに、その手であせもや虫刺されを掻いてしまうと、細菌が感染し、とびひを引き起こす可能性があります。そのため、鼻を触らないように意識しましょう。
爪は短く切っておく
爪が長いと皮膚を傷つけやすく、細菌が入り込む可能性が高くなります。爪は常に短く切っておくことで予防に繋がります。
とびひは抗菌薬を使わないと治りにくいため、水疱ができたら皮膚科を受診しよう
放置すると感染が広がり、体のあちこちに症状が広がる可能性があります。とびひは、細菌による感染症のため、抗菌薬を使わないと治癒が遅れることがあります。症状を悪化させないためには、早めに皮膚科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ
症状が軽度な場合や時間が取れない場合には、オンライン診療を利用して対処することもおすすめです。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットを利用して、自宅で医師の診察を受けられるサービスです。スマートフォン、タブレット、またはパソコンを使って、ビデオチャットで医師と直接コミュニケーションを取れます。予約から問診、診断、処方箋の発行、支払いまで、すべてオンラインで完結できるため、忙しい方や外出が難しい方でも健康管理がしやすくなります。
SOKUYAKUとは
オンライン診療をよりスムーズに行えるサービスです。アプリを操作して、予約から薬の受け取りまで、すべてのステップを簡単に行えます。専門スタッフによるサポートや、クリニックや薬局の登録機能があり、お薬手帳をデジタル化することも可能です。また、全国どこでも(※一部離島を除く)当日または翌日に薬を受け取れます。
まとめ
アトピー性皮膚炎の人は、黄色ブドウ球菌が皮膚に増殖しやすいため、「とびひ(伝染性膿痂疹)」を発症しやすい傾向があります。とびひには、かゆみを伴う水疱が現れる「水疱性膿痂疹」や、かさぶたが厚くなる「痂皮性膿痂疹」などがあり、重症化すると「ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群」を引き起こすこともあるため注意が必要です。
予防するためには皮膚を清潔に保ち、皮膚を傷つけないようにしましょう。水疱が現れた場合は、放置せず早期に皮膚科を受診し、適切な治療を受けてください。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。