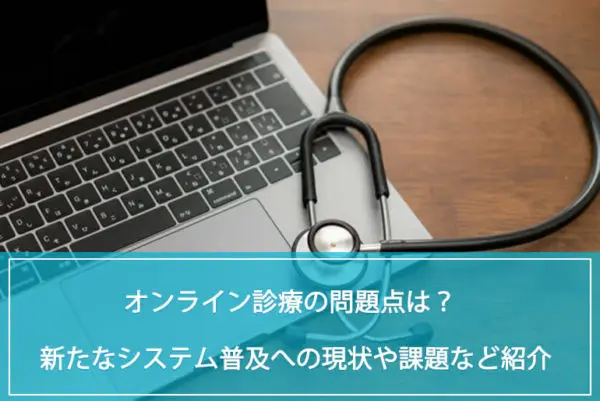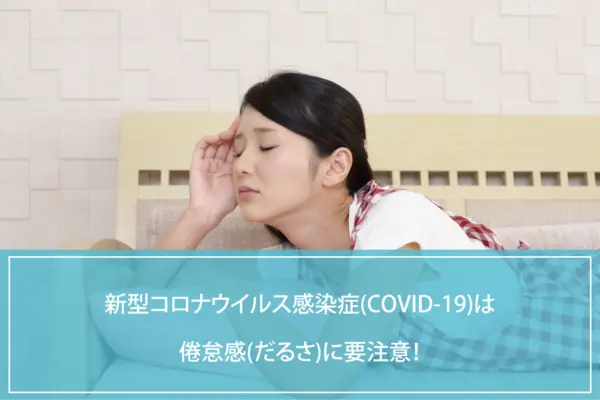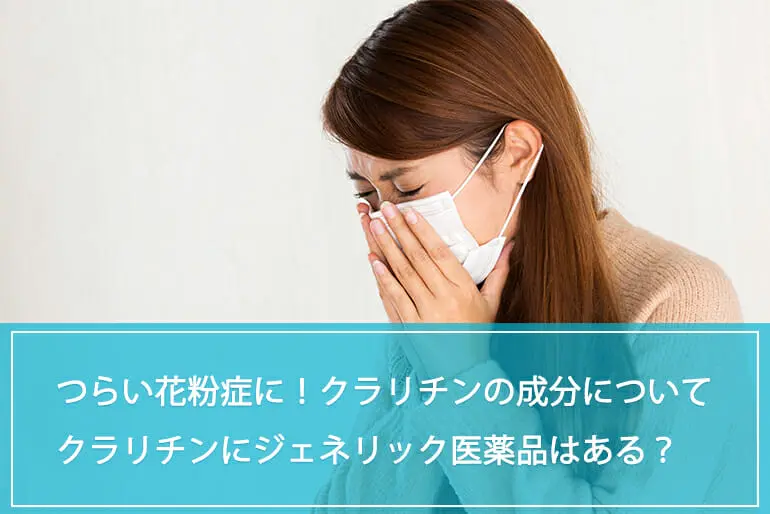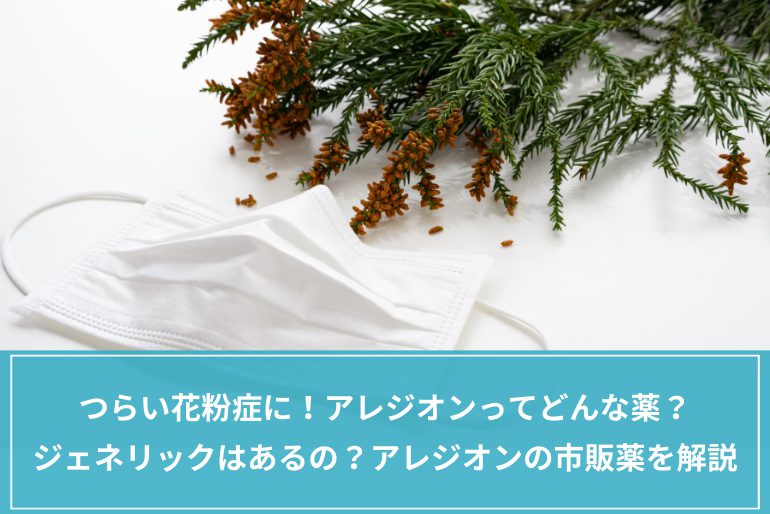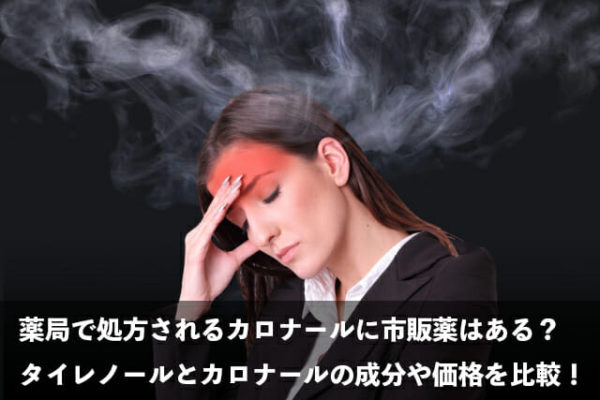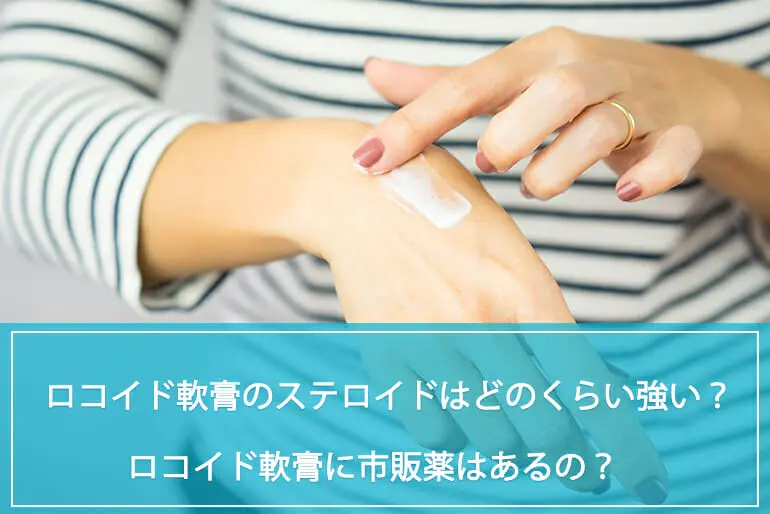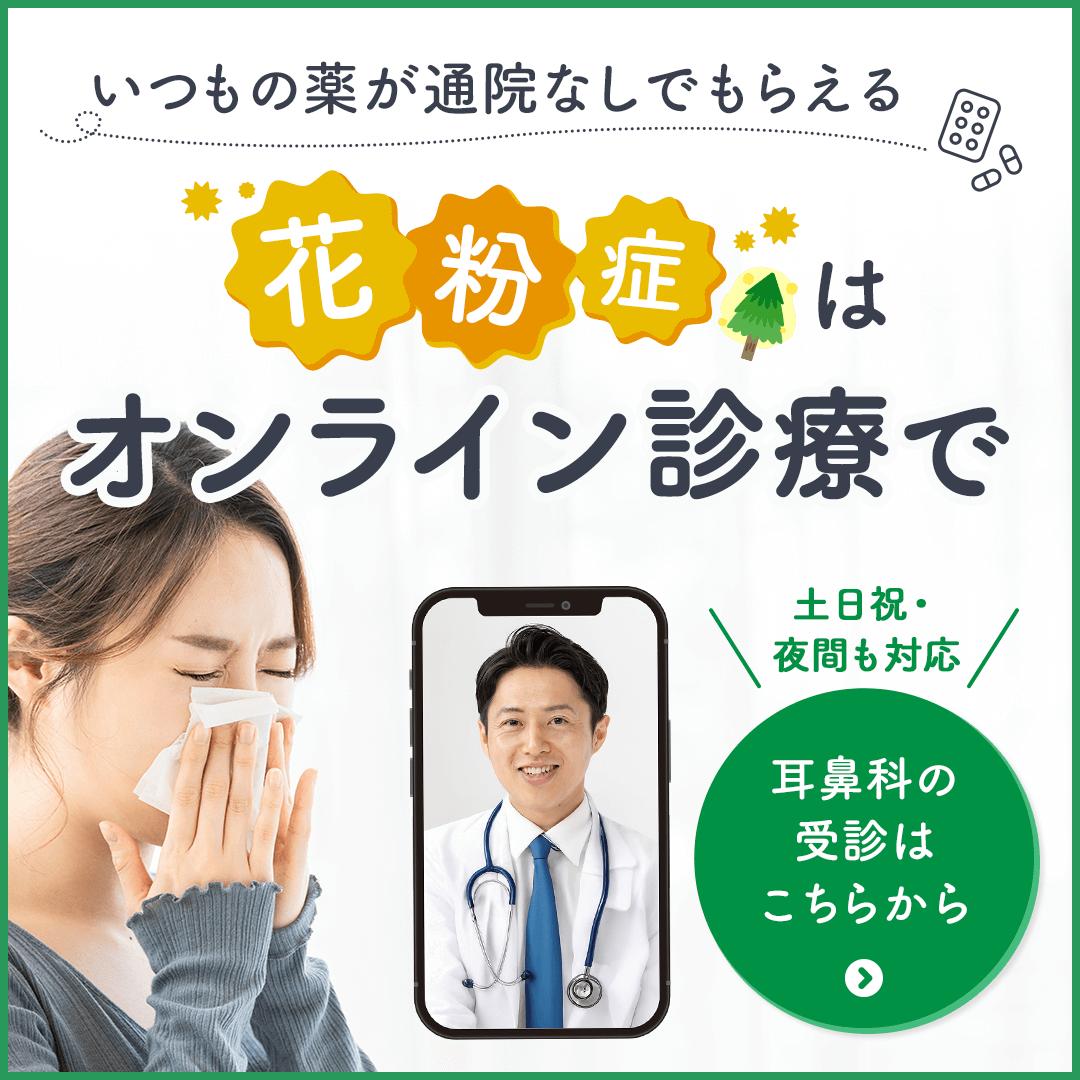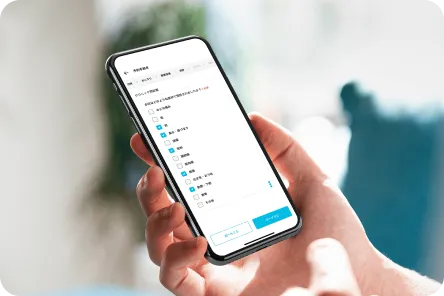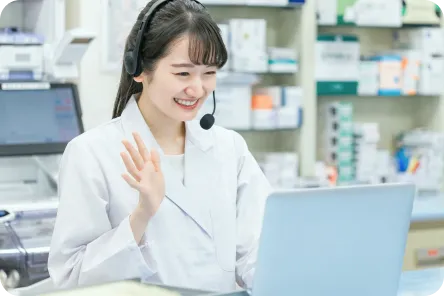薬局の受付時間や待ち時間のことを知って、薬局を上手に利用しよう
薬局の待ち時間は薬剤師が薬の安心・安全性を確認している
薬剤師は処方箋を確認し、他の薬との飲み合わせは大丈夫なのか、過去に処方された薬で副作用は起こっていないかを慎重に確認し、疑問が発生した場合は疑義照会(処方箋の内容について、発行した医師に問い合わせること)を行います。
安全性の確認ができたら薬のピッキング、分包や調合を行います。 そして、再度、確認をします。薬を安全にお渡しするために、薬剤師はこのようなことを行っているのです。
大まかに分類すると、「1.処方箋の受付」をし、「2.処方箋の入力」、「3.調剤」、「4.監査」、「5.投薬」の流れになります。
まず、病院から出された処方箋を医療事務または薬剤師が受付し、その内容を入力していきます。その後、薬剤師の一人が調剤をし、別の薬剤師が内容に間違いがないかダブルチェックをしています。
最後にカウンターで服薬指導の投薬をします。
なかでも大事なのは、お薬手帳や患者様からヒアリングを行い、同じお薬が出ていないか、服薬回数に間違いはないか、本当にこの処方箋内容で合っているかなどの疑義照会です。
ここで疑問点がある場合は処方箋を発行した医師への確認を行います。たとえば、前回歯医者さんからロキソニンが処方されているが、今回整形外科でまたロキソニンが処方されているなどの事例があります。
同じ薬なので、過剰に飲み過ぎることは健康を害してしまいます。その場合は薬局では勝手に処方箋の内容を変更をすることはできないので、医師に問い合わせをして、処方内容を確認します。
夜間や休日は医療費の金額が異なる
Array
「休日」は、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を指します。
そして、この「夜間」「休日」に調剤薬局に処方箋を出すと、医療費の自己負担が3割の場合、営業時間内の場合は1回につき120円、営業日・時間外の場合は基礎額(調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算)の30~60%が加算されます。
さらに、「夜間」「休日」に一定以上対応していたり、土曜日や「休日」に一定以上営業している調剤薬局は、地域医療に貢献できる体制ができている薬局として、医療費の自己負担が3割の場合、1回につき105円が加算されます。これは、処方箋を出した時間が夜間・休日でなくても加算される仕組みです。
これらの料金が加算されているかどうかは、領収書とともに渡される「調剤明細書」で確認できます。
Array
「薬局の営業時間」「処方箋の受付時間」を確認しよう
しかし、せっかくドラッグストアやスーパーに行っても、ドラッグストアがあいているのに、併設している調剤薬局が閉まっていたり、薬剤師が不在の時間で処方箋の受付や医薬品の販売を断られた経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
薬局で扱っている医薬品・医薬品外部の分類と、その販売や相談に当たれる職種を表で示すと次のようになります。
※1・・・利用者自身で選択できる医薬品(OTCは、「Over The Counter」の略)
※2・・・指定第2類医薬品を含む
薬剤師はすべての医薬品・医薬品外部の販売や相談に当たれますが、登録販売者(都道府県知事が資質認定した医薬品の専門家)や一般従事者は一部にしか関われません。
特に、医師の処方箋が原則として必要な「医療用医薬品」や、副作用などのリスクが特に高い「要指導医薬品」「第1類医薬品」については、法律上、薬剤師でなければ、相談をしたり、購入することができません(精算などの作業は、登録販売者や一般従事者でも可能です)。
また、厚生労働省の省令上、薬局の営業時間内は、薬剤師等の専門家が常駐することが決められていますが、いま薬剤師はたいへんな人手不足なので、大半のドラッグストアやスーパーでは、同じ店舗の中でも、薬局部分とその他の部分を分けて、それぞれ別々の営業時間を設定するところが多いです。
ドラッグストアやスーパーが営業していても、薬局部分が閉まっていることがあるのは、このような事情があるのです。
はじめに書いたようなことを避けるためにも、ドラッグストアやスーパーの中にある薬局を利用するときは、「薬局の営業時間」や「処方箋の受付時間」を確認してから出かけるようにしましょう。
事前に処方箋を渡すことで受付時間の短縮につながる
冒頭でお話しましたが、 医薬品の調剤にはさまざまな作業があります。例えば、処方箋の記載ミスや併用薬・禁忌薬の確認、処方箋の内容、お薬手帳、過去の薬剤服用歴などを確認します。疑問点がある場合は、処方した医師に問い合わせてから調剤をします。
また、医薬品を渡すときも、患者の状態を確認したり、医薬品の説明や服薬指導をしなければなりません。患者から質問があれば、相談にも応える必要があります。
患者の生命・健康に関わる作業なので、慎重さ、正確さが求められ、どうしても時間がかかってしまうのです。 しかし、すこしでも待ち時間を短くするための取り組みを実施している薬局も増えてきています。
病院の会計が終わったらFAXで処方箋を薬局に送っておくと、その時点から処方薬の準備ができるので、薬局に着いて処方箋を出す場合よりも短時間で医薬品の受け取りができます。
大きな病院には、処方箋送信専用のFAXを置いているところもあり、タッチパネルや専用のカードを入れるだけで送信できるので、活用してみましょう。
また、処方箋の写真を撮って、薬局に送信できる機能があるスマホアプリもあります。なかには薬局で独自に製作しているアプリもあるので、よく利用する薬局でアプリがあるかどうか確認してみるとよいでしょう。
FAXやアプリで予約をした後は、次のことに注意しましょう。
Array
なお、家族等の代理の方による受取も可能です。また、処方箋の受付時間は、FAX・アプリで送信した時間ではなく、薬局に処方箋の原本を渡した時間です。
ネットやアプリで処方箋の登録サービスを行う薬局が増えている
最近ではオンラインで診療・服薬指導を行っている病院・薬局も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。
オンライン診療は、
・受付や会計の待ち時間が短縮される。
・自宅や外出先で診療が受けられる。
・院内処方の場合くすりが自宅に届く。
・院内感染・二次感染のリスクがない。
などのメリットがあり、非常に便利なサービスです。
周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。
オンライン診療サービスSOKUYAKUについて詳しく見る

調剤薬局に対して「処方箋の受付時間を伸ばして欲しい」「休日も開けて欲しい」「待ち時間をもっと短くして欲しい」などの不満を感じたことはありませんか?
病院の診察時間に間に合ったのに、薬局の受付時間には間に合わなかった、という経験をされた方もいるもではないでしょうか。
また、仕事が忙しいときや、体調がすぐれないときは、薬局での待ち時間はとても長く感じるものです。またインフルエンザなど流行の時期などは待ち時間での2次感染も懸念されています。
今回は、そんな調剤薬局の「時間」について見ていきます。
薬局の待ち時間は薬剤師が薬の安心・安全性を確認している
薬剤師は処方箋を確認し、他の薬との飲み合わせは大丈夫なのか、過去に処方された薬で副作用は起こっていないかを慎重に確認し、疑問が発生した場合は疑義照会(処方箋の内容について、発行した医師に問い合わせること)を行います。
安全性の確認ができたら薬のピッキング、分包や調合を行います。 そして、再度、確認をします。薬を安全にお渡しするために、薬剤師はこのようなことを行っているのです。

大まかに分類すると、「1.処方箋の受付」をし、「2.処方箋の入力」、「3.調剤」、「4.監査」、「5.投薬」の流れになります。
まず、病院から出された処方箋を医療事務または薬剤師が受付し、その内容を入力していきます。その後、薬剤師の一人が調剤をし、別の薬剤師が内容に間違いがないかダブルチェックをしています。
最後にカウンターで服薬指導の投薬をします。
なかでも大事なのは、お薬手帳や患者様からヒアリングを行い、同じお薬が出ていないか、服薬回数に間違いはないか、本当にこの処方箋内容で合っているかなどの疑義照会です。
ここで疑問点がある場合は処方箋を発行した医師への確認を行います。たとえば、前回歯医者さんからロキソニンが処方されているが、今回整形外科でまたロキソニンが処方されているなどの事例があります。
同じ薬なので、過剰に飲み過ぎることは健康を害してしまいます。その場合は薬局では勝手に処方箋の内容を変更をすることはできないので、医師に問い合わせをして、処方内容を確認します。
夜間や休日は医療費の金額が異なる

調剤薬局の夜間・休日について、国の「調剤報酬」では、次のように決められています。 ※2020年4月時点
「夜間」は、次の時間帯を指します。
営業時間内の場合は、夜7時(土曜日は午後1時)~翌朝8時
営業時間外の場合は、夜6時~翌朝8時。そのうち夜10時~翌朝6時は「深夜」扱い
「休日」は、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を指します。
そして、この「夜間」「休日」に調剤薬局に処方箋を出すと、医療費の自己負担が3割の場合、営業時間内の場合は1回につき120円、営業日・時間外の場合は基礎額(調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算)の30~60%が加算されます。
さらに、「夜間」「休日」に一定以上対応していたり、土曜日や「休日」に一定以上営業している調剤薬局は、地域医療に貢献できる体制ができている薬局として、医療費の自己負担が3割の場合、1回につき105円が加算されます。これは、処方箋を出した時間が夜間・休日でなくても加算される仕組みです。
これらの料金が加算されているかどうかは、領収書とともに渡される「調剤明細書」で確認できます。
「調剤料」の項目に「時間外等加算」「夜間・休日等加算」
「調剤基本料」に「地域支援体制加算」
「薬局の営業時間」「処方箋の受付時間」を確認しよう

最近は、ドラッグストアやスーパーの中に調剤薬局を設けているところが増えてきました。医薬品の調剤をしてもらっている間に、お買い物ができてとても便利ですよね。
しかし、せっかくドラッグストアやスーパーに行っても、ドラッグストアがあいているのに、併設している調剤薬局が閉まっていたり、薬剤師が不在の時間で処方箋の受付や医薬品の販売を断られた経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
薬局で扱っている医薬品・医薬品外部の分類と、その販売や相談に当たれる職種を表で示すと次のようになります。

※1・・・利用者自身で選択できる医薬品(OTCは、「Over The Counter」の略)
※2・・・指定第2類医薬品を含む
薬剤師はすべての医薬品・医薬品外部の販売や相談に当たれますが、登録販売者(都道府県知事が資質認定した医薬品の専門家)や一般従事者は一部にしか関われません。
特に、医師の処方箋が原則として必要な「医療用医薬品」や、副作用などのリスクが特に高い「要指導医薬品」「第1類医薬品」については、法律上、薬剤師でなければ、相談をしたり、購入することができません(精算などの作業は、登録販売者や一般従事者でも可能です)。
また、厚生労働省の省令上、薬局の営業時間内は、薬剤師等の専門家が常駐することが決められていますが、いま薬剤師はたいへんな人手不足なので、大半のドラッグストアやスーパーでは、同じ店舗の中でも、薬局部分とその他の部分を分けて、それぞれ別々の営業時間を設定するところが多いです。
ドラッグストアやスーパーが営業していても、薬局部分が閉まっていることがあるのは、このような事情があるのです。
はじめに書いたようなことを避けるためにも、ドラッグストアやスーパーの中にある薬局を利用するときは、「薬局の営業時間」や「処方箋の受付時間」を確認してから出かけるようにしましょう。
事前に処方箋を渡すことで受付時間の短縮につながる
冒頭でお話しましたが、 医薬品の調剤にはさまざまな作業があります。例えば、処方箋の記載ミスや併用薬・禁忌薬の確認、処方箋の内容、お薬手帳、過去の薬剤服用歴などを確認します。疑問点がある場合は、処方した医師に問い合わせてから調剤をします。
また、医薬品を渡すときも、患者の状態を確認したり、医薬品の説明や服薬指導をしなければなりません。患者から質問があれば、相談にも応える必要があります。
患者の生命・健康に関わる作業なので、慎重さ、正確さが求められ、どうしても時間がかかってしまうのです。 しかし、すこしでも待ち時間を短くするための取り組みを実施している薬局も増えてきています。
病院の会計が終わったらFAXで処方箋を薬局に送っておくと、その時点から処方薬の準備ができるので、薬局に着いて処方箋を出す場合よりも短時間で医薬品の受け取りができます。
大きな病院には、処方箋送信専用のFAXを置いているところもあり、タッチパネルや専用のカードを入れるだけで送信できるので、活用してみましょう。
また、処方箋の写真を撮って、薬局に送信できる機能があるスマホアプリもあります。なかには薬局で独自に製作しているアプリもあるので、よく利用する薬局でアプリがあるかどうか確認してみるとよいでしょう。
FAXやアプリで予約をした後は、次のことに注意しましょう。
処方箋発行日から4日以内に処方箋を送信した調剤薬局に受取に行きましょう。
必ず処方箋の原本を持っていきましょう。
なお、家族等の代理の方による受取も可能です。また、処方箋の受付時間は、FAX・アプリで送信した時間ではなく、薬局に処方箋の原本を渡した時間です。
ネットやアプリで処方箋の登録サービスを行う薬局が増えている

最近ではオンラインで診療・服薬指導を行っている病院・薬局も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。
オンライン診療は、
・受付や会計の待ち時間が短縮される。
・自宅や外出先で診療が受けられる。
・院内処方の場合くすりが自宅に届く。
・院内感染・二次感染のリスクがない。
などのメリットがあり、非常に便利なサービスです。
周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。