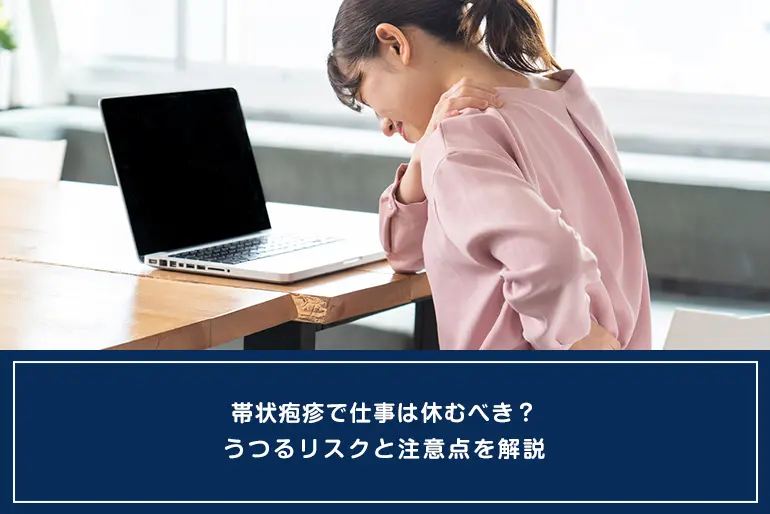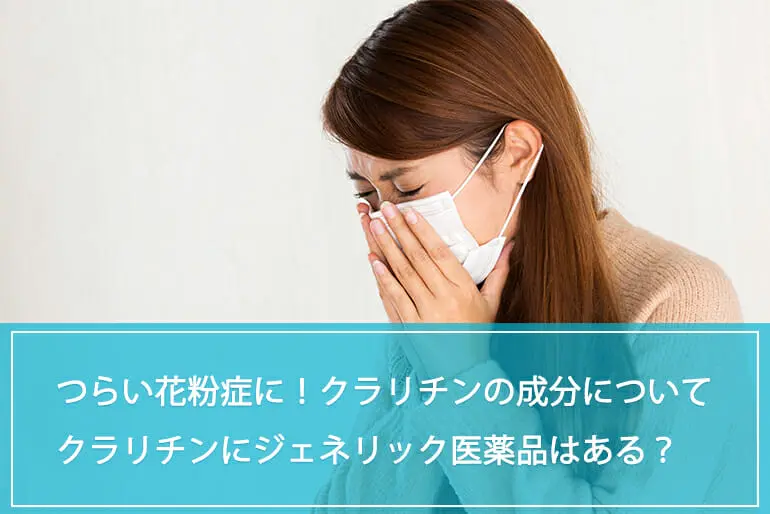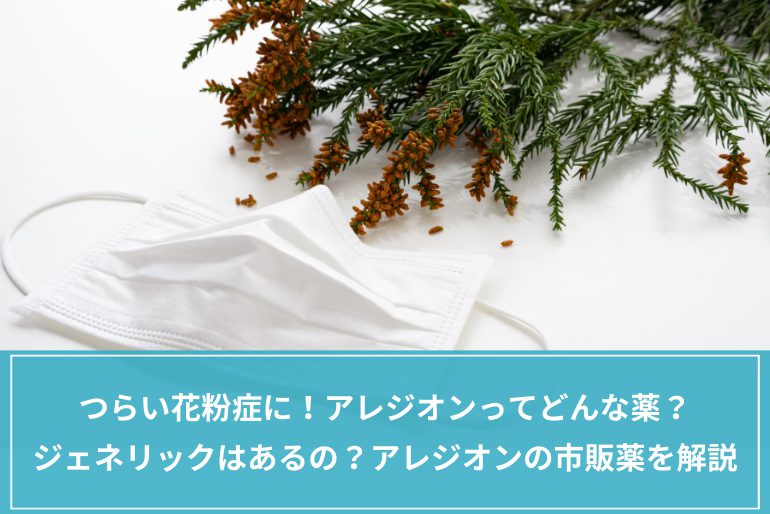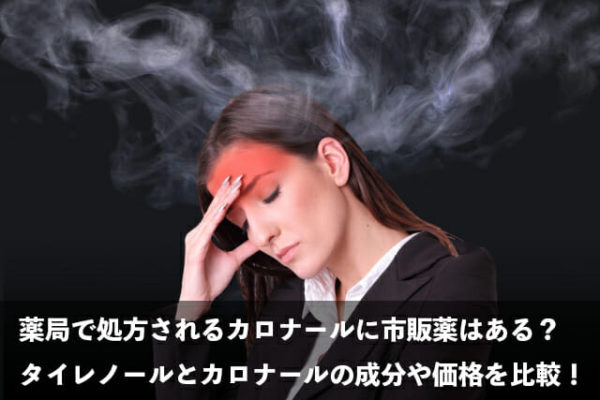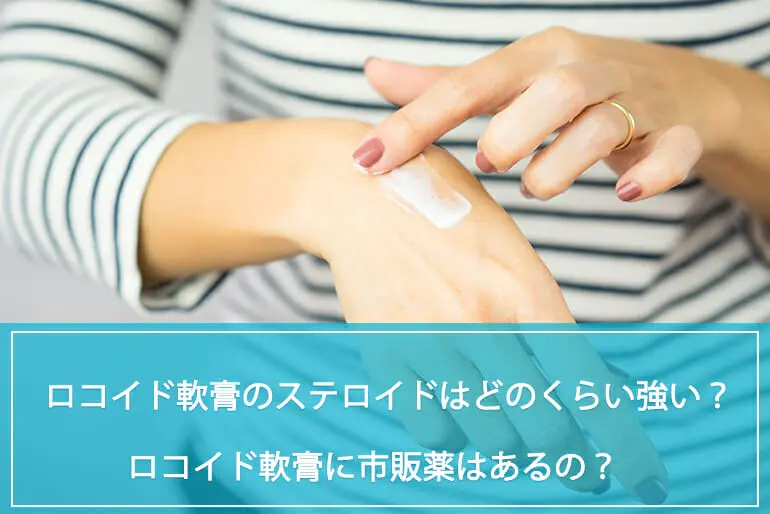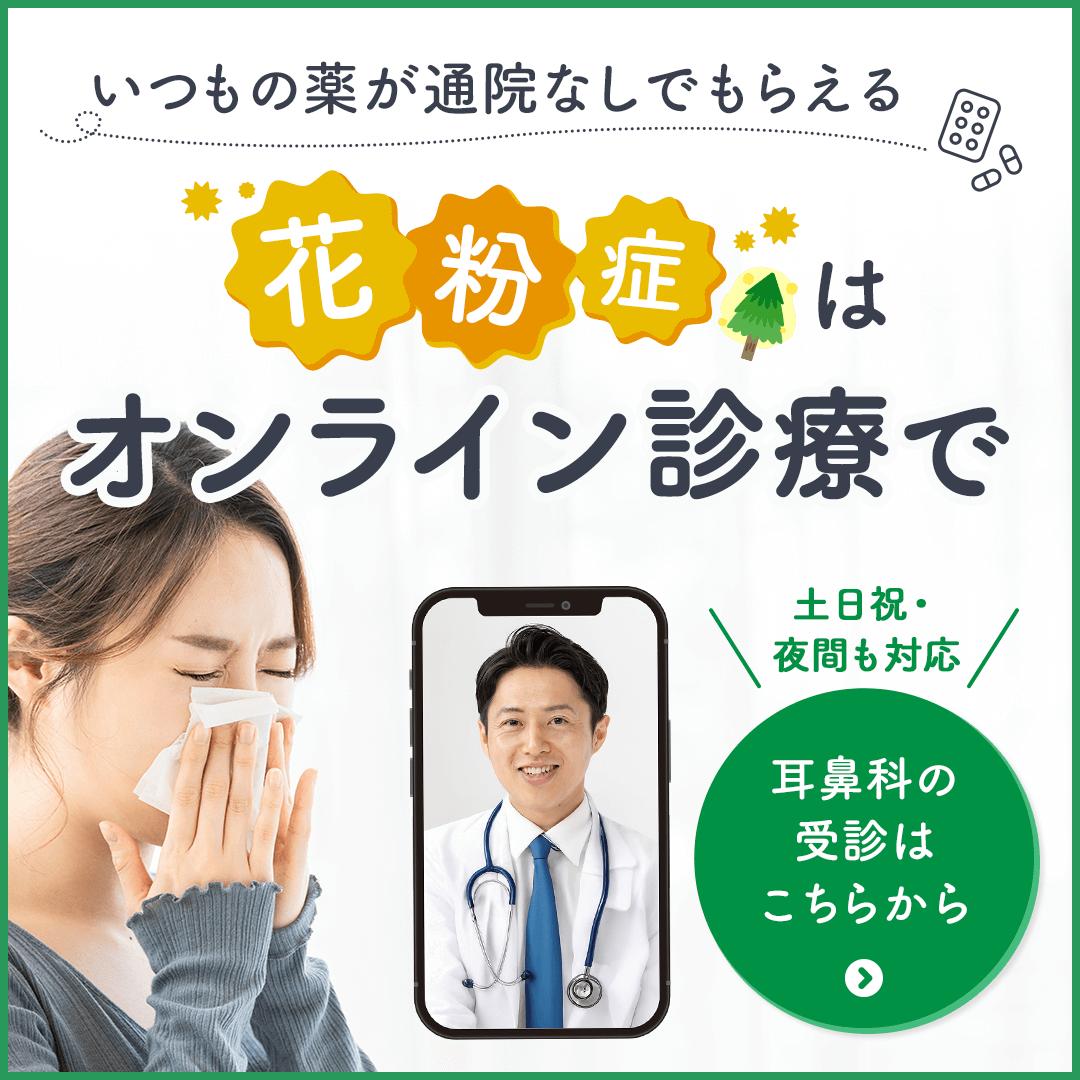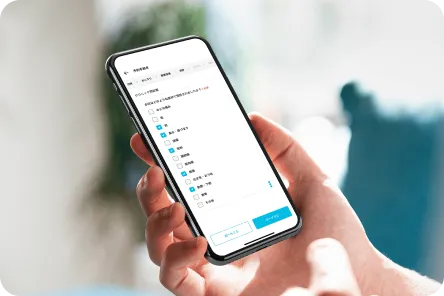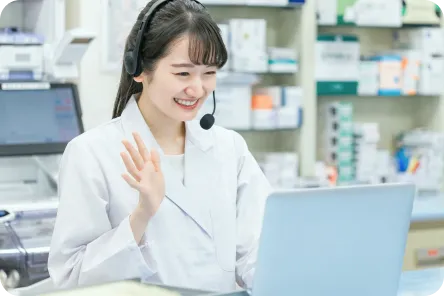温度差で発生する蕁麻疹(じんましん)、寒冷蕁麻疹とは?原因と対策について解説!
寒冷蕁麻疹(寒暖差アレルギー)とは
寒冷蕁麻疹は、冷たい刺激が皮膚に加わることで発症する蕁麻疹の一種です。皮膚内の肥満細胞からヒスタミンが放出されることによって、かゆみや炎症、膨疹と呼ばれる皮膚の赤い盛り上がりが現れます。膨疹は一過性の真皮の浮腫で突然発生し、境界がはっきりしているのが特徴です。
寒冷蕁麻疹は、子どもから高齢者まで幅広い年齢層で見られ、特定の年代に好発するわけではありません。冷たい環境や刺激をきっかけに発症するため、日常生活の中で注意が必要です。また、全身性寒冷蕁麻疹の中には、遺伝的な要因が関与しているケースも報告されています。
寒冷蕁麻疹(じんましん)の症状
寒冷蕁麻疹の症状は、膨疹(皮膚の盛り上がり)とかゆみが特徴的です。寒冷刺激や寒暖差を受けてから数分後から数十分後に症状が現れ、膨疹や赤みは多くの場合、数十分から数時間で自然に消失します。ただし、場合によっては半日から1日ほど続くこともあります。
寒冷蕁麻疹には、「局所性」と「全身性」の2種類があります。寒冷蕁麻疹のほとんどは局所性です。いずれの場合も時間の経過とともに症状は消え、跡が残ることはありません。ただし、再度冷たい刺激を受けると同じような症状が繰り返し現れることがあるため、注意しましょう。
局所性寒冷蕁麻疹
局所性寒冷蕁麻疹は、冷たい物質が皮膚に直接触れた部分に症状が現れるタイプの蕁麻疹です。円形や地図状の膨疹が生じ、通常はかゆみと発赤を伴いますが、個人差があり、かゆみがなく発赤だけが目立つ場合や、発赤がなくかゆみだけが生じる場合もあります。また、場合によっては痛みを伴うこともあります。
全身性寒冷蕁麻疹
全身性寒冷蕁麻疹は、全身が冷えることによって発症します。小豆大の膨疹が腕や脚、背中、腹部、首まわりなど全身に広がり、発赤とかゆみを伴うのが特徴です。この症状は、運動や入浴後に発症するコリン性蕁麻疹と外見が似ているため、区別がつきにくいことがあります。
寒暖差が起こりやすい状況
寒暖差とは、昼夜や季節の移り変わり、または室内外の環境の違いによる気温の変化のことです。一日の中での最高気温と最低気温の差、前日との気温差、室内外の温度差などがあげられます。
一般的に、寒暖差が7℃以上になると、体への影響が出やすいとされています。特に、暖かさと寒さを交互に感じるような大きな気温差がある場合、体が寒暖差の影響を受けやすくなるため注意しましょう。
寒冷蕁麻疹が発生しやすい寒暖差は、局所性と全身性でも違ってきます。
局所性寒冷蕁麻疹
こういった日常的な行動が発症の原因となります。冷水や冷風といった寒冷刺激が触れた部位にのみ症状が現れるのが特徴です。
全身性寒冷蕁麻疹
全身が冷えることが引き金となります。中でも、暖かい環境から急に冷えた環境へ移動する寒暖差が大きい場合に、特に症状が出やすい傾向があります。
寒冷蕁麻疹(じんましん)の予防方法
大切なのは「寒暖差をできるだけ避けること」です。短時間だからと薄着で寒い外に出たり、お風呂上がりに湯冷めをしていないかなど、日常生活の中で体を冷やしやすい行動を見直しましょう。小さな工夫を積み重ねることで予防に繋がります。
身体を冷やさない
体が急激に冷えないようにすることが重要です。寒暖差の影響を和らげるために、マフラーや手袋を着用し、重ね着で体温を調節する工夫をしましょう。外出時には、玄関や建物内で体を寒さに慣らしてからゆっくり外に出るようにすると、急激な温度変化を防げます。また、冷たい空気を吸い込まないよう、マスクを着用することも効果的です。
また、冷たいフローリングの上を素足で歩くことでも寒冷蕁麻疹が現れることがあるため、室内ではスリッパや靴下を履くといった工夫を検討してください。夏場でも予防するには、エアコンが効いた室内で体が冷えすぎないよう工夫することが大切です。羽織物やレッグウォーマーを活用して体温を調整し、冷気から肌を守りましょう。
また、冷たい飲み物やアイス、かき氷などは避けるか、少量ずつ様子を見ながら摂取してください。お風呂上がりに冷たい物を摂取したり、熱いサウナの後に冷たい水風呂に入ったりする行動は避けるようにしましょう。
環境を整える
暖房が効いた室内に長時間いると外出時に気温差が生じるため、外出前には暖房の電源を切り、室内の温度を徐々に外気温に近づけておきましょう。これにより、外出時の急激な温度変化を和らげ、体が寒暖差に適応しやすくなります。
体調を整える
蕁麻疹は、体調が優れないときに現れやすくなります。そのため、十分な睡眠をとり、栄養バランスの良い食事を心がけてください。また、適度な運動を取り入れ、ストレスをため込まないように意識することも重要です。
忙しい時期は心身のバランスが崩れやすく、アレルギー症状が悪化する可能性があるため、無理をしすぎず、自分の体調を最優先にケアするようにしましょう。
寒冷蕁麻疹(じんましん)が出た場合の対策
寒冷蕁麻疹の症状に対して、冷やしてしまうと逆効果になります。以下の方法を試してみてください。
患部を温める
対処法として最も効果的なのは、症状が出ている部位や全身を「温めること」です。多くの場合、時間の経過とともに自然と落ち着きますが、かゆみが辛い場合は患部を温めることで緩和できます。
安静にする
かゆみが強い場合でも、掻きむしるのは避けましょう。掻き壊しによって蕁麻疹が広がったり、症状が悪化する可能性があるため注意が必要です。
病院を受診する
症状がなかなか治まらない場合や再発を繰り返す場合は、早めに医療機関を受診しましょう。皮膚科では、寒冷負荷試験と呼ばれる方法で実際に氷を肌に当てて症状の出方を確認する検査や、血液検査を行うことで、寒冷蕁麻疹の原因や適切な治療法を特定することが可能です。
蕁麻疹(じんましん)が辛いときは皮膚科を受診しよう
繰り返し症状が現れる場合や、全身に広がる症状が見られる場合は、早めに病院を受診しましょう。専門医の診察を受けることで、原因を特定し、症状の悪化や再発を防ぐ助けとなります。
忙しくて通院できない場合はオンライン診療がおすすめ
忙しくて病院に行く時間が取れない場合には、オンライン診療を活用してください。時間の節約にもなるため、忙しい方にとって効率的かつ便利なサービスです。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットを利用して、自宅などにいながら医師の診察を受けられる医療サービスです。スマートフォンやタブレット、パソコンを通じて、ビデオチャットで医師と直接話せるため、通院する手間が省けます。診察の予約や問診、診断、薬の処方箋の発行、さらには支払いまで、すべてをオンライン上で完結できるのが特徴です。忙しい方や移動が難しい方にとって、時間と手間を大幅に軽減できます。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をよりスムーズに利用できるサービスです。診察の予約からお薬の受け取りまで、すべての手続きがアプリで簡単に行えるよう設計されています。専門スタッフによるサポート機能があり、初めての方でも安心して利用することが可能です。
よく利用するクリニックや薬局をお気に入り登録することで、次回以降の予約や利用がさらに簡単になります。さらに、お薬手帳をデジタル化する機能も備わっており、薬の管理が便利に行えます。SOKUYAKUは全国どこでも対応しており、当日または翌日にお薬を受け取れるため、忙しい方や通院が難しい方にもおすすめのサービスです。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒
まとめ
寒冷蕁麻疹は、寒暖差や体が冷えることが原因で、肌に赤みや腫れが生じる蕁麻疹です。寒い環境で身体を冷やさない工夫や適切な環境管理、体調を整えることで予防しましょう。発症した場合には、患部を温めることで症状が緩和されることがあります。ただし、症状が重かったり、日常生活に支障をきたす場合は、早めに皮膚科を受診して専門的な治療を受けてください。寒暖差に負けないためにも、日々の対策をしっかり行い、健康的な肌を保つよう心がけましょう。

「寒い場所に出ると、なぜか肌が赤く腫れてかゆくなる」こういった症状にお悩みではありませんか?これは「寒冷蕁麻疹」という蕁麻疹かもしれません。冬場や急激な温度変化のある環境で発症しやすく、日常生活に影響を及ぼすこともあります。この記事では、寒冷蕁麻疹の症状や原因について詳しく説明し、予防や対策のポイントを分かりやすくお伝えします。
寒冷蕁麻疹(寒暖差アレルギー)とは
寒冷蕁麻疹は、冷たい刺激が皮膚に加わることで発症する蕁麻疹の一種です。皮膚内の肥満細胞からヒスタミンが放出されることによって、かゆみや炎症、膨疹と呼ばれる皮膚の赤い盛り上がりが現れます。膨疹は一過性の真皮の浮腫で突然発生し、境界がはっきりしているのが特徴です。
寒冷蕁麻疹は、子どもから高齢者まで幅広い年齢層で見られ、特定の年代に好発するわけではありません。冷たい環境や刺激をきっかけに発症するため、日常生活の中で注意が必要です。また、全身性寒冷蕁麻疹の中には、遺伝的な要因が関与しているケースも報告されています。
寒冷蕁麻疹(じんましん)の症状
寒冷蕁麻疹の症状は、膨疹(皮膚の盛り上がり)とかゆみが特徴的です。寒冷刺激や寒暖差を受けてから数分後から数十分後に症状が現れ、膨疹や赤みは多くの場合、数十分から数時間で自然に消失します。ただし、場合によっては半日から1日ほど続くこともあります。
寒冷蕁麻疹には、「局所性」と「全身性」の2種類があります。寒冷蕁麻疹のほとんどは局所性です。いずれの場合も時間の経過とともに症状は消え、跡が残ることはありません。ただし、再度冷たい刺激を受けると同じような症状が繰り返し現れることがあるため、注意しましょう。
局所性寒冷蕁麻疹
局所性寒冷蕁麻疹は、冷たい物質が皮膚に直接触れた部分に症状が現れるタイプの蕁麻疹です。円形や地図状の膨疹が生じ、通常はかゆみと発赤を伴いますが、個人差があり、かゆみがなく発赤だけが目立つ場合や、発赤がなくかゆみだけが生じる場合もあります。また、場合によっては痛みを伴うこともあります。
全身性寒冷蕁麻疹
全身性寒冷蕁麻疹は、全身が冷えることによって発症します。小豆大の膨疹が腕や脚、背中、腹部、首まわりなど全身に広がり、発赤とかゆみを伴うのが特徴です。この症状は、運動や入浴後に発症するコリン性蕁麻疹と外見が似ているため、区別がつきにくいことがあります。
寒暖差が起こりやすい状況
寒暖差とは、昼夜や季節の移り変わり、または室内外の環境の違いによる気温の変化のことです。一日の中での最高気温と最低気温の差、前日との気温差、室内外の温度差などがあげられます。
一般的に、寒暖差が7℃以上になると、体への影響が出やすいとされています。特に、暖かさと寒さを交互に感じるような大きな気温差がある場合、体が寒暖差の影響を受けやすくなるため注意しましょう。
寒冷蕁麻疹が発生しやすい寒暖差は、局所性と全身性でも違ってきます。
局所性寒冷蕁麻疹
- 冷たい水で手を洗う
- 氷に触れる
- 冷風が肌に当たる
こういった日常的な行動が発症の原因となります。冷水や冷風といった寒冷刺激が触れた部位にのみ症状が現れるのが特徴です。
全身性寒冷蕁麻疹
- 暑い場所から急に冷房の効いた部屋に入る
- プールや海などで冷たい水に浸かる
- 素足で冷たい床を歩く
- 冷たい飲み物や食べ物を摂取する
- 運動後や入浴後に体が急激に冷える
全身が冷えることが引き金となります。中でも、暖かい環境から急に冷えた環境へ移動する寒暖差が大きい場合に、特に症状が出やすい傾向があります。
寒冷蕁麻疹(じんましん)の予防方法
大切なのは「寒暖差をできるだけ避けること」です。短時間だからと薄着で寒い外に出たり、お風呂上がりに湯冷めをしていないかなど、日常生活の中で体を冷やしやすい行動を見直しましょう。小さな工夫を積み重ねることで予防に繋がります。
身体を冷やさない
体が急激に冷えないようにすることが重要です。寒暖差の影響を和らげるために、マフラーや手袋を着用し、重ね着で体温を調節する工夫をしましょう。外出時には、玄関や建物内で体を寒さに慣らしてからゆっくり外に出るようにすると、急激な温度変化を防げます。また、冷たい空気を吸い込まないよう、マスクを着用することも効果的です。
また、冷たいフローリングの上を素足で歩くことでも寒冷蕁麻疹が現れることがあるため、室内ではスリッパや靴下を履くといった工夫を検討してください。夏場でも予防するには、エアコンが効いた室内で体が冷えすぎないよう工夫することが大切です。羽織物やレッグウォーマーを活用して体温を調整し、冷気から肌を守りましょう。
また、冷たい飲み物やアイス、かき氷などは避けるか、少量ずつ様子を見ながら摂取してください。お風呂上がりに冷たい物を摂取したり、熱いサウナの後に冷たい水風呂に入ったりする行動は避けるようにしましょう。
環境を整える
暖房が効いた室内に長時間いると外出時に気温差が生じるため、外出前には暖房の電源を切り、室内の温度を徐々に外気温に近づけておきましょう。これにより、外出時の急激な温度変化を和らげ、体が寒暖差に適応しやすくなります。
体調を整える
蕁麻疹は、体調が優れないときに現れやすくなります。そのため、十分な睡眠をとり、栄養バランスの良い食事を心がけてください。また、適度な運動を取り入れ、ストレスをため込まないように意識することも重要です。
忙しい時期は心身のバランスが崩れやすく、アレルギー症状が悪化する可能性があるため、無理をしすぎず、自分の体調を最優先にケアするようにしましょう。
寒冷蕁麻疹(じんましん)が出た場合の対策
寒冷蕁麻疹の症状に対して、冷やしてしまうと逆効果になります。以下の方法を試してみてください。
患部を温める
対処法として最も効果的なのは、症状が出ている部位や全身を「温めること」です。多くの場合、時間の経過とともに自然と落ち着きますが、かゆみが辛い場合は患部を温めることで緩和できます。
安静にする
かゆみが強い場合でも、掻きむしるのは避けましょう。掻き壊しによって蕁麻疹が広がったり、症状が悪化する可能性があるため注意が必要です。
病院を受診する
症状がなかなか治まらない場合や再発を繰り返す場合は、早めに医療機関を受診しましょう。皮膚科では、寒冷負荷試験と呼ばれる方法で実際に氷を肌に当てて症状の出方を確認する検査や、血液検査を行うことで、寒冷蕁麻疹の原因や適切な治療法を特定することが可能です。
蕁麻疹(じんましん)が辛いときは皮膚科を受診しよう
繰り返し症状が現れる場合や、全身に広がる症状が見られる場合は、早めに病院を受診しましょう。専門医の診察を受けることで、原因を特定し、症状の悪化や再発を防ぐ助けとなります。
忙しくて通院できない場合はオンライン診療がおすすめ
忙しくて病院に行く時間が取れない場合には、オンライン診療を活用してください。時間の節約にもなるため、忙しい方にとって効率的かつ便利なサービスです。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットを利用して、自宅などにいながら医師の診察を受けられる医療サービスです。スマートフォンやタブレット、パソコンを通じて、ビデオチャットで医師と直接話せるため、通院する手間が省けます。診察の予約や問診、診断、薬の処方箋の発行、さらには支払いまで、すべてをオンライン上で完結できるのが特徴です。忙しい方や移動が難しい方にとって、時間と手間を大幅に軽減できます。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をよりスムーズに利用できるサービスです。診察の予約からお薬の受け取りまで、すべての手続きがアプリで簡単に行えるよう設計されています。専門スタッフによるサポート機能があり、初めての方でも安心して利用することが可能です。
よく利用するクリニックや薬局をお気に入り登録することで、次回以降の予約や利用がさらに簡単になります。さらに、お薬手帳をデジタル化する機能も備わっており、薬の管理が便利に行えます。SOKUYAKUは全国どこでも対応しており、当日または翌日にお薬を受け取れるため、忙しい方や通院が難しい方にもおすすめのサービスです。
まとめ
寒冷蕁麻疹は、寒暖差や体が冷えることが原因で、肌に赤みや腫れが生じる蕁麻疹です。寒い環境で身体を冷やさない工夫や適切な環境管理、体調を整えることで予防しましょう。発症した場合には、患部を温めることで症状が緩和されることがあります。ただし、症状が重かったり、日常生活に支障をきたす場合は、早めに皮膚科を受診して専門的な治療を受けてください。寒暖差に負けないためにも、日々の対策をしっかり行い、健康的な肌を保つよう心がけましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。