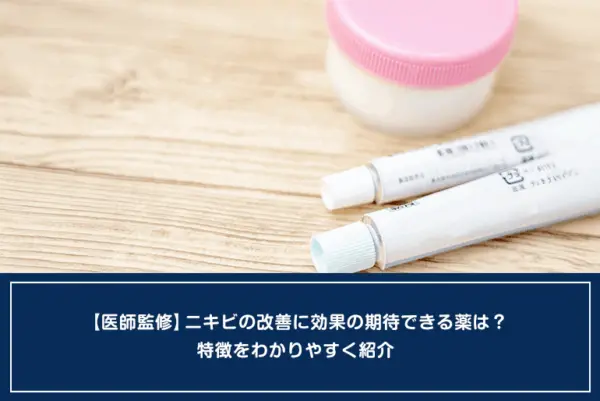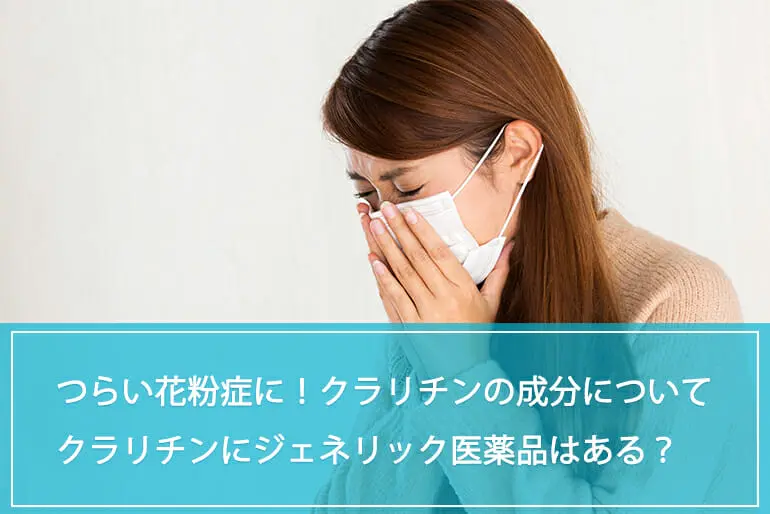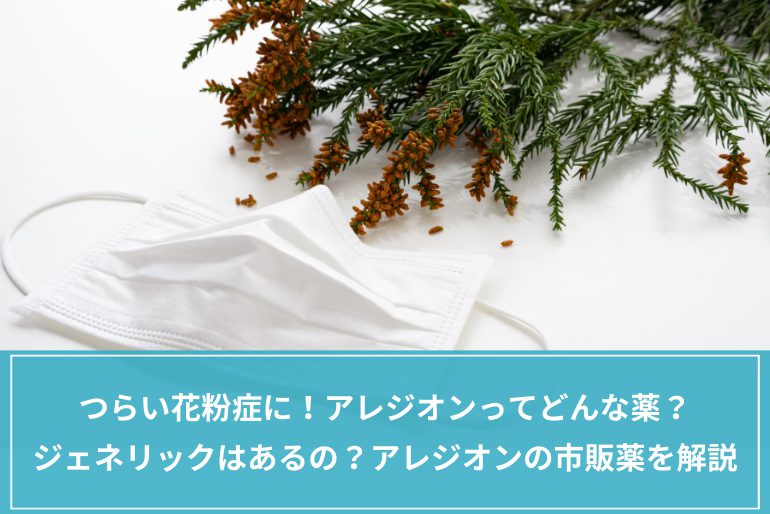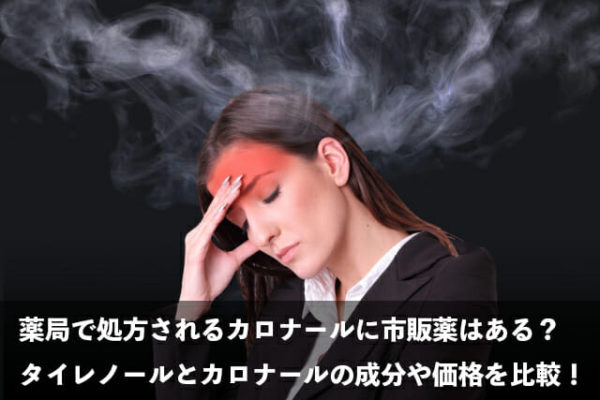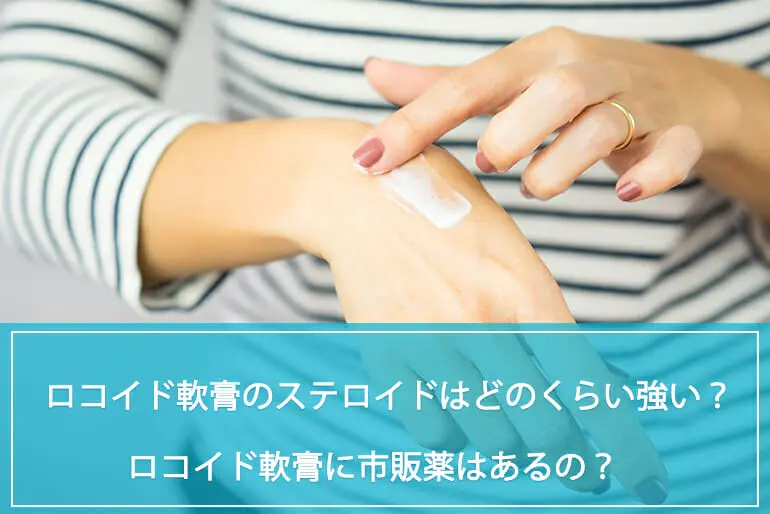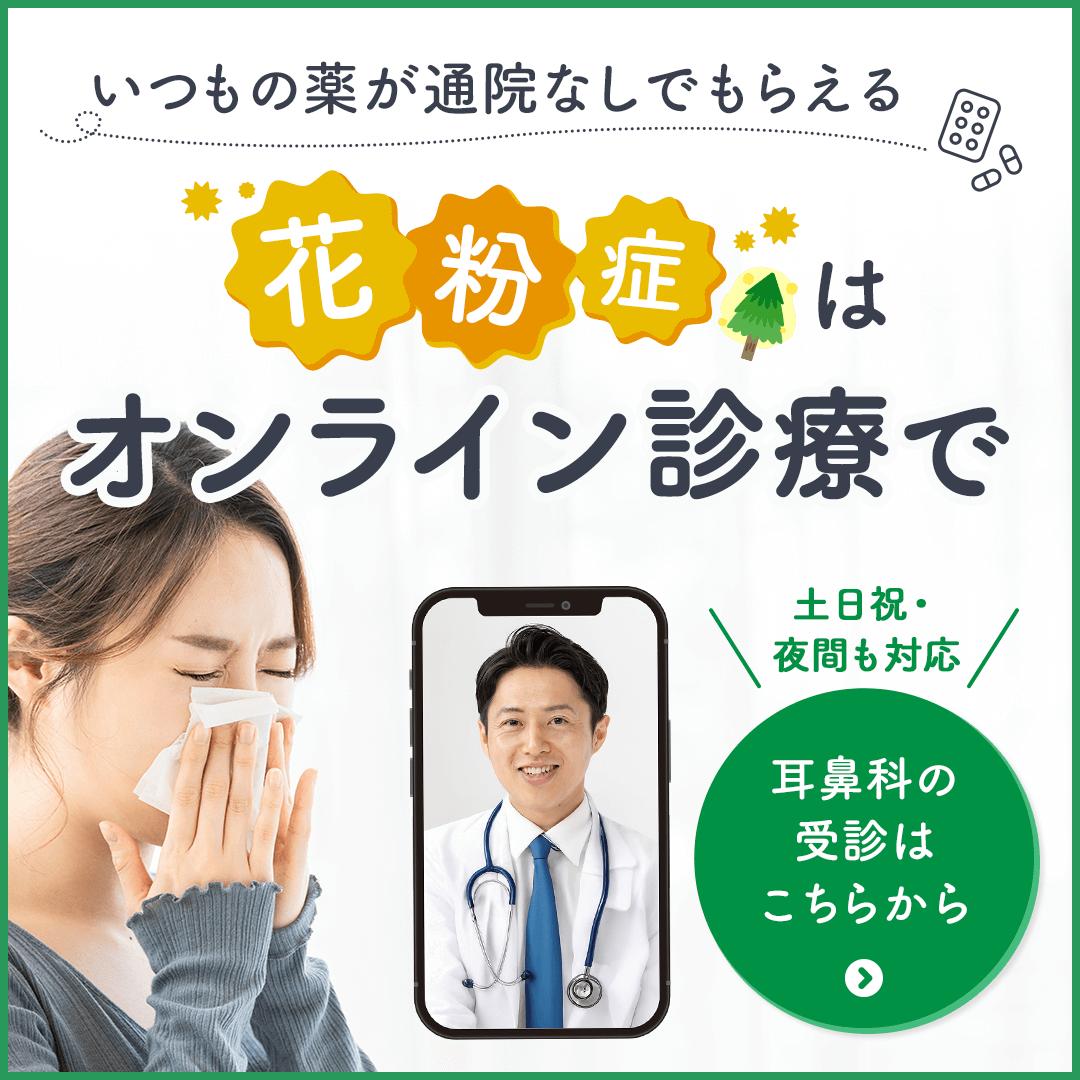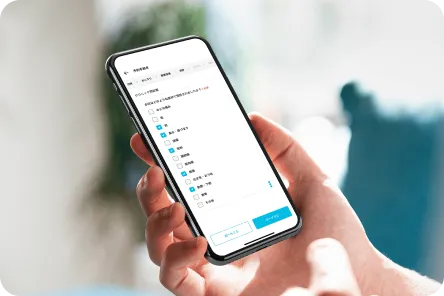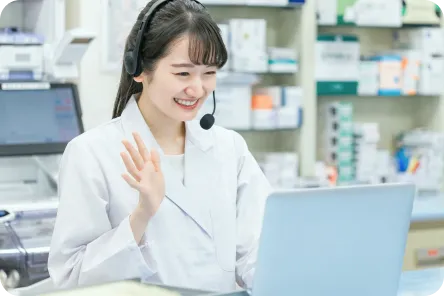食べ物で起こる蕁麻疹(じんましん)とは?原因になる食べ物や対処方法を解説!
食べ物が原因で蕁麻疹(じんましん)は起こる?
食べ物による刺激によって、蕁麻疹が発生することがあります。食べ物によって起こる蕁麻疹には、アレルギー性蕁麻疹と非アレルギー性蕁麻疹が考えられます。
食べ物が原因のアレルギー性蕁麻疹(じんましん)は子供に多い
体には、病気を引き起こす細菌やウイルスを防ぐための免疫システムがありますが、アレルギーがある子どもでは、本来無害であるはずの食べ物に対しても免疫が反応してしまいます。この免疫の過剰反応により、かゆみや皮膚の赤み、蕁麻疹などの症状が出ることがあります。
アレルギーで蕁麻疹が起こる仕組み
アレルギーのある食べ物で蕁麻疹が出るのは、特定の食べ物を食べた際に体が過剰に反応してしまうことが原因です。通常、私たちの免疫システムは細菌やウイルスのような有害なものから体を守る役割を果たしています。しかし、本来無害であるはずの食べ物を「有害」と認識してしまい、それを排除しようとする反応が過剰に起こります。その結果、かゆみや蕁麻疹、腹痛、吐き気、さらには呼吸困難などの症状が現れることがあります。
IgE依存性アレルギー反応は、アレルゲンが体内に入ると免疫系が過剰に反応してしまう仕組みです。この反応は、最初にアレルゲンが体内に侵入した際に、体がその物質に対してIgE抗体を作ることで始まります。一度IgE抗体が作られると、次回以降に同じアレルゲンが体内に入った際、体内でヒスタミンなどの物質が放出され、アレルギー症状を引き起こしてしまうのです。
この反応はアレルゲンの摂取から2時間以内に症状が出るため、「即時型アレルギー」と呼ばれています。
食物アレルギー性蕁麻疹の原因になりやすい食べ物
食物アレルギー性蕁麻疹の特徴として、特定の食品を摂取すると毎回蕁麻疹が現れる傾向があります。このため、皮膚検査や血液検査を行うことで比較的簡単に原因を特定することが可能です。
・鶏卵
・牛乳
・小麦
・木の実類
・落花生
・果物類
・魚卵類
・甲殻類
・そば
・大豆
・魚
鶏卵や牛乳、小麦といった基本的な食材は、小さな子どもにアレルギーを引き起こすことが多い食品です。木の実類や落花生は、少量でも強いアレルギー反応を引き起こす場合があるため、注意しましょう。また、果物類や魚卵、エビやカニなどの甲殻類、そば、大豆、魚などもアレルギーの原因となることがあります。
食べ物による非アレルギー性の蕁麻疹(じんましん)もある
青魚や肉類、タケノコ、ほうれん草などの食べ物で蕁麻疹が出る場合、その原因はアレルギー性のものとは限りません。これらの食品には、ヒスタミンやヒスタミン様物質が含まれている場合があります。このヒスタミンが直接血管に作用したり、または体内のヒスタミンを放出させやすい成分が含まれていることで、蕁麻疹が発症することがあります。
ヒスタミンとは
ヒスタミンとは、体内や食品中に存在する化学物質で、さまざまな生理機能に関与しています。体内では主に免疫反応やアレルギー反応に関わる重要な物質として働き、かゆみや炎症、血管の拡張といった反応を引き起こします。
ヒスタミンは耐熱性が高く、調理や加工によっても分解されたり除去されたりすることはありません。食品中に自然に存在するヒスチジンが、食品に付着したヒスタミン産生菌の働きで変化して生成されます。不適切な保存方法、特に常温での放置や冷蔵管理の不備が原因となり、菌が増殖しやすくなります。
ヒスタミンの多い食べ物
ヒスタミン食中毒の主な原因食品としては、赤身魚です。ヒスチジンを含む発酵食品も該当します。
・サバ
・カツオ
・マグロ
・サンマ
・タケノコ
・ワイン
・チーズ
・ヨーグルト
・味噌
・醤油
・納豆
非アレルギー性蕁麻疹では、同じ食品を摂取しても症状が出る日と出ない日があるという点が特徴です。これは食品の品質や調理方法、その日の体調やストレスの有無などが影響している可能性があるためです。
食べ物で蕁麻疹(じんましん)がでる他の理由
食べ物によって起こる蕁麻疹で、その他の原因を紹介します。
辛いもの
温熱蕁麻疹やコリン性蕁麻疹では辛い物や熱いものを食べた時に、体温が上昇する刺激や汗によって蕁麻疹が発生することがあります。また、辛い食べ物を摂取すると、体内では交感神経が刺激され、心拍数が増加したり血流が促進され、体の一部が赤くなったり、かゆみを強く感じたりすることがあります。
アルコール
お酒を飲むと体がかゆくなったり、蕁麻疹が出たりする症状が現れる方がいます。「アルコールアレルギー」や「アルコール過敏症」と呼びますが、実際にはアレルギー反応ではありません。アルコールそのものに対する体の反応や代謝不全が関係しています。
お酒を飲むと顔が赤くなるのは、体内でアルコールを分解する酵素「ALDH(アルデヒド脱水素酵素)」の活性が低いことが原因です。この体質は遺伝によるもので、生まれつき決まっています。そのため、加齢や訓練でこの酵素の活性を高めたり、体質を変えることはできません。
もともとお酒を飲んでも問題なかった人でも、加齢やストレス、病気などで体調が変化することで、突然不快な症状が現れることがあります。この場合も、ALDHの働きが弱まったことが関係している可能性があります。
食べた後に運動する
蕁麻疹は誰にでも起こるわけではありません。特定の過敏体質の人が、外部からの刺激を受けることで発症するものです。小麦製品やエビなどの特定の食べ物を摂取した後に運動をすると、蕁麻疹だけでなく血圧の低下や気分不良、呼吸困難などのアナフィラキシー症状が現れるケースがあるため、注意しましょう。この場合、症状を予防するためには、原因となる食物を避けるか、食後の運動を控えることが効果的です。
アナフィラキシーに注意!
息苦しさや意識障害がある場合は、ただちに専門の治療が必要です。アナフィラキシーは、アレルギー反応の中でも特に重い症状を引き起こす緊急性の高い状態になります。
アナフィラキシーが起こった場合、体全体に発疹やかゆみが広がったり、呼吸がしづらくなったりします。さらに、強い腹痛や吐き気、嘔吐、血圧の低下、意識がもうろうとするなどもアナフィラキシーの症状です。
これらの症状が出た場合は、放置すると命にかかわる可能性があります。迷わずに救急車を呼び、速やかに医療機関の助けを求めてください。
食べ物による蕁麻疹(じんましん)への対策
食べ物による蕁麻疹が気になる場合は、次に紹介する対策を試してみましょう。
食べたものを記録する
症状が出現した時間や、その直前に食べたものなどをメモしておきましょう。食物アレルギーの疑いがある場合は、どのような食材を摂取したかを記録することで、原因の特定がスムーズに進む可能性があります。
原因を避ける
原因と考えられる食べ物を避けましょう。動物性のタンパク質や油は、一部の人にとって蕁麻疹を引き起こすきっかけになることがあります。また、チョコレートや辛いもの、アルコールなどの刺激物は、体内でのヒスタミンの放出を促進し、症状を悪化させることがあるため、蕁麻疹が出ている間はこれらの摂取を控えましょう。
患部を冷やす
かゆみを感じたときは、掻かずに患部を冷やしましょう。皮膚の温度を下げることで、かゆみを伝える神経の興奮が抑えられ、症状が和らぎます。冷やす際には、保冷剤や氷をタオルに包んで患部に当てると効果的です。ただし、直接氷を肌に当てると刺激となる場合があるため、必ず布やタオルを間に挟むようにしてください。
安静にする
蕁麻疹が出ているときは、体を安静にして穏やかに過ごすことが大切です。運動や熱いお風呂など、体温が上昇する行動は症状を悪化させる可能性があります。しっかりと休息をとり、栄養バランスのとれた食事を心がけることで、ストレスを軽減し症状の緩和につながることがあります。無理をせず、リラックスした時間を過ごすようにしましょう。
病院を受診する
食物が原因の蕁麻疹は、特定の食材を摂取した直後に症状が現れる事が多いため、原因となる食品を予測しやすいかもしれません。そのため、数週間以上にわたり毎日のように蕁麻疹が繰り返される場合は、食物が原因である可能性は低いと考えられます。自己判断せず、専門医に相談して原因を特定してもらうことが重要です。
蕁麻疹(じんましん)が辛いときは我慢せず病院を受診しよう
特定の食べ物を摂取した後に皮膚に痒みが出たり、体調が悪くなった場合は早めに病院を受診することが大切です。症状が食物アレルギーによるものかどうかは、専門的な診断が必要です。
食べ物が原因で皮膚に痒みや発疹が現れると、多くの人が「食物アレルギーだ」と考えますが、必ずしもそうではありません。食物アレルギー以外にも、食品に含まれる成分や、摂取後の体調の変化が要因となる場合もあります。
正確な診断を受けることで、適切な治療や食事管理を行い、症状を防ぐための対策を行えます。
症状がつらくて通院が難しい場合にはオンライン診療がおすすめ
症状がつらくても病院への通院が難しい場合は、オンライン診療の活用を検討してみましょう。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットに接続されたデバイスを使用して、自宅にいながら医師の診察を受けられる医療サービスです。スマートフォン、タブレット、パソコンを通じて、ビデオチャットで医師と直接話せます。このサービスでは、診察の予約、問診、診断、薬の処方箋の発行、そして支払いまでオンライン上で完結します。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をアプリでスムーズに行えるサービスです。予約からお薬の受け取りまで、すべてのステップを簡単に行えます。専門スタッフによるサポート、お気に入りのクリニックや薬局の登録機能があり、お薬手帳をデジタル化することも可能です。さらに、全国どこでも当日または翌日にお薬を受け取れるため、忙しい方でも健康管理の手助けとなります。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒
まとめ
食物が原因で発生する蕁麻疹は、食物アレルギーやヒスタミンを多く含む食材が主な引き金となりますが、食後の運動やアルコール摂取も原因になり得ます。アレルギー性と非アレルギー性の2種類があり、異なるメカニズムで引き起こされます。蕁麻疹の症状が現れた場合は、摂取した食物を記録し原因を特定して避けることが大切です。また、重度の症状ではアナフィラキシーのリスクがあるため、迅速に医療機関を受診してください。日常生活で可能な予防策を取り入れ、蕁麻疹を予防しましょう。

「食べ物を食べた後に突然体がかゆくなった…」そんな経験はありませんか?これは、特定食事をした後に突然かゆみを感じたことはありませんか?それは、特定の食べ物が引き金となる蕁麻疹の可能性があります。食べ物による蕁麻疹は、アレルギーによるものと、それ以外の要因が関与するものに分けられます。小さなお子さんは食物アレルギーを起こしやすいため、注意しましょう。この記事では、食べ物による蕁麻疹の仕組みや、原因となりやすい食品、また症状が出た際の適切な対処方法について詳しく解説します。正しい知識を身につけ、蕁麻疹の予防と対策にお役立てください。
食べ物が原因で蕁麻疹(じんましん)は起こる?
食べ物による刺激によって、蕁麻疹が発生することがあります。食べ物によって起こる蕁麻疹には、アレルギー性蕁麻疹と非アレルギー性蕁麻疹が考えられます。
食べ物が原因のアレルギー性蕁麻疹(じんましん)は子供に多い
体には、病気を引き起こす細菌やウイルスを防ぐための免疫システムがありますが、アレルギーがある子どもでは、本来無害であるはずの食べ物に対しても免疫が反応してしまいます。この免疫の過剰反応により、かゆみや皮膚の赤み、蕁麻疹などの症状が出ることがあります。
アレルギーで蕁麻疹が起こる仕組み
アレルギーのある食べ物で蕁麻疹が出るのは、特定の食べ物を食べた際に体が過剰に反応してしまうことが原因です。通常、私たちの免疫システムは細菌やウイルスのような有害なものから体を守る役割を果たしています。しかし、本来無害であるはずの食べ物を「有害」と認識してしまい、それを排除しようとする反応が過剰に起こります。その結果、かゆみや蕁麻疹、腹痛、吐き気、さらには呼吸困難などの症状が現れることがあります。
IgE依存性アレルギー反応は、アレルゲンが体内に入ると免疫系が過剰に反応してしまう仕組みです。この反応は、最初にアレルゲンが体内に侵入した際に、体がその物質に対してIgE抗体を作ることで始まります。一度IgE抗体が作られると、次回以降に同じアレルゲンが体内に入った際、体内でヒスタミンなどの物質が放出され、アレルギー症状を引き起こしてしまうのです。
この反応はアレルゲンの摂取から2時間以内に症状が出るため、「即時型アレルギー」と呼ばれています。
食物アレルギー性蕁麻疹の原因になりやすい食べ物
食物アレルギー性蕁麻疹の特徴として、特定の食品を摂取すると毎回蕁麻疹が現れる傾向があります。このため、皮膚検査や血液検査を行うことで比較的簡単に原因を特定することが可能です。
・鶏卵
・牛乳
・小麦
・木の実類
・落花生
・果物類
・魚卵類
・甲殻類
・そば
・大豆
・魚
鶏卵や牛乳、小麦といった基本的な食材は、小さな子どもにアレルギーを引き起こすことが多い食品です。木の実類や落花生は、少量でも強いアレルギー反応を引き起こす場合があるため、注意しましょう。また、果物類や魚卵、エビやカニなどの甲殻類、そば、大豆、魚などもアレルギーの原因となることがあります。
食べ物による非アレルギー性の蕁麻疹(じんましん)もある
青魚や肉類、タケノコ、ほうれん草などの食べ物で蕁麻疹が出る場合、その原因はアレルギー性のものとは限りません。これらの食品には、ヒスタミンやヒスタミン様物質が含まれている場合があります。このヒスタミンが直接血管に作用したり、または体内のヒスタミンを放出させやすい成分が含まれていることで、蕁麻疹が発症することがあります。
ヒスタミンとは
ヒスタミンとは、体内や食品中に存在する化学物質で、さまざまな生理機能に関与しています。体内では主に免疫反応やアレルギー反応に関わる重要な物質として働き、かゆみや炎症、血管の拡張といった反応を引き起こします。
ヒスタミンは耐熱性が高く、調理や加工によっても分解されたり除去されたりすることはありません。食品中に自然に存在するヒスチジンが、食品に付着したヒスタミン産生菌の働きで変化して生成されます。不適切な保存方法、特に常温での放置や冷蔵管理の不備が原因となり、菌が増殖しやすくなります。
ヒスタミンの多い食べ物
ヒスタミン食中毒の主な原因食品としては、赤身魚です。ヒスチジンを含む発酵食品も該当します。
・サバ
・カツオ
・マグロ
・サンマ
・タケノコ
・ワイン
・チーズ
・ヨーグルト
・味噌
・醤油
・納豆
非アレルギー性蕁麻疹では、同じ食品を摂取しても症状が出る日と出ない日があるという点が特徴です。これは食品の品質や調理方法、その日の体調やストレスの有無などが影響している可能性があるためです。
食べ物で蕁麻疹(じんましん)がでる他の理由
食べ物によって起こる蕁麻疹で、その他の原因を紹介します。
辛いもの
温熱蕁麻疹やコリン性蕁麻疹では辛い物や熱いものを食べた時に、体温が上昇する刺激や汗によって蕁麻疹が発生することがあります。また、辛い食べ物を摂取すると、体内では交感神経が刺激され、心拍数が増加したり血流が促進され、体の一部が赤くなったり、かゆみを強く感じたりすることがあります。
アルコール
お酒を飲むと体がかゆくなったり、蕁麻疹が出たりする症状が現れる方がいます。「アルコールアレルギー」や「アルコール過敏症」と呼びますが、実際にはアレルギー反応ではありません。アルコールそのものに対する体の反応や代謝不全が関係しています。
お酒を飲むと顔が赤くなるのは、体内でアルコールを分解する酵素「ALDH(アルデヒド脱水素酵素)」の活性が低いことが原因です。この体質は遺伝によるもので、生まれつき決まっています。そのため、加齢や訓練でこの酵素の活性を高めたり、体質を変えることはできません。
もともとお酒を飲んでも問題なかった人でも、加齢やストレス、病気などで体調が変化することで、突然不快な症状が現れることがあります。この場合も、ALDHの働きが弱まったことが関係している可能性があります。
食べた後に運動する
蕁麻疹は誰にでも起こるわけではありません。特定の過敏体質の人が、外部からの刺激を受けることで発症するものです。小麦製品やエビなどの特定の食べ物を摂取した後に運動をすると、蕁麻疹だけでなく血圧の低下や気分不良、呼吸困難などのアナフィラキシー症状が現れるケースがあるため、注意しましょう。この場合、症状を予防するためには、原因となる食物を避けるか、食後の運動を控えることが効果的です。
アナフィラキシーに注意!
息苦しさや意識障害がある場合は、ただちに専門の治療が必要です。アナフィラキシーは、アレルギー反応の中でも特に重い症状を引き起こす緊急性の高い状態になります。
アナフィラキシーが起こった場合、体全体に発疹やかゆみが広がったり、呼吸がしづらくなったりします。さらに、強い腹痛や吐き気、嘔吐、血圧の低下、意識がもうろうとするなどもアナフィラキシーの症状です。
これらの症状が出た場合は、放置すると命にかかわる可能性があります。迷わずに救急車を呼び、速やかに医療機関の助けを求めてください。
食べ物による蕁麻疹(じんましん)への対策
食べ物による蕁麻疹が気になる場合は、次に紹介する対策を試してみましょう。
食べたものを記録する
症状が出現した時間や、その直前に食べたものなどをメモしておきましょう。食物アレルギーの疑いがある場合は、どのような食材を摂取したかを記録することで、原因の特定がスムーズに進む可能性があります。
原因を避ける
原因と考えられる食べ物を避けましょう。動物性のタンパク質や油は、一部の人にとって蕁麻疹を引き起こすきっかけになることがあります。また、チョコレートや辛いもの、アルコールなどの刺激物は、体内でのヒスタミンの放出を促進し、症状を悪化させることがあるため、蕁麻疹が出ている間はこれらの摂取を控えましょう。
患部を冷やす
かゆみを感じたときは、掻かずに患部を冷やしましょう。皮膚の温度を下げることで、かゆみを伝える神経の興奮が抑えられ、症状が和らぎます。冷やす際には、保冷剤や氷をタオルに包んで患部に当てると効果的です。ただし、直接氷を肌に当てると刺激となる場合があるため、必ず布やタオルを間に挟むようにしてください。
安静にする
蕁麻疹が出ているときは、体を安静にして穏やかに過ごすことが大切です。運動や熱いお風呂など、体温が上昇する行動は症状を悪化させる可能性があります。しっかりと休息をとり、栄養バランスのとれた食事を心がけることで、ストレスを軽減し症状の緩和につながることがあります。無理をせず、リラックスした時間を過ごすようにしましょう。
病院を受診する
食物が原因の蕁麻疹は、特定の食材を摂取した直後に症状が現れる事が多いため、原因となる食品を予測しやすいかもしれません。そのため、数週間以上にわたり毎日のように蕁麻疹が繰り返される場合は、食物が原因である可能性は低いと考えられます。自己判断せず、専門医に相談して原因を特定してもらうことが重要です。
蕁麻疹(じんましん)が辛いときは我慢せず病院を受診しよう
特定の食べ物を摂取した後に皮膚に痒みが出たり、体調が悪くなった場合は早めに病院を受診することが大切です。症状が食物アレルギーによるものかどうかは、専門的な診断が必要です。
食べ物が原因で皮膚に痒みや発疹が現れると、多くの人が「食物アレルギーだ」と考えますが、必ずしもそうではありません。食物アレルギー以外にも、食品に含まれる成分や、摂取後の体調の変化が要因となる場合もあります。
正確な診断を受けることで、適切な治療や食事管理を行い、症状を防ぐための対策を行えます。
症状がつらくて通院が難しい場合にはオンライン診療がおすすめ
症状がつらくても病院への通院が難しい場合は、オンライン診療の活用を検討してみましょう。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットに接続されたデバイスを使用して、自宅にいながら医師の診察を受けられる医療サービスです。スマートフォン、タブレット、パソコンを通じて、ビデオチャットで医師と直接話せます。このサービスでは、診察の予約、問診、診断、薬の処方箋の発行、そして支払いまでオンライン上で完結します。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をアプリでスムーズに行えるサービスです。予約からお薬の受け取りまで、すべてのステップを簡単に行えます。専門スタッフによるサポート、お気に入りのクリニックや薬局の登録機能があり、お薬手帳をデジタル化することも可能です。さらに、全国どこでも当日または翌日にお薬を受け取れるため、忙しい方でも健康管理の手助けとなります。
まとめ
食物が原因で発生する蕁麻疹は、食物アレルギーやヒスタミンを多く含む食材が主な引き金となりますが、食後の運動やアルコール摂取も原因になり得ます。アレルギー性と非アレルギー性の2種類があり、異なるメカニズムで引き起こされます。蕁麻疹の症状が現れた場合は、摂取した食物を記録し原因を特定して避けることが大切です。また、重度の症状ではアナフィラキシーのリスクがあるため、迅速に医療機関を受診してください。日常生活で可能な予防策を取り入れ、蕁麻疹を予防しましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。