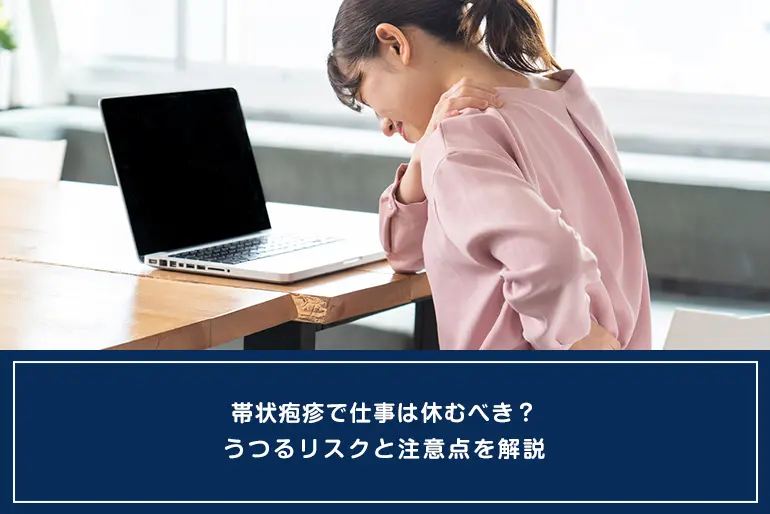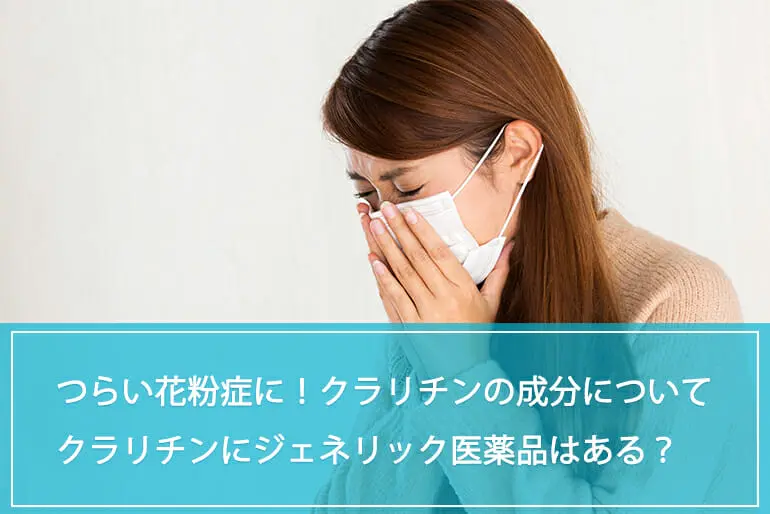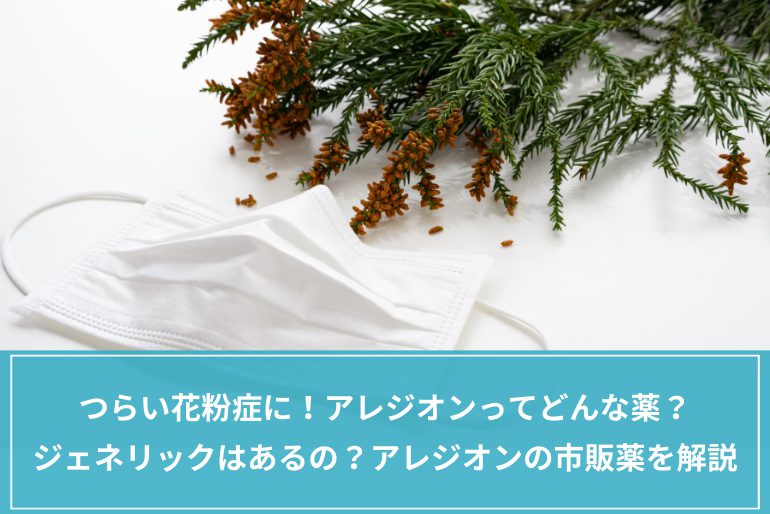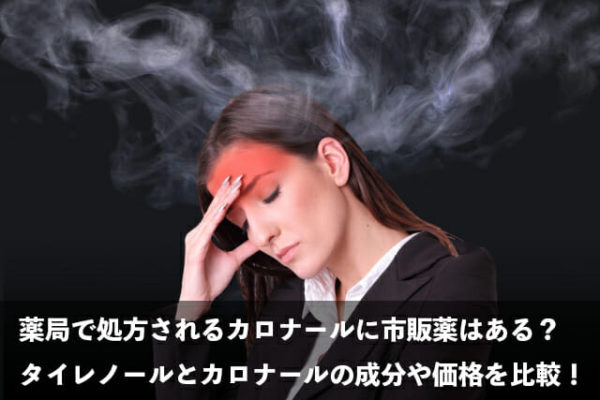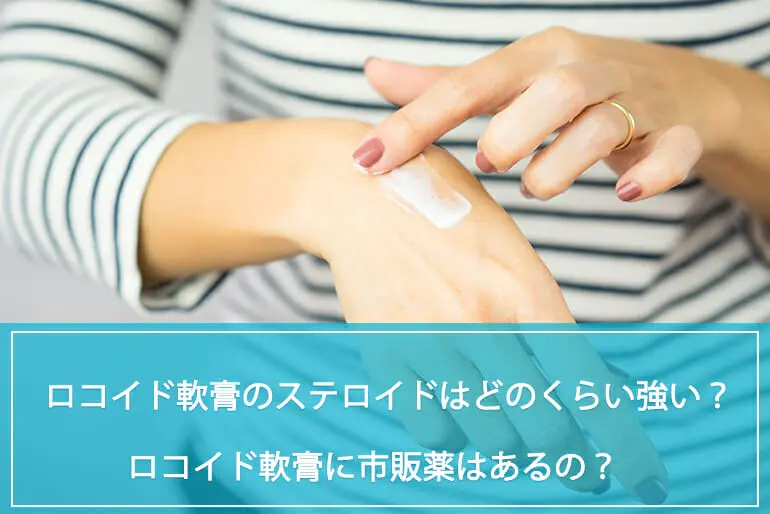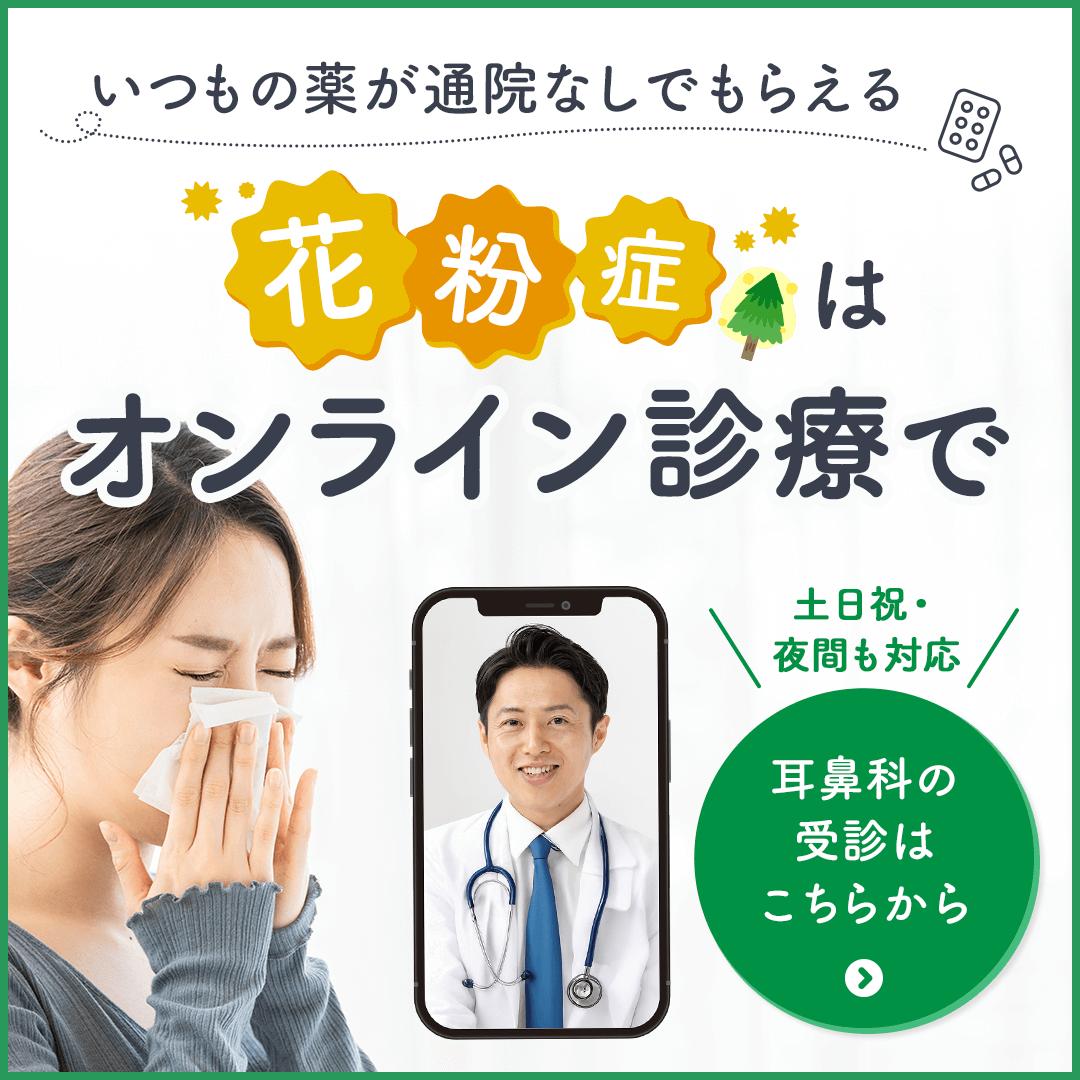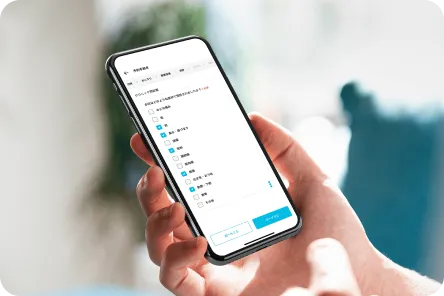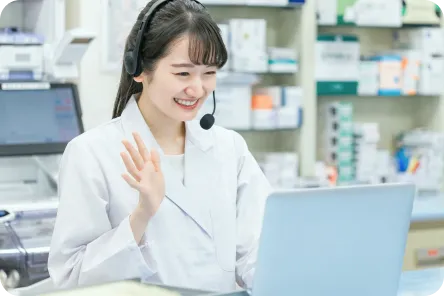手のひらにできる蕁麻疹(じんましん)の原因と対処方法について徹底解説!
蕁麻疹(じんましん)とは
蕁麻疹とは、皮膚が虫刺されのように赤く盛り上がり、かゆみを伴う病気です。多くの場合、発疹やかゆみは1日以内に消えるのが特徴ですが、繰り返し発症することもあります。1か月以上症状が続く場合は「慢性蕁麻疹」と呼ばれ、1か月以内で治まるものは「急性蕁麻疹」と区別されています。
蕁麻疹の症状
皮膚の一部が突然赤くなり、少し膨らむのが特徴です。発疹の大きさや形はさまざまで、小さな点状のものから、直径10センチ以上の広い範囲にわたるものまであります。かゆみは人によって異なり、チクチクした感覚や焼けつくような痛みを伴う場合もあります。
首や頬、お腹、太もも、臀部など、皮膚が柔らかい部分が、症状が現れやすい部位です。体のどの部位にも発症する可能性があるため、広範囲に症状が広がることもあります。一度消えたと思っても、時間が経つと別の場所に現れることがあるため注意しましょう。
蕁麻疹のできる仕組み
蕁麻疹の膨らんだ皮膚は、アレルギーを引き起こす物質(アレルゲン)や、温かさや物が当たる刺激などがきっかけで皮膚に現れます。この反応に関与しているのが「ヒスタミン」という化学伝達物質です。
皮膚の中にある細胞からヒスタミンという物質が放出され、皮膚の細い血管(毛細血管)を広げます。その結果、血液が集まりやすくなり、皮膚が赤く見えるようになります。また、血管から水分が漏れ出して皮膚の中にたまることで、皮膚がふくらみ、ぷっくりとした赤い腫れができるのです。
さらに、ヒスタミンはかゆみを感じる神経を刺激するため、蕁麻疹にはかゆみが伴います。蕁麻疹は数時間で消えたり、別の場所に現れたりするのが特徴で、同じ症状が繰り返し起こることがあります。
手にできる蕁麻疹(じんましん)の原因は
手にできる蕁麻疹の原因はさまざまで、感染症や運動、寒暖差、日光、アレルギー反応などが挙げられます。また、ストレスも蕁麻疹を引き起こす要因となることがあります。
アレルギー性蕁麻疹
特定のアレルゲンが引き金となって発症する蕁麻疹です。アレルゲンとは、体の免疫系が過剰に反応する原因となる物質のことで、たとえば花粉、ダニ、ペットの毛やフケ、特定の食品や薬などが挙げられます。アレルゲンが体内に取り込まれると免疫系がこれを「異物」と認識し、強く反応することで起こります。
物理性蕁麻疹
物理性蕁麻疹とは、皮膚に物理的な刺激が加わることで引き起こされます。皮膚が特定の物理的な要因に反応して症状が現れるのが特徴です。この蕁麻疹にはさまざまなタイプがあり、皮膚の機械的な刺激や圧迫、振動、日光、寒冷・温熱、水との接触などがきっかけで発症します。
機械性蕁麻疹
皮膚に対する摩擦や圧迫といった機械的な刺激が原因で発症します。日常生活の中でよく見られる刺激が引き金となりやすいのが特徴です。
たとえば、皮膚を掻いたり、下着や衣服のゴムで締め付けられたり、重い荷物を持って肩や手に負担がかかったりすることで、刺激を受けた部位にミミズ腫れのような赤い盛り上がりが生じます。症状は一時的なものですが、皮膚に強い刺激が加わるたびに繰り返し現れることがあります。
日光蕁麻疹
光線過敏症の一種で、日光に当たった皮膚に突然かゆみを伴う赤いミミズ腫れが現れます。この蕁麻疹は、日光に対する過敏反応として後天的に発症することが特徴です。以前は問題なく日光を浴びていた人にも突然現れることがあります。症状が進行すると、まれにアナフィラキシー反応(全身性の重篤なアレルギー反応)が現れることもあり、注意が必要です。
温熱蕁麻疹
体温よりも高い温かいものや温風に触れることで皮膚が刺激を受け、かゆみを伴う赤みや膨疹が現れます。症状が出るまでの時間が非常に短く、刺激を受けた直後から数分以内に現れるのが特徴です。多くの場合、症状は刺激を受けた部分だけに現れる「局所性温熱蕁麻疹」になります。
寒冷蕁麻疹
寒暖差や冷えなどの刺激を受けた後、数十分以内に皮膚に赤みや膨らみ(膨疹)が現れる蕁麻疹です。この膨疹や赤みは通常、数十分から数時間で自然に消えますが、場合によっては半日から1日程度続くこともあります。
寒冷蕁麻疹のほとんどが「局所性」です。局所性寒冷蕁麻疹は、冷たい水や氷に触れた部分など、特定の体の部位にのみ症状が現れます。この場合、皮膚に円形や地図状の膨疹が生じ、かゆみや赤みを伴います。
ストレスや疲労
ストレスや疲労、睡眠不足は、蕁麻疹を引き起こす可能性があります。過度なストレスは、体調を崩したり症状を悪化させたりする原因です。慢性的な蕁麻疹が続く場合、知らず知らずのうちにストレスを抱えていることが多い傾向があります。就職や転職、引っ越し、転校など、生活や仕事の環境が大きく変化するタイミングには注意しましょう。環境が大きく変わると、心身に負担がかかりやすくなります。
手に蕁麻疹(じんましん)が出来た場合の対処方法は
蕁麻疹が出た場合は、次の方法で対処してみましょう。
触らない
かゆいときに掻いてしまうのは誰にでもあることですが、軽減するわけではありません。むしろ、掻く行為が「かゆみの悪循環」を引き起こしてしまうことがほとんどです。
掻くことで皮膚が傷つくと、その刺激がさらにヒスタミンなどのかゆみを引き起こす物質の分泌を促します。その結果、かゆみがさらに強くなり、また掻いてしまうという悪循環に陥るのです。掻かないように意識するだけでも、皮膚の状態が大きく改善することがあります。
患部を冷やす
かゆみがあるときは、患部を冷やしてみましょう。皮膚の温度を下げると、かゆみを引き起こす神経の興奮が鎮まり、かゆみが軽減します。
冷やす際には、冷たい水で湿らせたタオルや、氷や保冷剤をタオルに包んだものを使用し、患部に優しく当てると効果的です。また、冷たいシャワーを患部に当てる方法もあります。ただし、冷やし過ぎは皮膚に負担をかけることがあるため、適度な冷却を心がけてください。また、寒冷蕁麻疹の場合も冷やすと逆効果になります。
安静にする
運動や熱いお風呂に入ることで体温が上昇し、症状が悪化することがあります。そのため、こうした行動は避け、涼しい場所で安静に過ごしましょう。
病院を受診する(早期診断の重要性)
蕁麻疹の症状が治まらない、繰り返し発生する、または症状が重い場合には、我慢せずに早めに病院を受診しましょう。医療機関での診断を受けることが安心につながります。
手にできる蕁麻疹(じんましん)の予防方法
蕁麻疹の予防方法について紹介します。自分に合ったものを見つけてください。
原因を避ける
特定の食べ物や薬が原因であれば、それらを避けるだけで症状が軽減する場合があります。寒さや摩擦といった物理的な刺激が引き金になる場合もあるため、これらの要因を避ける工夫も必要です。もし原因が特定できない場合、アレルギー検査を受けることで、どの物質が関係しているのかを調べられることがあります。
環境を整える
生活環境の見直しも重要です。たとえば、締め付けの少ない衣類を選んだり、暖房や加湿器で寒冷刺激を軽減したり、空気清浄機を使ってアレルギー物質を減らすなど工夫してみましょう。症状が現れるタイミングや状況を記録してみると、何が影響しているのかが見えてくるかもしれません。
スキンケアを行う
肌のバリア機能を保つことは、蕁麻疹や肌トラブルを予防するために重要です。入浴後は、皮膚の脂分が洗い流されるため、そのままにしておくと肌が乾燥しやすくなります。そのため、入浴後早めに保湿剤を塗ることが大切です。
保湿剤を塗るときは、こすらないように注意し、やさしく手のひらで肌に広げましょう。特に関節やシワがある部分は、皮膚を軽く伸ばして丁寧に塗り込むのがおすすめです。こうすることで、肌全体に保湿成分がしっかりと行き渡り、乾燥を防げます。
体調を整える
ストレスや疲労が蕁麻疹の悪化を招くこともあります。リラックスできる時間を作り、趣味や軽い運動などを通じてストレスを解消しましょう。十分な睡眠や休息を心がけることも、体調を整え、症状の改善につながる可能性があります。
手の蕁麻疹(じんましん)が気になる場合は皮膚科を受診しよう
手の蕁麻疹が悪化したり、繰り返し出たりする場合は、日常生活に支障をきたすかもしれません。早めに皮膚科を受診することが大切です。症状の原因が明確でない場合や、かゆみや赤みが強い場合も、自己判断せず専門医に相談しましょう。
忙しくて通院ができない場合にはオンライン診療がおすすめ
忙しくて病院に行く時間が取れない場合、オンライン診療の利用を検討してみると良いでしょう。時間が限られている方にとって、負担を軽減する手段の一つです。
オンライン診療とは
オンライン診療とは、インターネット接続が可能なデバイスを利用して、医師の診察を自宅などから受けられる医療サービスです。スマートフォンやタブレット、パソコンを使い、ビデオ通話を通じて医師と直接話しながら診察を受けられます。このサービスでは、診察の予約から問診、診断、薬の処方箋の発行、さらには支払いまで、すべてオンラインで完結することが特徴です。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をより簡単に利用できるサービスです。診察の予約から薬の受け取りまで、すべての手順をスムーズに行える仕組みが整っています。また、専門スタッフによるサポートや、お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能もあります。
お薬手帳をデジタル化して管理することも可能で、全国何処からでも、処方された薬を当日または翌日中に受け取れるため、利便性の高いサービスといえるでしょう。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒
まとめ
手のひらに発生する蕁麻疹は、アレルギーや物理的刺激、ストレスなどが関係しているかもしれません。原因を把握し適切に対応することで症状の軽減や予防が期待できます。症状が長引いたり悪化する場合は、自己判断を避けて早めに皮膚科を受診しましょう。専門的な治療を受けることが重要です。また、日々のスキンケアや体調管理を心がけることも、蕁麻疹の予防に役立つため行ってみてください。

蕁麻疹は、体のどの部分にも現れる可能性があります。手のひらに出た場合には、日常生活に影響を及ぼすことがあります。手のひらに蕁麻疹ができる原因はさまざまで、適切な対処と予防が欠かせません。この記事では、手のひらに現れる蕁麻疹の主な原因や特徴、効果的な対処法や予防策についてわかりやすく解説します。
蕁麻疹(じんましん)とは
蕁麻疹とは、皮膚が虫刺されのように赤く盛り上がり、かゆみを伴う病気です。多くの場合、発疹やかゆみは1日以内に消えるのが特徴ですが、繰り返し発症することもあります。1か月以上症状が続く場合は「慢性蕁麻疹」と呼ばれ、1か月以内で治まるものは「急性蕁麻疹」と区別されています。
蕁麻疹の症状
皮膚の一部が突然赤くなり、少し膨らむのが特徴です。発疹の大きさや形はさまざまで、小さな点状のものから、直径10センチ以上の広い範囲にわたるものまであります。かゆみは人によって異なり、チクチクした感覚や焼けつくような痛みを伴う場合もあります。
首や頬、お腹、太もも、臀部など、皮膚が柔らかい部分が、症状が現れやすい部位です。体のどの部位にも発症する可能性があるため、広範囲に症状が広がることもあります。一度消えたと思っても、時間が経つと別の場所に現れることがあるため注意しましょう。
蕁麻疹のできる仕組み
蕁麻疹の膨らんだ皮膚は、アレルギーを引き起こす物質(アレルゲン)や、温かさや物が当たる刺激などがきっかけで皮膚に現れます。この反応に関与しているのが「ヒスタミン」という化学伝達物質です。
皮膚の中にある細胞からヒスタミンという物質が放出され、皮膚の細い血管(毛細血管)を広げます。その結果、血液が集まりやすくなり、皮膚が赤く見えるようになります。また、血管から水分が漏れ出して皮膚の中にたまることで、皮膚がふくらみ、ぷっくりとした赤い腫れができるのです。
さらに、ヒスタミンはかゆみを感じる神経を刺激するため、蕁麻疹にはかゆみが伴います。蕁麻疹は数時間で消えたり、別の場所に現れたりするのが特徴で、同じ症状が繰り返し起こることがあります。
手にできる蕁麻疹(じんましん)の原因は
手にできる蕁麻疹の原因はさまざまで、感染症や運動、寒暖差、日光、アレルギー反応などが挙げられます。また、ストレスも蕁麻疹を引き起こす要因となることがあります。
アレルギー性蕁麻疹
特定のアレルゲンが引き金となって発症する蕁麻疹です。アレルゲンとは、体の免疫系が過剰に反応する原因となる物質のことで、たとえば花粉、ダニ、ペットの毛やフケ、特定の食品や薬などが挙げられます。アレルゲンが体内に取り込まれると免疫系がこれを「異物」と認識し、強く反応することで起こります。
物理性蕁麻疹
物理性蕁麻疹とは、皮膚に物理的な刺激が加わることで引き起こされます。皮膚が特定の物理的な要因に反応して症状が現れるのが特徴です。この蕁麻疹にはさまざまなタイプがあり、皮膚の機械的な刺激や圧迫、振動、日光、寒冷・温熱、水との接触などがきっかけで発症します。
機械性蕁麻疹
皮膚に対する摩擦や圧迫といった機械的な刺激が原因で発症します。日常生活の中でよく見られる刺激が引き金となりやすいのが特徴です。
たとえば、皮膚を掻いたり、下着や衣服のゴムで締め付けられたり、重い荷物を持って肩や手に負担がかかったりすることで、刺激を受けた部位にミミズ腫れのような赤い盛り上がりが生じます。症状は一時的なものですが、皮膚に強い刺激が加わるたびに繰り返し現れることがあります。
日光蕁麻疹
光線過敏症の一種で、日光に当たった皮膚に突然かゆみを伴う赤いミミズ腫れが現れます。この蕁麻疹は、日光に対する過敏反応として後天的に発症することが特徴です。以前は問題なく日光を浴びていた人にも突然現れることがあります。症状が進行すると、まれにアナフィラキシー反応(全身性の重篤なアレルギー反応)が現れることもあり、注意が必要です。
温熱蕁麻疹
体温よりも高い温かいものや温風に触れることで皮膚が刺激を受け、かゆみを伴う赤みや膨疹が現れます。症状が出るまでの時間が非常に短く、刺激を受けた直後から数分以内に現れるのが特徴です。多くの場合、症状は刺激を受けた部分だけに現れる「局所性温熱蕁麻疹」になります。
寒冷蕁麻疹
寒暖差や冷えなどの刺激を受けた後、数十分以内に皮膚に赤みや膨らみ(膨疹)が現れる蕁麻疹です。この膨疹や赤みは通常、数十分から数時間で自然に消えますが、場合によっては半日から1日程度続くこともあります。
寒冷蕁麻疹のほとんどが「局所性」です。局所性寒冷蕁麻疹は、冷たい水や氷に触れた部分など、特定の体の部位にのみ症状が現れます。この場合、皮膚に円形や地図状の膨疹が生じ、かゆみや赤みを伴います。
ストレスや疲労
ストレスや疲労、睡眠不足は、蕁麻疹を引き起こす可能性があります。過度なストレスは、体調を崩したり症状を悪化させたりする原因です。慢性的な蕁麻疹が続く場合、知らず知らずのうちにストレスを抱えていることが多い傾向があります。就職や転職、引っ越し、転校など、生活や仕事の環境が大きく変化するタイミングには注意しましょう。環境が大きく変わると、心身に負担がかかりやすくなります。
手に蕁麻疹(じんましん)が出来た場合の対処方法は
蕁麻疹が出た場合は、次の方法で対処してみましょう。
触らない
かゆいときに掻いてしまうのは誰にでもあることですが、軽減するわけではありません。むしろ、掻く行為が「かゆみの悪循環」を引き起こしてしまうことがほとんどです。
掻くことで皮膚が傷つくと、その刺激がさらにヒスタミンなどのかゆみを引き起こす物質の分泌を促します。その結果、かゆみがさらに強くなり、また掻いてしまうという悪循環に陥るのです。掻かないように意識するだけでも、皮膚の状態が大きく改善することがあります。
患部を冷やす
かゆみがあるときは、患部を冷やしてみましょう。皮膚の温度を下げると、かゆみを引き起こす神経の興奮が鎮まり、かゆみが軽減します。
冷やす際には、冷たい水で湿らせたタオルや、氷や保冷剤をタオルに包んだものを使用し、患部に優しく当てると効果的です。また、冷たいシャワーを患部に当てる方法もあります。ただし、冷やし過ぎは皮膚に負担をかけることがあるため、適度な冷却を心がけてください。また、寒冷蕁麻疹の場合も冷やすと逆効果になります。
安静にする
運動や熱いお風呂に入ることで体温が上昇し、症状が悪化することがあります。そのため、こうした行動は避け、涼しい場所で安静に過ごしましょう。
病院を受診する(早期診断の重要性)
蕁麻疹の症状が治まらない、繰り返し発生する、または症状が重い場合には、我慢せずに早めに病院を受診しましょう。医療機関での診断を受けることが安心につながります。
手にできる蕁麻疹(じんましん)の予防方法
蕁麻疹の予防方法について紹介します。自分に合ったものを見つけてください。
原因を避ける
特定の食べ物や薬が原因であれば、それらを避けるだけで症状が軽減する場合があります。寒さや摩擦といった物理的な刺激が引き金になる場合もあるため、これらの要因を避ける工夫も必要です。もし原因が特定できない場合、アレルギー検査を受けることで、どの物質が関係しているのかを調べられることがあります。
環境を整える
生活環境の見直しも重要です。たとえば、締め付けの少ない衣類を選んだり、暖房や加湿器で寒冷刺激を軽減したり、空気清浄機を使ってアレルギー物質を減らすなど工夫してみましょう。症状が現れるタイミングや状況を記録してみると、何が影響しているのかが見えてくるかもしれません。
スキンケアを行う
肌のバリア機能を保つことは、蕁麻疹や肌トラブルを予防するために重要です。入浴後は、皮膚の脂分が洗い流されるため、そのままにしておくと肌が乾燥しやすくなります。そのため、入浴後早めに保湿剤を塗ることが大切です。
保湿剤を塗るときは、こすらないように注意し、やさしく手のひらで肌に広げましょう。特に関節やシワがある部分は、皮膚を軽く伸ばして丁寧に塗り込むのがおすすめです。こうすることで、肌全体に保湿成分がしっかりと行き渡り、乾燥を防げます。
体調を整える
ストレスや疲労が蕁麻疹の悪化を招くこともあります。リラックスできる時間を作り、趣味や軽い運動などを通じてストレスを解消しましょう。十分な睡眠や休息を心がけることも、体調を整え、症状の改善につながる可能性があります。
手の蕁麻疹(じんましん)が気になる場合は皮膚科を受診しよう
手の蕁麻疹が悪化したり、繰り返し出たりする場合は、日常生活に支障をきたすかもしれません。早めに皮膚科を受診することが大切です。症状の原因が明確でない場合や、かゆみや赤みが強い場合も、自己判断せず専門医に相談しましょう。
忙しくて通院ができない場合にはオンライン診療がおすすめ
忙しくて病院に行く時間が取れない場合、オンライン診療の利用を検討してみると良いでしょう。時間が限られている方にとって、負担を軽減する手段の一つです。
オンライン診療とは
オンライン診療とは、インターネット接続が可能なデバイスを利用して、医師の診察を自宅などから受けられる医療サービスです。スマートフォンやタブレット、パソコンを使い、ビデオ通話を通じて医師と直接話しながら診察を受けられます。このサービスでは、診察の予約から問診、診断、薬の処方箋の発行、さらには支払いまで、すべてオンラインで完結することが特徴です。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をより簡単に利用できるサービスです。診察の予約から薬の受け取りまで、すべての手順をスムーズに行える仕組みが整っています。また、専門スタッフによるサポートや、お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能もあります。
お薬手帳をデジタル化して管理することも可能で、全国何処からでも、処方された薬を当日または翌日中に受け取れるため、利便性の高いサービスといえるでしょう。
まとめ
手のひらに発生する蕁麻疹は、アレルギーや物理的刺激、ストレスなどが関係しているかもしれません。原因を把握し適切に対応することで症状の軽減や予防が期待できます。症状が長引いたり悪化する場合は、自己判断を避けて早めに皮膚科を受診しましょう。専門的な治療を受けることが重要です。また、日々のスキンケアや体調管理を心がけることも、蕁麻疹の予防に役立つため行ってみてください。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。