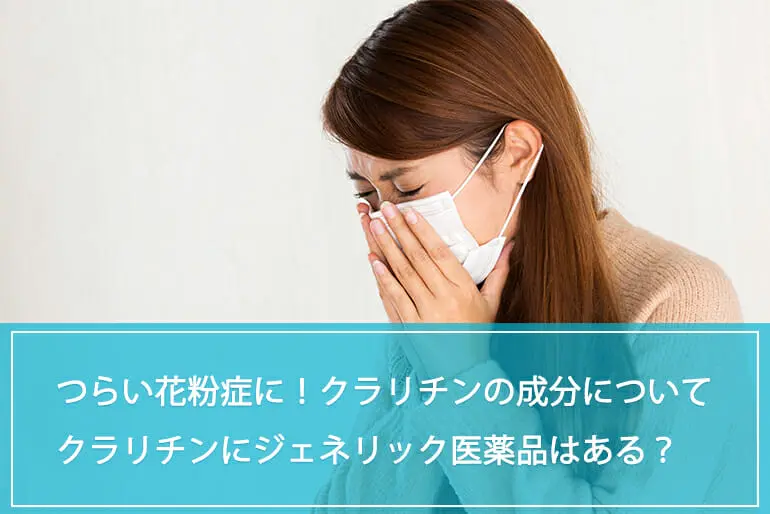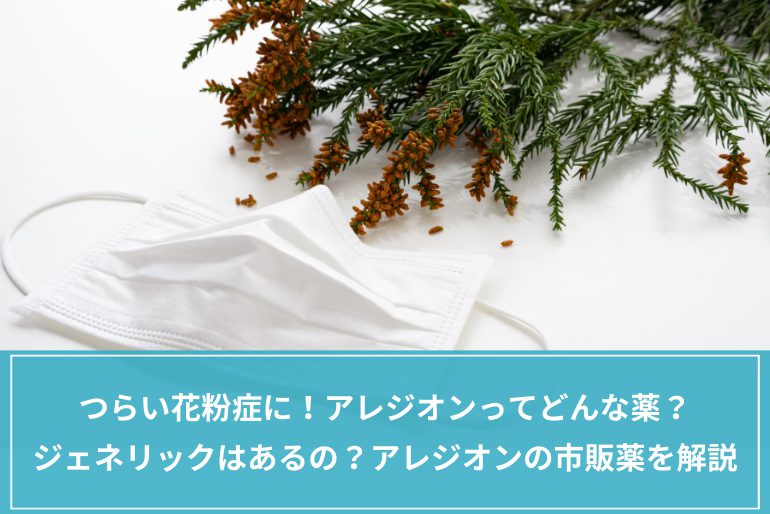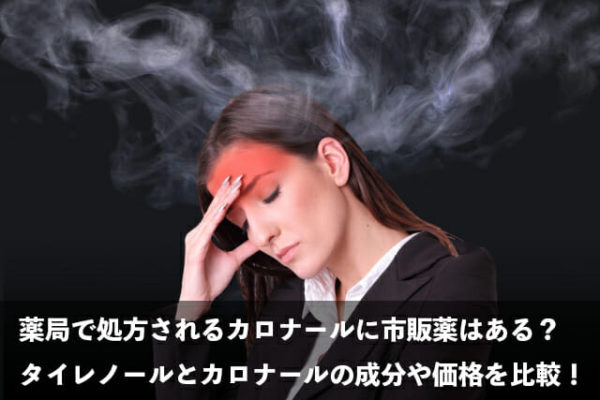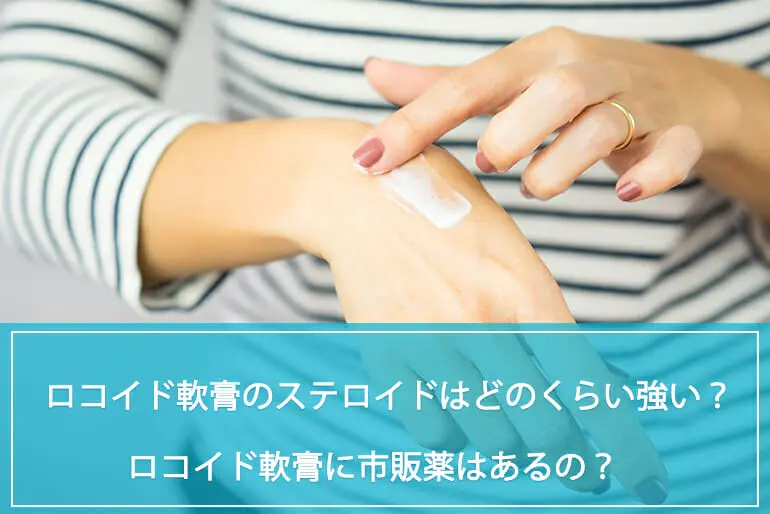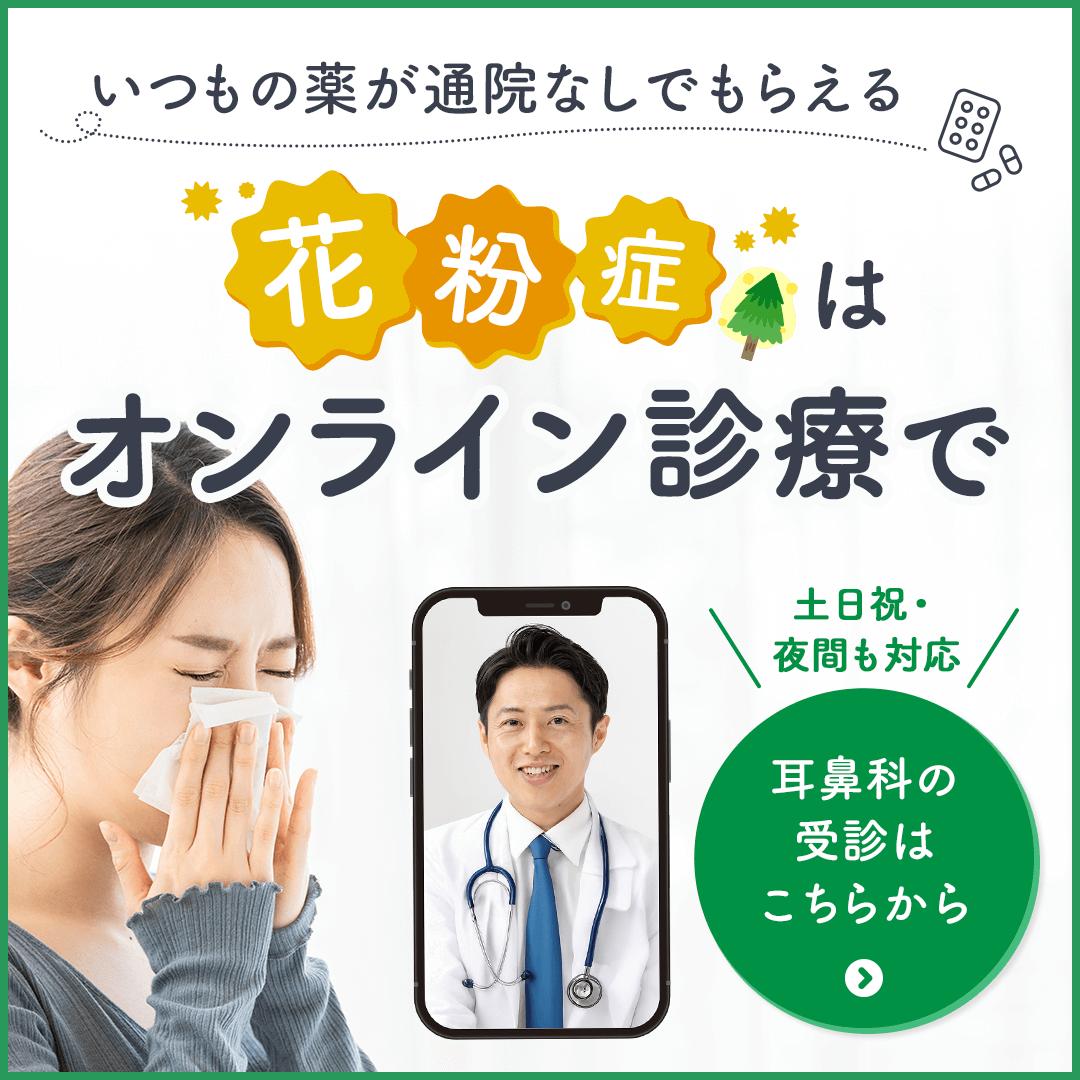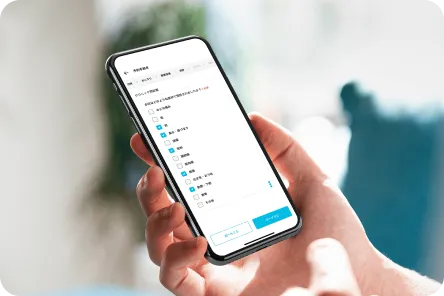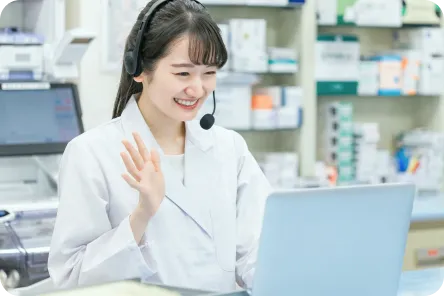蕁麻疹(じんましん)で病院を受診するタイミングは?何科を受診すればいい?
蕁麻疹(じんましん)とは
蕁麻疹とは、皮膚が突然、蚊に刺されたように盛り上がり、赤みや強いかゆみを伴う病気です。症状は通常、数十分から1日以内に自然に治まります。原因は多くのケースで、わかりません。しかし、抗ヒスタミン薬の内服などで症状を抑えられます。
蕁麻疹の症状
蚊に刺されたような赤い膨らみが皮膚に現れ、これを膨疹(ぼうしん)と呼びます。膨疹のサイズはさまざまで、時にはお互いに繋がって地図のように広がることがあります。一つひとつの膨疹は通常、24時間以内に消えて跡を残しません。かゆみを伴ったり、チクチクしたり焼けるような感じがすることもあります。
顔を含む体のどの部分にも現れることがあります。慢性蕁麻疹の場合、夕方から夜にかけて症状が出たり悪化したりすることが多いのが特徴です。
蕁麻疹の原因
特定の刺激(食物などのアレルギー反応、圧迫などの物理的刺激、発汗など)が原因・誘因となる蕁麻疹と、直接的な原因がわからない蕁麻疹があります。
1度だけ症状が出たり数日内で治まる「急性蕁麻疹」と、原因が特定できず、1か月半以上、皮疹が出たり消えたりが続く「慢性蕁麻疹」と呼ばれるタイプがあり、慢性蕁麻疹は数か月~数年にわたって続くこともあります。
蕁麻疹を起こしやすくしたり悪化させたりする因子として、ストレスや疲労、体調不良、かぜなどの感染症、月経などです。蕁麻疹は、人から人へうつることはありません。
甲状腺疾患や膠原病などの病気が原因で現れる蕁麻疹もあります。この場合、医療機関を受診しましょう。
蕁麻疹(じんましん)で病院を受診する目安
不安や心配があるときは、自己判断せずに医療機関で診察を受けてください。判断が難しい場合は、次のいずれかに当てはまる場合が病院を受診する目安です。
通常、蕁麻疹の発疹は数時間以内に消えることが多いですが、半日以上続く場合や何日も繰り返す場合は注意してください。また、症状が重くなって色素沈着が残った場合や、特定の物質や刺激が原因で蕁麻疹が出ていると考えられる場合も、早めに診てもらうことがおすすめです。
蕁麻疹があるとき受診する診療科
蕁麻疹が出た場合に受診するべき診療科は、症状や原因によって異なります。
皮膚科
皮膚科は蕁麻疹の診断と治療を受ける場合の第一選択です。皮膚症状が主で、特に他の症状がない場合は皮膚科を受診してください。
内科
発熱や喉の痛みなど、蕁麻疹以外の全身症状がある場合は内科の受診を検討しましょう。
小児科
子どもの場合、かかりつけの小児科で診てもらうのが安心です。既往歴や全身の状態を把握している医師に相談しましょう。
心療内科
ストレスが原因で発症する蕁麻疹を「心因性蕁麻疹」と呼びます。多くの蕁麻疹は数時間で消えますが、心因性蕁麻疹の場合は、原因となるストレスを取り除くのが難しく、症状が慢性化しやすい特徴があります。放置せず、医療機関で治療を受けるようにしましょう。治療法としては、抗ヒスタミン薬やステロイド外用薬による皮膚治療と、心療内科や精神科での心理面からの治療が効果的です。
救急外来
血圧低下や息苦しさを伴う場合、アナフィラキシーの可能性が考えられます。この場合はすぐに医療機関に連絡し、緊急対応が必要です。自己判断せずに適切な医療措置を受けるようにしましょう。
蕁麻疹(じんましん)で病院に行ったら何される?
蕁麻疹で病院を受診した場合、医師は蕁麻疹が出た時期、どのような状況で発症したか、かゆみの程度、過去のアレルギー歴などを確認します。そして、皮膚の状態を直接観察します。
検査
蕁麻疹の原因が特定できないことが多いため、通常は検査をあまり行いません。しかし、内臓疾患などが疑われる場合には、血液検査で肝臓や腎臓の機能、白血球の数などを調べます。また、問診などで原因が判明する可能性がある場合は、皮膚にパッチテストを行うほか、血液検査で原因となる物質を特定することもあります。
①血液検査
肝機能が悪いと蕁麻疹が治りにくい場合があるため、肝臓の状態をチェックします。また、体内に慢性的な炎症があるとCRPという項目や白血球の数が上昇するため、これも検査の一部として役立ちます。アレルギー性の蕁麻疹の場合、IgE値を調べることがあります。
②皮膚テスト
皮内テスト、プリックテスト、スクラッチテストなど。アレルゲン(アレルギーの原因物質)エキスを皮膚に注射したり垂らしたりして、反応を見る方法です。
③誘発テスト
温熱や寒冷、圧迫などの物理的刺激を皮膚に与えて蕁麻疹が出るかどうかを調べます。
④負荷テスト
原因が疑わしいものの皮膚テストで結論が出ない場合に行います。たとえば、薬剤性の蕁麻疹の原因を調べるために、実際にその薬剤を摂取して反応を見ます。
診断
蕁麻疹の診断は、蕁麻疹の発疹は表面が赤くなる程度で、ザラザラしたりジクジクしたりはしません。また、発疹は1時間から長くても1日程度で消えるため他の発疹と明確に区別できます。しかし、治療においては蕁麻疹の「病型」が重要です。この病型は、蕁麻疹がどのような原因で引き起こされるかによって決まります。
蕁麻疹には原因がはっきりしているものと、原因がわからないものの二つのタイプがあります。全体の約7割は原因が不明です。
治療
外用薬は、痒みを軽減する程度の効果しかないため、通常は使用しません。原因が不明な場合も多く、その場合は症状を緩和するために内服薬を使用します。
原因を避ける
原因や悪化要因が明確であれば、それらを取り除くことが重要です。具体的には、アレルギー原因物質やストレスなどを避けることが治療の第一歩となります。
内服薬
蕁麻疹の多くはヒスタミンという物質が原因で発症します。このヒスタミンの作用を抑える抗ヒスタミン薬を使用することで、症状を抑えられます。
これらの薬は主に内服薬として使用されますが、症状が強い場合は注射を行うこともあります。症状が治まっても内服をすぐに中断すると再発する恐れがあるため、自己判断で薬をやめないことが重要です。
蕁麻疹が出た時に家で出来る対策
突然蕁麻疹が出た場合、慌ててしまうかもしれませんが、冷静に対処しましょう。普段の生活で少し気を付けるだけでも、症状を軽減できることがあるため試してみてください。
患部を冷やす
体温が上がるとかゆみが増すことがあるため注意してください。かゆみは患部を冷やすと和らぐことがあります。冷却にはタオルで包んだ保冷剤などを使ってください。ただし、寒冷刺激による蕁麻疹の場合は、冷やすと悪化することがあるため避けましょう。
患部に負担をかけない
肌への摩擦や締め付けが蕁麻疹を悪化させることがあります。ゆったりとした服装を選び、肌に余計なストレスを与えないよう心がけましょう。また、蕁麻疹が出ている部分を掻くと症状が悪化するため、避けてください。
睡眠をしっかりとる
蕁麻疹には、生活習慣も影響します。睡眠不足やストレスは症状を悪化させる要因です。十分な睡眠をとることを心がけ、規則正しく正しい生活リズムを心掛けてください。かゆみで眠れない場合は症状が悪化することがあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
記録をとる
どんな時に蕁麻疹が出るのか記録しておくことで、きっかけを見つけやすくなります。蕁麻疹の約7割が原因不明とされていますが、生活パターンを記録しておくと思わぬ発見があるかもしれません。
また、通常24時間以内に消えてしまうので、症状が出ている時にスマートフォンなどで写真を撮っておくと、診察が行いやすくなります。
蕁麻疹(じんましん)が辛いときは、我慢せず病院を受診しよう
通常、蕁麻疹の皮膚症状は数十分から数時間で消えるものですが、症状が繰り返しあらわれることがあります。症状が悪化した場合や、繰り返す場合は皮膚科を受診しましょう。
また、皮膚症状が継続する場合や、色素沈着が残る場合は、別の病気の可能性があります。自己判断せず、専門医の診断を受けてください。
忙しくて通院できない場合はオンライン診療がおすすめ
忙しくて病院を受診する時間がない場合でも放置せず、オンライン診療を活用してみましょう。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットを利用して自宅や職場から医師の診察を受けられるサービスです。スマートフォンやパソコンを使って、画面越しに医師と直接対話することで、病院に行かなくても診察を受けられます。診察の予約から始まり、問診、診断、薬の処方箋発行や支払いまで、すべてオンライン上で完了する仕組みです。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療を簡単かつ快適に利用できるサービスです。アプリを使うことで、診察の予約から薬の受け取りまでの流れをスムーズに進められます。
特徴的なのは、専門のスタッフが利用者をサポートしてくれる点や、お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能がある点です。また、紙のお薬手帳の情報をデジタル化し、アプリ内で管理することもできます。さらに、全国どこからでも当日または翌日に薬を受け取れるため、忙しい方にとって心強いサービスといえます。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒
まとめ
蕁麻疹は、軽い症状で済む場合もあれば、日常生活に支障をきたすほど辛いケースもあります。症状が繰り返し現れた場合や、かゆみが強い場合は、我慢せず早めに医療機関を受診することが大切です。受診の際には、症状の経過や生活環境についての記録を用意しておくと、診断がスムーズに進みます。自己判断に頼らず、専門家のアドバイスを受けながら適切な治療を行うことで、安心して日々を過ごせるようにしましょう。

蕁麻疹はかゆみや腫れが突然皮膚に現れます。一時的なものだと思って、放置すると重症化する危険性もあります。しかし、どんな症状が出た場合に、どこの科に受診したらいいのでしょうか?この記事では、蕁麻疹が発生した際にどのタイミングで病院を受診すべきか、どの診療科を選ぶべきか解説します。また、診察内容や自宅での対処方法についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
蕁麻疹(じんましん)とは
蕁麻疹とは、皮膚が突然、蚊に刺されたように盛り上がり、赤みや強いかゆみを伴う病気です。症状は通常、数十分から1日以内に自然に治まります。原因は多くのケースで、わかりません。しかし、抗ヒスタミン薬の内服などで症状を抑えられます。
蕁麻疹の症状
蚊に刺されたような赤い膨らみが皮膚に現れ、これを膨疹(ぼうしん)と呼びます。膨疹のサイズはさまざまで、時にはお互いに繋がって地図のように広がることがあります。一つひとつの膨疹は通常、24時間以内に消えて跡を残しません。かゆみを伴ったり、チクチクしたり焼けるような感じがすることもあります。
顔を含む体のどの部分にも現れることがあります。慢性蕁麻疹の場合、夕方から夜にかけて症状が出たり悪化したりすることが多いのが特徴です。
蕁麻疹の原因
特定の刺激(食物などのアレルギー反応、圧迫などの物理的刺激、発汗など)が原因・誘因となる蕁麻疹と、直接的な原因がわからない蕁麻疹があります。
1度だけ症状が出たり数日内で治まる「急性蕁麻疹」と、原因が特定できず、1か月半以上、皮疹が出たり消えたりが続く「慢性蕁麻疹」と呼ばれるタイプがあり、慢性蕁麻疹は数か月~数年にわたって続くこともあります。
蕁麻疹を起こしやすくしたり悪化させたりする因子として、ストレスや疲労、体調不良、かぜなどの感染症、月経などです。蕁麻疹は、人から人へうつることはありません。
甲状腺疾患や膠原病などの病気が原因で現れる蕁麻疹もあります。この場合、医療機関を受診しましょう。
蕁麻疹(じんましん)で病院を受診する目安
不安や心配があるときは、自己判断せずに医療機関で診察を受けてください。判断が難しい場合は、次のいずれかに当てはまる場合が病院を受診する目安です。
- 蕁麻疹が繰り返し出る
- 症状が重い
- 半日経っても症状が消えない
- 数日間続く
- 発熱を伴った蕁麻疹
通常、蕁麻疹の発疹は数時間以内に消えることが多いですが、半日以上続く場合や何日も繰り返す場合は注意してください。また、症状が重くなって色素沈着が残った場合や、特定の物質や刺激が原因で蕁麻疹が出ていると考えられる場合も、早めに診てもらうことがおすすめです。
蕁麻疹があるとき受診する診療科
蕁麻疹が出た場合に受診するべき診療科は、症状や原因によって異なります。
皮膚科
皮膚科は蕁麻疹の診断と治療を受ける場合の第一選択です。皮膚症状が主で、特に他の症状がない場合は皮膚科を受診してください。
内科
発熱や喉の痛みなど、蕁麻疹以外の全身症状がある場合は内科の受診を検討しましょう。
小児科
子どもの場合、かかりつけの小児科で診てもらうのが安心です。既往歴や全身の状態を把握している医師に相談しましょう。
心療内科
ストレスが原因で発症する蕁麻疹を「心因性蕁麻疹」と呼びます。多くの蕁麻疹は数時間で消えますが、心因性蕁麻疹の場合は、原因となるストレスを取り除くのが難しく、症状が慢性化しやすい特徴があります。放置せず、医療機関で治療を受けるようにしましょう。治療法としては、抗ヒスタミン薬やステロイド外用薬による皮膚治療と、心療内科や精神科での心理面からの治療が効果的です。
救急外来
血圧低下や息苦しさを伴う場合、アナフィラキシーの可能性が考えられます。この場合はすぐに医療機関に連絡し、緊急対応が必要です。自己判断せずに適切な医療措置を受けるようにしましょう。
蕁麻疹(じんましん)で病院に行ったら何される?
蕁麻疹で病院を受診した場合、医師は蕁麻疹が出た時期、どのような状況で発症したか、かゆみの程度、過去のアレルギー歴などを確認します。そして、皮膚の状態を直接観察します。
検査
蕁麻疹の原因が特定できないことが多いため、通常は検査をあまり行いません。しかし、内臓疾患などが疑われる場合には、血液検査で肝臓や腎臓の機能、白血球の数などを調べます。また、問診などで原因が判明する可能性がある場合は、皮膚にパッチテストを行うほか、血液検査で原因となる物質を特定することもあります。
①血液検査
肝機能が悪いと蕁麻疹が治りにくい場合があるため、肝臓の状態をチェックします。また、体内に慢性的な炎症があるとCRPという項目や白血球の数が上昇するため、これも検査の一部として役立ちます。アレルギー性の蕁麻疹の場合、IgE値を調べることがあります。
②皮膚テスト
皮内テスト、プリックテスト、スクラッチテストなど。アレルゲン(アレルギーの原因物質)エキスを皮膚に注射したり垂らしたりして、反応を見る方法です。
③誘発テスト
温熱や寒冷、圧迫などの物理的刺激を皮膚に与えて蕁麻疹が出るかどうかを調べます。
④負荷テスト
原因が疑わしいものの皮膚テストで結論が出ない場合に行います。たとえば、薬剤性の蕁麻疹の原因を調べるために、実際にその薬剤を摂取して反応を見ます。
診断
蕁麻疹の診断は、蕁麻疹の発疹は表面が赤くなる程度で、ザラザラしたりジクジクしたりはしません。また、発疹は1時間から長くても1日程度で消えるため他の発疹と明確に区別できます。しかし、治療においては蕁麻疹の「病型」が重要です。この病型は、蕁麻疹がどのような原因で引き起こされるかによって決まります。
蕁麻疹には原因がはっきりしているものと、原因がわからないものの二つのタイプがあります。全体の約7割は原因が不明です。
治療
外用薬は、痒みを軽減する程度の効果しかないため、通常は使用しません。原因が不明な場合も多く、その場合は症状を緩和するために内服薬を使用します。
原因を避ける
原因や悪化要因が明確であれば、それらを取り除くことが重要です。具体的には、アレルギー原因物質やストレスなどを避けることが治療の第一歩となります。
内服薬
蕁麻疹の多くはヒスタミンという物質が原因で発症します。このヒスタミンの作用を抑える抗ヒスタミン薬を使用することで、症状を抑えられます。
これらの薬は主に内服薬として使用されますが、症状が強い場合は注射を行うこともあります。症状が治まっても内服をすぐに中断すると再発する恐れがあるため、自己判断で薬をやめないことが重要です。
蕁麻疹が出た時に家で出来る対策
突然蕁麻疹が出た場合、慌ててしまうかもしれませんが、冷静に対処しましょう。普段の生活で少し気を付けるだけでも、症状を軽減できることがあるため試してみてください。
患部を冷やす
体温が上がるとかゆみが増すことがあるため注意してください。かゆみは患部を冷やすと和らぐことがあります。冷却にはタオルで包んだ保冷剤などを使ってください。ただし、寒冷刺激による蕁麻疹の場合は、冷やすと悪化することがあるため避けましょう。
患部に負担をかけない
肌への摩擦や締め付けが蕁麻疹を悪化させることがあります。ゆったりとした服装を選び、肌に余計なストレスを与えないよう心がけましょう。また、蕁麻疹が出ている部分を掻くと症状が悪化するため、避けてください。
睡眠をしっかりとる
蕁麻疹には、生活習慣も影響します。睡眠不足やストレスは症状を悪化させる要因です。十分な睡眠をとることを心がけ、規則正しく正しい生活リズムを心掛けてください。かゆみで眠れない場合は症状が悪化することがあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
記録をとる
どんな時に蕁麻疹が出るのか記録しておくことで、きっかけを見つけやすくなります。蕁麻疹の約7割が原因不明とされていますが、生活パターンを記録しておくと思わぬ発見があるかもしれません。
また、通常24時間以内に消えてしまうので、症状が出ている時にスマートフォンなどで写真を撮っておくと、診察が行いやすくなります。
蕁麻疹(じんましん)が辛いときは、我慢せず病院を受診しよう
通常、蕁麻疹の皮膚症状は数十分から数時間で消えるものですが、症状が繰り返しあらわれることがあります。症状が悪化した場合や、繰り返す場合は皮膚科を受診しましょう。
また、皮膚症状が継続する場合や、色素沈着が残る場合は、別の病気の可能性があります。自己判断せず、専門医の診断を受けてください。
忙しくて通院できない場合はオンライン診療がおすすめ
忙しくて病院を受診する時間がない場合でも放置せず、オンライン診療を活用してみましょう。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットを利用して自宅や職場から医師の診察を受けられるサービスです。スマートフォンやパソコンを使って、画面越しに医師と直接対話することで、病院に行かなくても診察を受けられます。診察の予約から始まり、問診、診断、薬の処方箋発行や支払いまで、すべてオンライン上で完了する仕組みです。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療を簡単かつ快適に利用できるサービスです。アプリを使うことで、診察の予約から薬の受け取りまでの流れをスムーズに進められます。
特徴的なのは、専門のスタッフが利用者をサポートしてくれる点や、お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能がある点です。また、紙のお薬手帳の情報をデジタル化し、アプリ内で管理することもできます。さらに、全国どこからでも当日または翌日に薬を受け取れるため、忙しい方にとって心強いサービスといえます。
まとめ
蕁麻疹は、軽い症状で済む場合もあれば、日常生活に支障をきたすほど辛いケースもあります。症状が繰り返し現れた場合や、かゆみが強い場合は、我慢せず早めに医療機関を受診することが大切です。受診の際には、症状の経過や生活環境についての記録を用意しておくと、診断がスムーズに進みます。自己判断に頼らず、専門家のアドバイスを受けながら適切な治療を行うことで、安心して日々を過ごせるようにしましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。