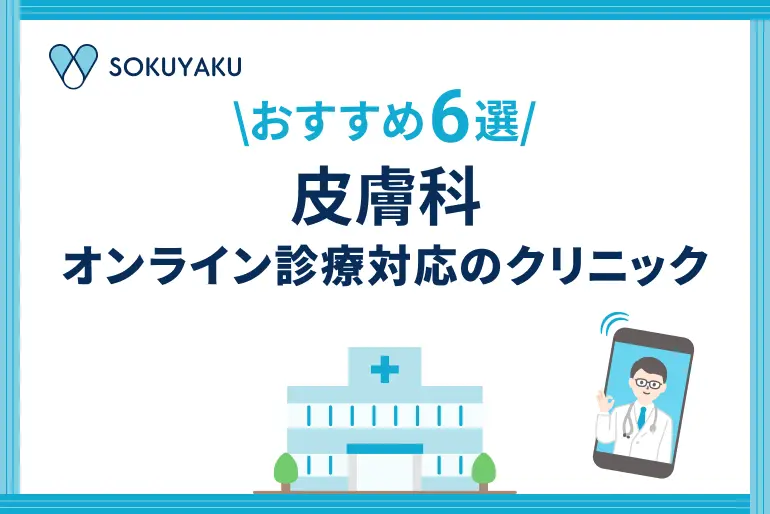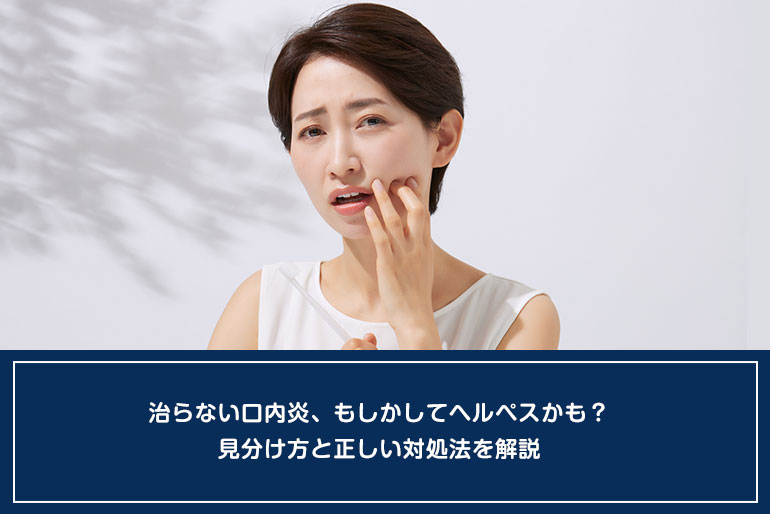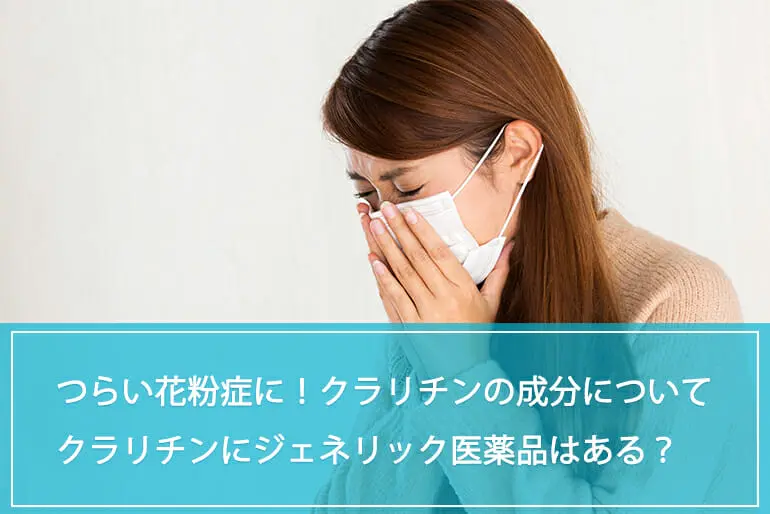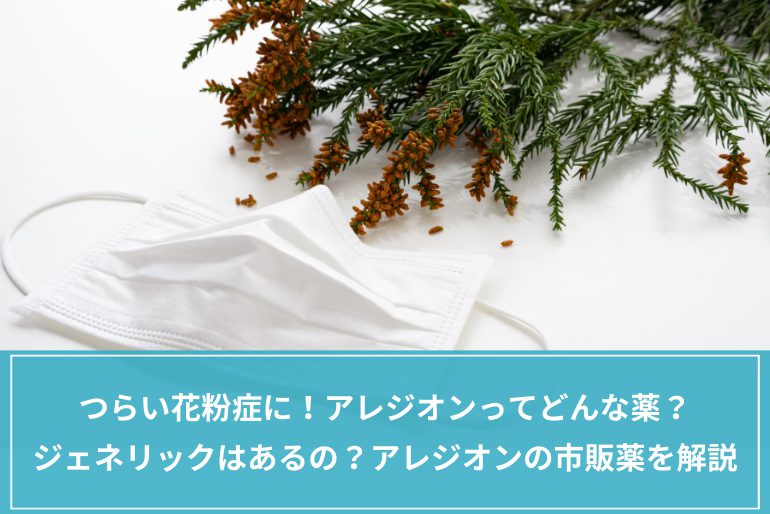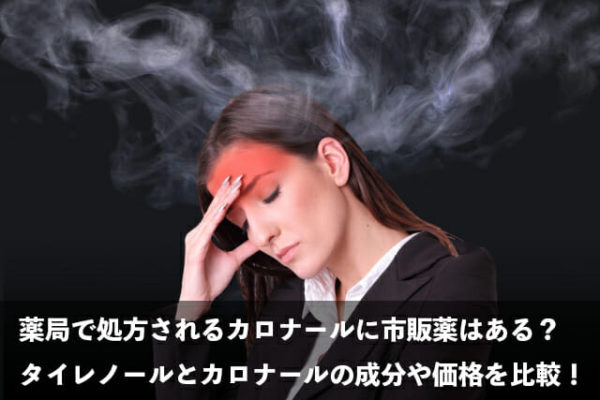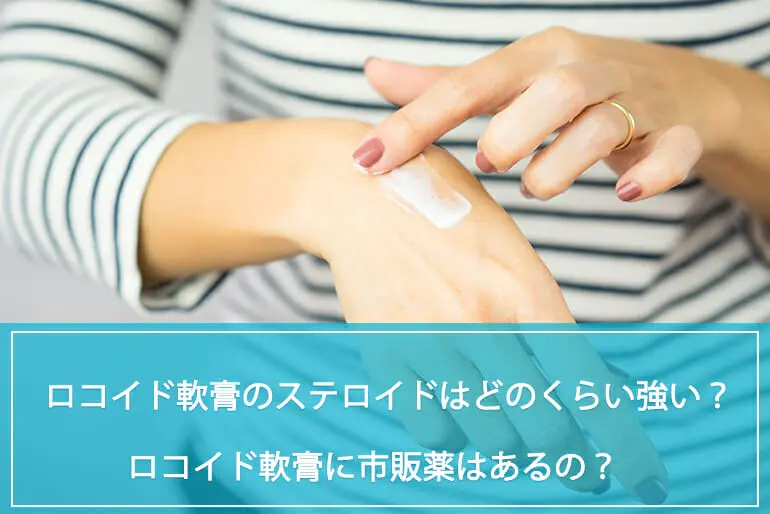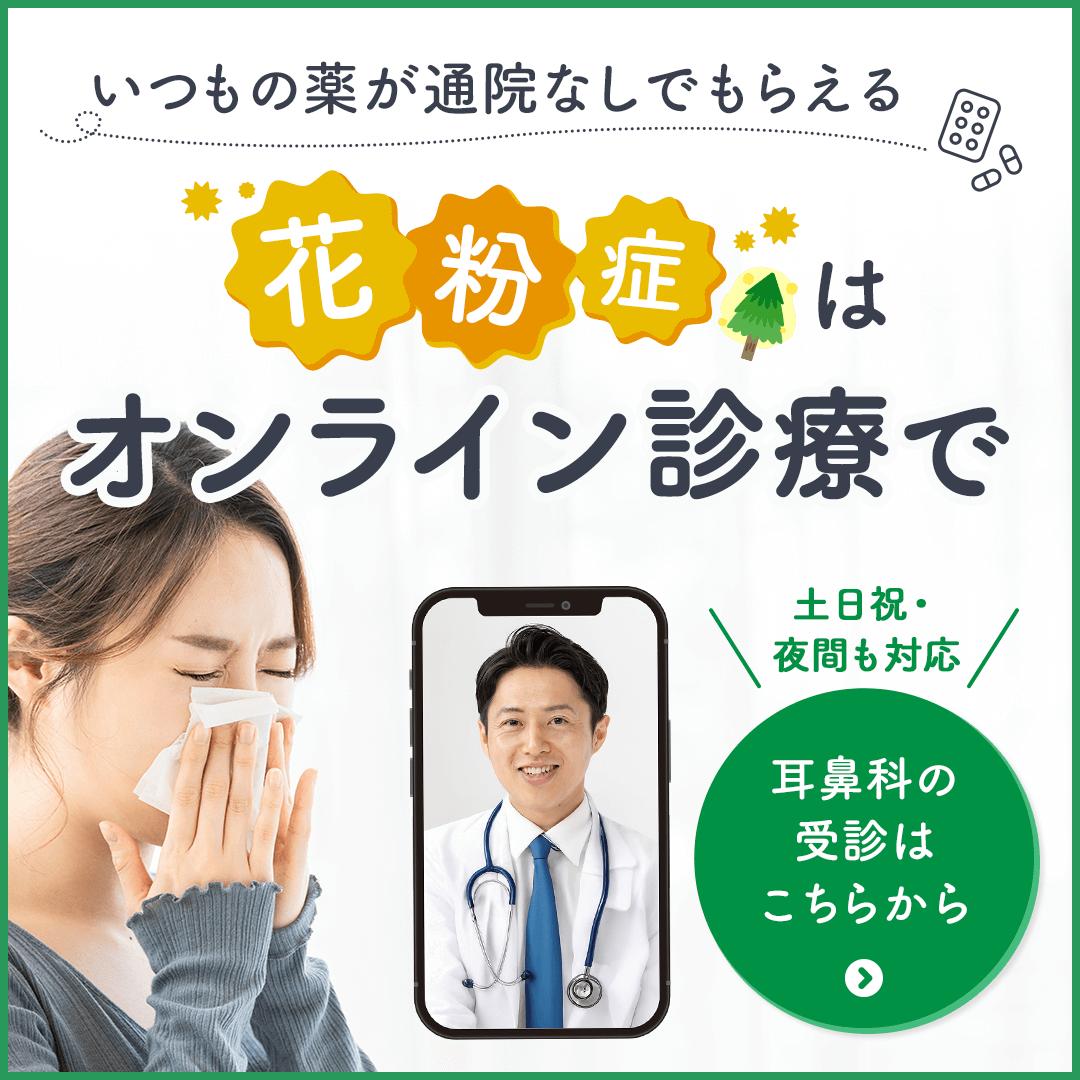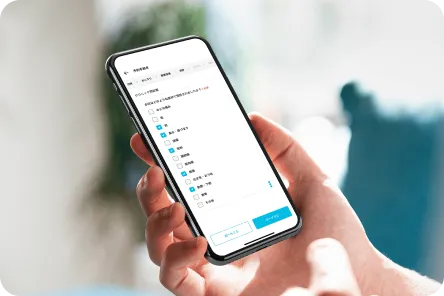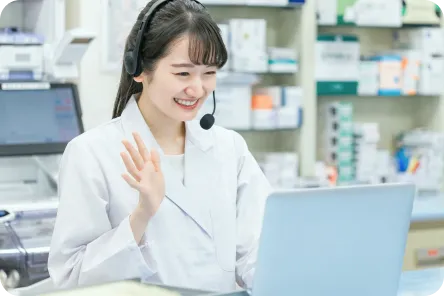アトピー性皮膚炎と食べ物の関係は?体の内側から肌を守る栄養素とは
アトピー性皮膚炎と食べ物の関係
アトピー性皮膚炎の原因はさまざまで、必ずしも食べ物が症状の悪化に関与しているわけではありません。ただし、食生活が乱れると、栄養不足によって肌のバリア機能が低下し、炎症やかゆみが悪化する可能性があります。極端な食事制限や偏食は、症状を悪化させる要因です。
バランスの取れた食事を心がけることで、症状の軽減が期待できます。タンパク質やビタミン、オメガ3脂肪酸、プロバイオティクスなどを適切に摂取することで、肌の健康を保ち、アトピー性皮膚炎の管理に役立ちます。
アトピー性皮膚炎の方が不足している栄養素とは
アトピー性皮膚炎の患者では、血液検査で特有の傾向がみられます。低タンパク、鉄・亜鉛不足、ビタミンA・B群・C不足、低血糖症、抗酸化力の低下が主な特徴です。
タンパク質
タンパク質は肌の弾力やバリア機能を支える重要な成分です。不足すると、肌トラブルが引き起こされ、アトピー性皮膚炎では症状が悪化することがあります。
肌の真皮はコラーゲンが主成分で、タンパク質が弾力を維持しています。不足すると、肌がたるみやすく、免疫細胞の材料でもあるため、感染しやすくなり傷の治りも遅くなります。また、皮膚のバリア機能を支えるフィラグリンもタンパク質が必要です。不足すると保湿能力が低下し、外部刺激やアレルゲンが侵入しやすくなります。
アトピー性皮膚炎の方がタンパク質不足になる理由は、腸内環境の悪化により消化吸収が不十分になったり、皮膚の炎症や損傷でタンパク質が失われやすくなることです。これにより、慢性的にタンパク質が不足していまします。
鉄
鉄は皮膚や粘膜に、酸素と栄養を供給するために欠かせない成分です。不足すると、皮膚や粘膜が酸素不足に陥り、健康な皮膚の再生や保護が難しくなり、乾燥肌やアトピー性皮膚炎の症状が悪化します。
ヘム鉄は酸素を運搬する役割を果たすヘモグロビンに含まれ、組織鉄は皮膚のコラーゲン形成に必要です。鉄不足が進むと、皮膚の酸素や栄養供給が不足し皮膚機能が低下します。また、薬の運搬にも影響し治療効果も低下する可能性もあります。
亜鉛
アトピー性皮膚炎では皮膚のバリア機能が低下し炎症や傷が頻繁に発生します。炎症によって亜鉛が多く消費され、皮膚の剥脱によって亜鉛も失われるため不足しやすくなります。
皮膚に存在する亜鉛はコラーゲンの合成に関与する成分です。不足すると皮膚炎やかゆみ傷が治りにくくなり、免疫機能も低下するため、皮膚感染が長引く原因になります。また、炎症を抑える局所ホルモンの生成にも関与し、不足すると炎症が抑えられなくなります。
ビタミンA
ビタミンAは、乾燥肌のケアにおいて重要な役割を果たす栄養素です。皮膚の細胞の成長と分化を促進し、肌のターンオーバーを正常化させます。これにより、古い角質が適切に排出され、新しい細胞が表面に移動することで、乾燥や肌荒れを防ぐことが可能です。また、皮膚のバリア機能を強化する働きもあります。
ビタミンB群
ビタミンB群は、エネルギー代謝に重要な役割を果たす栄養素です。ナイアシンは、肌のバリア機能を強化し、水分の蒸発を防ぐ効果があります。また、肌の再生をサポートし、乾燥によるダメージを修復するのを助ける働きもあります。
ビタミンC
ビタミンCは、肌の乾燥を予防し、健康を保つためにとても重要な栄養素です。肌のバリア機能を強化し、水分を保つ役割があるため乾燥を防ぎます。さらに、ビタミンCはコラーゲンの生成を助けます。コラーゲンは肌をしっかりと保つ成分です。これによって乾燥や肌荒れ、しわを防げます。また、ビタミンCは抗酸化作用も持っていて、乾燥によるダメージを軽減し、赤みや炎症を和らげます。
アトピー性皮膚炎と腸内環境の関係
腸内細菌叢が乱れると、善玉菌が減り、悪玉菌が増えることから、アレルギーを発症するリスクが高まるとされています。腸内細菌叢が正常に保たれることで、アレルギー症状の発症を抑える可能性があるのです。
プロバイオティクス
プロバイオティクスは腸内環境を整えるのに役立つ微生物のことです。アレルギーを引き起こす免疫反応は、免疫抑制の役割を果たすTregというリンパ球によって調整されています。
腸内で酪酸菌が作り出す酪酸がTregの増加を促すため、アレルギーを抑える効果が期待できます。酪酸菌を増やすためには、ヨーグルトや納豆、キムチなどの発酵食品を多く取ることが有効です。
水溶性食物繊維
酪酸菌を増やすためには、水溶性食物繊維を多く含む食品を摂取することが重要です。水溶性食物繊維は善玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを保つ効果があります。野菜や果物、海藻などに多く含まれているので、意識して摂りましょう。
自己判断で除去食は避けよう
特定の食品が症状を悪化させることはありますが、それだけで病気が発症するわけではありません。適切な治療やスキンケアと並行して、バランスの取れた食生活を心がけることが重要です。食べ物が直接の原因とは限らないため、基本的に食事制限はしないようにしましょう。
食物アレルギーが疑われる場合は、医師の指導のもとでアレルゲンの特定を行い、適切な食事制限を行ってください。自己判断で、食物を除去することは避けましょう。
アトピー性皮膚炎の症状が出ている時に控えた方がいい食べ物
アトピー性皮膚炎の症状が悪化する可能性がある食べ物については個人差があります。ただし、症状の出ているときは、以下の食べ物は控えめにしましょう。
脂肪分が多く含まれる食べ物
肉類の油に多く含まれる飽和脂肪酸、揚げ物や炒め物などで使われる加熱された油、マーガリン、ショートニングなどの合成油に含まれるトランス脂肪酸は、皮膚や血管などの細胞膜をもろくします。体内でアトピー症状を抑制する物質の合成を抑えてしまうため、アトピーの症状が悪化しやすくなります。体内でほとんど分解されずに蓄積されるため、極力摂取を控えてください。
甘いもの
アレルギーの症状が悪化する原因の一つとして、アレルギーに対抗するコルチゾールというホルモンの分泌の減少があります。糖質が多い食べ物を摂取すると、血糖値が急激に上昇し、その後、血糖値を下げるインスリンが大量に分泌されます。その結果、血糖値が急激に下がり、脳が危険を察知して防御反応を示します。
この時に分泌されるのが、副腎で合成されるコルチゾールです。急激な血糖値の変動を避けるためにも、糖質の摂取に注意しましょう。
ヒスタミンを含む食べ物
ヒスタミンやその類似物質を多く含む食べ物は、かゆみを引き起こす可能性があります。サバ、サケ、イカ、エビ、豚肉、そばなどの動物性食品や、たけのこ、ごぼう、なす、さといも、ほうれん草、トマトなどの植物性食品があります。
刺激物
血管を拡張させる作用がある食品(アルコール、辛い物など)は、発汗や皮膚のほてりを引き起こし、かゆみを悪化させる可能性があります。
食事以外の生活習慣も重要
バランスの良い食事、健康的な生活習慣、適度な運動は免疫力を高め、アトピー性皮膚炎の症状を管理するために効果的です。
スキンケア
肌を清潔に保つために、汗や皮膚の汚れを落とし、入浴時は38〜40度のぬるま湯で優しく洗いましょう。熱すぎるお湯はかゆみを引き起こし、皮膚に負担をかけます。入浴後は保湿剤で乾燥を防ぎ、肌の潤いを保つことが重要です。また、乾燥しやすい季節には加湿器を使用して、湿度を保つように心掛けましょう。
ストレスの管理
ストレスはアトピー性皮膚炎を悪化させる要因となることがあります。自分に合った方法でリフレッシュし、ストレスを溜め込まないように心掛けることが大切です。
環境を整える
生活環境中にあるアレルギー原因物質(ダニ、ホコリ、カビ、花粉など)にも、注意が必要です。ダニやホコリにアレルギーがある場合、掃除をこまめに行いましょう。花粉に反応する場合は、花粉の多い時期にマスクや長袖を着用して肌の露出を減らすようにしてください。
アトピー性皮膚炎は食べ物以外のサポートも大切!医師に相談しよう
トピー性皮膚炎のケアには、食べ物以外のサポートも非常に大切です。皮膚科の専門医に相談することで、適切な治療法やアドバイスを受けられます。保湿ケアや適切な環境管理、ストレスの軽減も重要な要素です。
忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ
忙しくて病院に行く時間が取れない場合、オンライン診療が便利です。自宅にいながら医師の診察を受けられるため、時間を効率的に使えます。
オンライン診療とは
オンライン診療とは、自宅にいながらインターネットを利用して医師の診察を受けられる医療サービスです。スマートフォンやパソコンを通じて、ビデオチャットで直接医師とコミュニケーションが取れ、診察から問診、診断、薬の処方まで全てオンラインで完結します。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をよりスムーズに受けられるサービスです。予約から薬の受け取りまで全てアプリをつかって簡単に操作でき、専門スタッフのサポートも受けられます。
お気に入りのクリニックや薬局を登録でき、お薬手帳をデジタル化する機能もあります。全国どこでも当日または翌日に薬を受け取ることが可能です。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒
まとめ
アトピー性皮膚炎の改善には、タンパク質やビタミンなどの不足しやすい栄養素を積極的に摂取することが重要です。また、腸内環境を整えることも、効果が期待できます。脂肪分や甘いもの、刺激物は症状を悪化させる恐れがあるため注意してください。自己判断での食事制限は避け、医師と相談しながらバランスの取れた食事を心掛けましょう。食事だけでなく、スキンケアやストレス管理、生活環境の見直しも行い、総合的にアトピーの症状をケアしましょう。

アトピー性皮膚炎と食べ物の関係が気になったことはありませんか?食事だけで、アトピーを完全に治すことはできません。ただし、適切な栄養バランスを保つことで肌のバリア機能をサポートし、症状の軽減に役立ちます。タンパク質やビタミン、腸内環境を整えるための栄養素が重要です。この記事では、アトピー性皮膚炎と食事の関係、積極的に摂りたい栄養素や控えた方が良い食品について詳しく解説します。
アトピー性皮膚炎と食べ物の関係
アトピー性皮膚炎の原因はさまざまで、必ずしも食べ物が症状の悪化に関与しているわけではありません。ただし、食生活が乱れると、栄養不足によって肌のバリア機能が低下し、炎症やかゆみが悪化する可能性があります。極端な食事制限や偏食は、症状を悪化させる要因です。
バランスの取れた食事を心がけることで、症状の軽減が期待できます。タンパク質やビタミン、オメガ3脂肪酸、プロバイオティクスなどを適切に摂取することで、肌の健康を保ち、アトピー性皮膚炎の管理に役立ちます。
アトピー性皮膚炎の方が不足している栄養素とは
アトピー性皮膚炎の患者では、血液検査で特有の傾向がみられます。低タンパク、鉄・亜鉛不足、ビタミンA・B群・C不足、低血糖症、抗酸化力の低下が主な特徴です。
タンパク質
タンパク質は肌の弾力やバリア機能を支える重要な成分です。不足すると、肌トラブルが引き起こされ、アトピー性皮膚炎では症状が悪化することがあります。
肌の真皮はコラーゲンが主成分で、タンパク質が弾力を維持しています。不足すると、肌がたるみやすく、免疫細胞の材料でもあるため、感染しやすくなり傷の治りも遅くなります。また、皮膚のバリア機能を支えるフィラグリンもタンパク質が必要です。不足すると保湿能力が低下し、外部刺激やアレルゲンが侵入しやすくなります。
アトピー性皮膚炎の方がタンパク質不足になる理由は、腸内環境の悪化により消化吸収が不十分になったり、皮膚の炎症や損傷でタンパク質が失われやすくなることです。これにより、慢性的にタンパク質が不足していまします。
鉄
鉄は皮膚や粘膜に、酸素と栄養を供給するために欠かせない成分です。不足すると、皮膚や粘膜が酸素不足に陥り、健康な皮膚の再生や保護が難しくなり、乾燥肌やアトピー性皮膚炎の症状が悪化します。
ヘム鉄は酸素を運搬する役割を果たすヘモグロビンに含まれ、組織鉄は皮膚のコラーゲン形成に必要です。鉄不足が進むと、皮膚の酸素や栄養供給が不足し皮膚機能が低下します。また、薬の運搬にも影響し治療効果も低下する可能性もあります。
亜鉛
アトピー性皮膚炎では皮膚のバリア機能が低下し炎症や傷が頻繁に発生します。炎症によって亜鉛が多く消費され、皮膚の剥脱によって亜鉛も失われるため不足しやすくなります。
皮膚に存在する亜鉛はコラーゲンの合成に関与する成分です。不足すると皮膚炎やかゆみ傷が治りにくくなり、免疫機能も低下するため、皮膚感染が長引く原因になります。また、炎症を抑える局所ホルモンの生成にも関与し、不足すると炎症が抑えられなくなります。
ビタミンA
ビタミンAは、乾燥肌のケアにおいて重要な役割を果たす栄養素です。皮膚の細胞の成長と分化を促進し、肌のターンオーバーを正常化させます。これにより、古い角質が適切に排出され、新しい細胞が表面に移動することで、乾燥や肌荒れを防ぐことが可能です。また、皮膚のバリア機能を強化する働きもあります。
ビタミンB群
ビタミンB群は、エネルギー代謝に重要な役割を果たす栄養素です。ナイアシンは、肌のバリア機能を強化し、水分の蒸発を防ぐ効果があります。また、肌の再生をサポートし、乾燥によるダメージを修復するのを助ける働きもあります。
ビタミンC
ビタミンCは、肌の乾燥を予防し、健康を保つためにとても重要な栄養素です。肌のバリア機能を強化し、水分を保つ役割があるため乾燥を防ぎます。さらに、ビタミンCはコラーゲンの生成を助けます。コラーゲンは肌をしっかりと保つ成分です。これによって乾燥や肌荒れ、しわを防げます。また、ビタミンCは抗酸化作用も持っていて、乾燥によるダメージを軽減し、赤みや炎症を和らげます。
アトピー性皮膚炎と腸内環境の関係
腸内細菌叢が乱れると、善玉菌が減り、悪玉菌が増えることから、アレルギーを発症するリスクが高まるとされています。腸内細菌叢が正常に保たれることで、アレルギー症状の発症を抑える可能性があるのです。
プロバイオティクス
プロバイオティクスは腸内環境を整えるのに役立つ微生物のことです。アレルギーを引き起こす免疫反応は、免疫抑制の役割を果たすTregというリンパ球によって調整されています。
腸内で酪酸菌が作り出す酪酸がTregの増加を促すため、アレルギーを抑える効果が期待できます。酪酸菌を増やすためには、ヨーグルトや納豆、キムチなどの発酵食品を多く取ることが有効です。
水溶性食物繊維
酪酸菌を増やすためには、水溶性食物繊維を多く含む食品を摂取することが重要です。水溶性食物繊維は善玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを保つ効果があります。野菜や果物、海藻などに多く含まれているので、意識して摂りましょう。
自己判断で除去食は避けよう
特定の食品が症状を悪化させることはありますが、それだけで病気が発症するわけではありません。適切な治療やスキンケアと並行して、バランスの取れた食生活を心がけることが重要です。食べ物が直接の原因とは限らないため、基本的に食事制限はしないようにしましょう。
食物アレルギーが疑われる場合は、医師の指導のもとでアレルゲンの特定を行い、適切な食事制限を行ってください。自己判断で、食物を除去することは避けましょう。
アトピー性皮膚炎の症状が出ている時に控えた方がいい食べ物
アトピー性皮膚炎の症状が悪化する可能性がある食べ物については個人差があります。ただし、症状の出ているときは、以下の食べ物は控えめにしましょう。
脂肪分が多く含まれる食べ物
肉類の油に多く含まれる飽和脂肪酸、揚げ物や炒め物などで使われる加熱された油、マーガリン、ショートニングなどの合成油に含まれるトランス脂肪酸は、皮膚や血管などの細胞膜をもろくします。体内でアトピー症状を抑制する物質の合成を抑えてしまうため、アトピーの症状が悪化しやすくなります。体内でほとんど分解されずに蓄積されるため、極力摂取を控えてください。
甘いもの
アレルギーの症状が悪化する原因の一つとして、アレルギーに対抗するコルチゾールというホルモンの分泌の減少があります。糖質が多い食べ物を摂取すると、血糖値が急激に上昇し、その後、血糖値を下げるインスリンが大量に分泌されます。その結果、血糖値が急激に下がり、脳が危険を察知して防御反応を示します。
この時に分泌されるのが、副腎で合成されるコルチゾールです。急激な血糖値の変動を避けるためにも、糖質の摂取に注意しましょう。
ヒスタミンを含む食べ物
ヒスタミンやその類似物質を多く含む食べ物は、かゆみを引き起こす可能性があります。サバ、サケ、イカ、エビ、豚肉、そばなどの動物性食品や、たけのこ、ごぼう、なす、さといも、ほうれん草、トマトなどの植物性食品があります。
刺激物
血管を拡張させる作用がある食品(アルコール、辛い物など)は、発汗や皮膚のほてりを引き起こし、かゆみを悪化させる可能性があります。
食事以外の生活習慣も重要
バランスの良い食事、健康的な生活習慣、適度な運動は免疫力を高め、アトピー性皮膚炎の症状を管理するために効果的です。
スキンケア
肌を清潔に保つために、汗や皮膚の汚れを落とし、入浴時は38〜40度のぬるま湯で優しく洗いましょう。熱すぎるお湯はかゆみを引き起こし、皮膚に負担をかけます。入浴後は保湿剤で乾燥を防ぎ、肌の潤いを保つことが重要です。また、乾燥しやすい季節には加湿器を使用して、湿度を保つように心掛けましょう。
ストレスの管理
ストレスはアトピー性皮膚炎を悪化させる要因となることがあります。自分に合った方法でリフレッシュし、ストレスを溜め込まないように心掛けることが大切です。
環境を整える
生活環境中にあるアレルギー原因物質(ダニ、ホコリ、カビ、花粉など)にも、注意が必要です。ダニやホコリにアレルギーがある場合、掃除をこまめに行いましょう。花粉に反応する場合は、花粉の多い時期にマスクや長袖を着用して肌の露出を減らすようにしてください。
アトピー性皮膚炎は食べ物以外のサポートも大切!医師に相談しよう
トピー性皮膚炎のケアには、食べ物以外のサポートも非常に大切です。皮膚科の専門医に相談することで、適切な治療法やアドバイスを受けられます。保湿ケアや適切な環境管理、ストレスの軽減も重要な要素です。
忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ
忙しくて病院に行く時間が取れない場合、オンライン診療が便利です。自宅にいながら医師の診察を受けられるため、時間を効率的に使えます。
オンライン診療とは
オンライン診療とは、自宅にいながらインターネットを利用して医師の診察を受けられる医療サービスです。スマートフォンやパソコンを通じて、ビデオチャットで直接医師とコミュニケーションが取れ、診察から問診、診断、薬の処方まで全てオンラインで完結します。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をよりスムーズに受けられるサービスです。予約から薬の受け取りまで全てアプリをつかって簡単に操作でき、専門スタッフのサポートも受けられます。
お気に入りのクリニックや薬局を登録でき、お薬手帳をデジタル化する機能もあります。全国どこでも当日または翌日に薬を受け取ることが可能です。
まとめ
アトピー性皮膚炎の改善には、タンパク質やビタミンなどの不足しやすい栄養素を積極的に摂取することが重要です。また、腸内環境を整えることも、効果が期待できます。脂肪分や甘いもの、刺激物は症状を悪化させる恐れがあるため注意してください。自己判断での食事制限は避け、医師と相談しながらバランスの取れた食事を心掛けましょう。食事だけでなく、スキンケアやストレス管理、生活環境の見直しも行い、総合的にアトピーの症状をケアしましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。