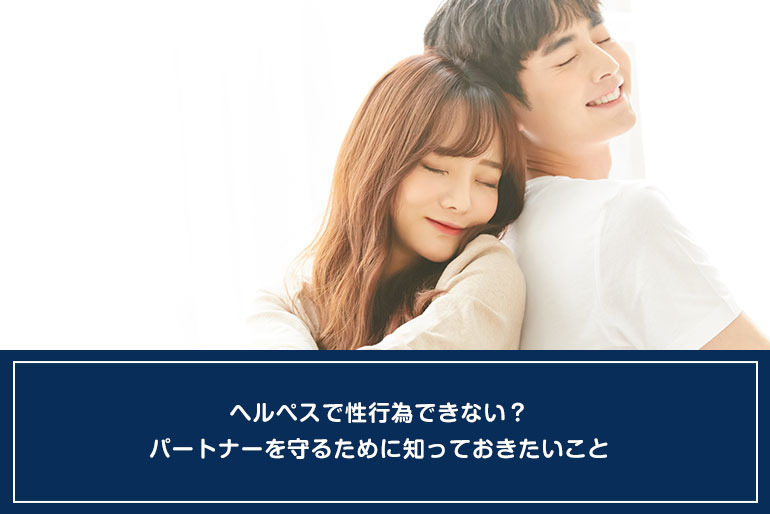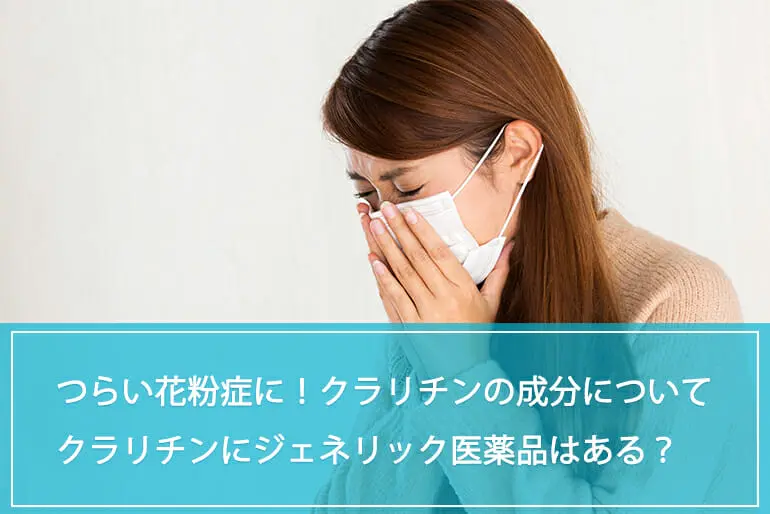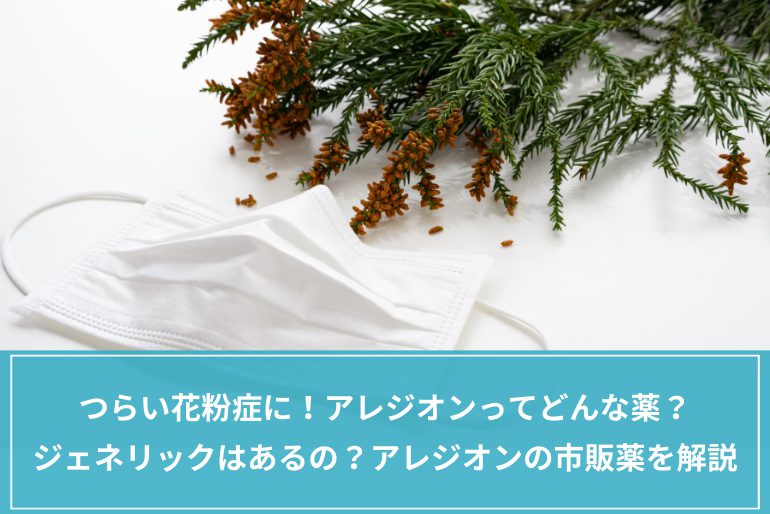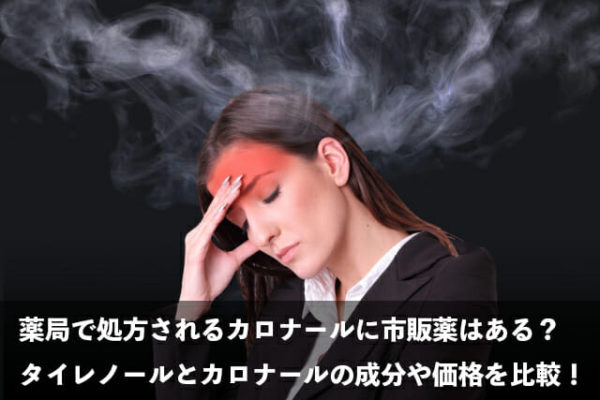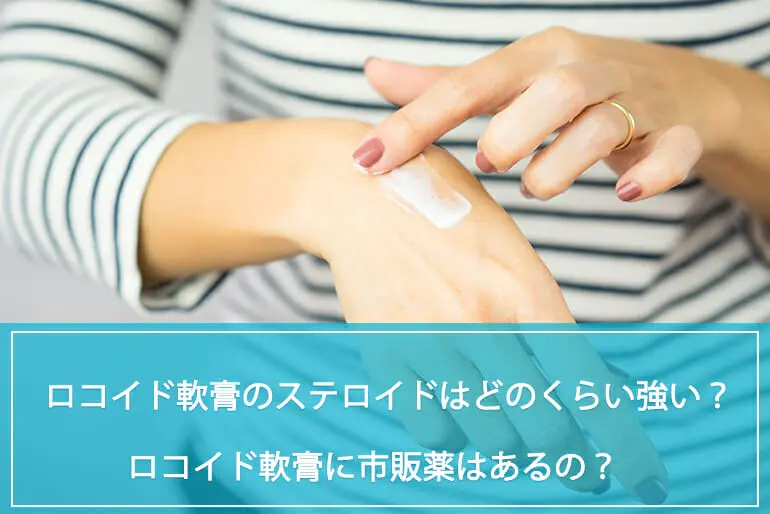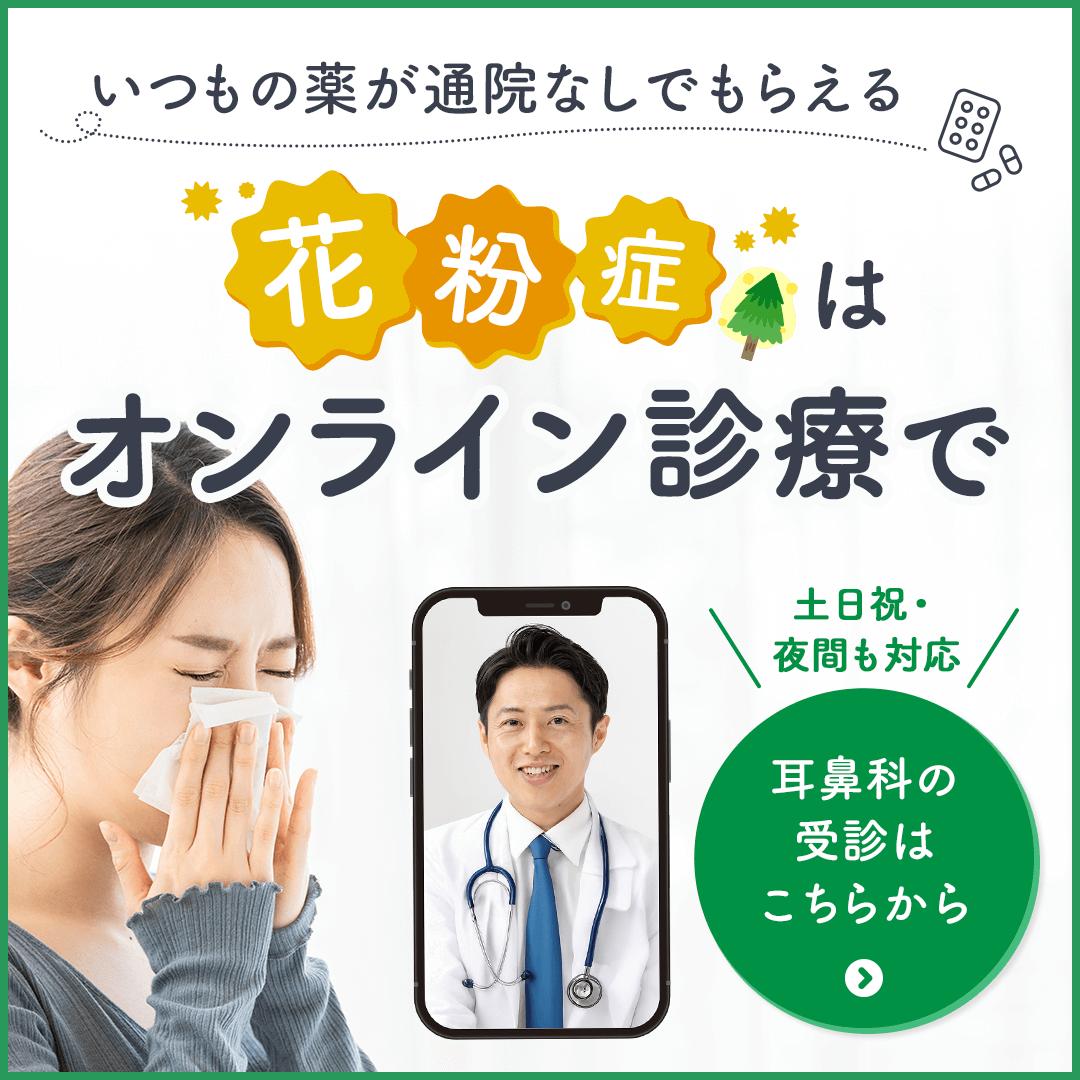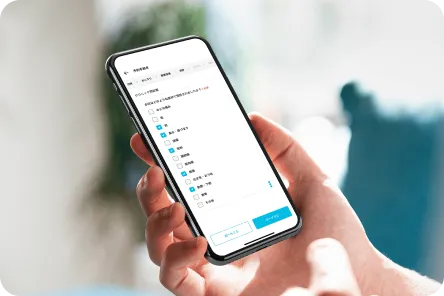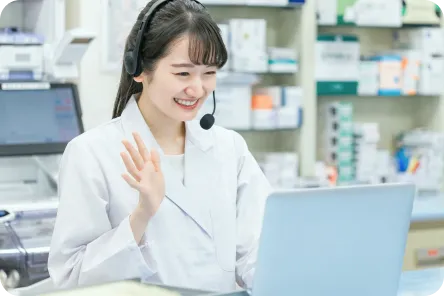【医師監修】おなかを整えたらアトピー性皮膚炎は改善する?乳酸菌との関係とは
腸内フローラとは
私たちの腸内には、約500〜1000種類、100兆個以上の細菌が存在し、それぞれが勢力を保ちながら共存しています。これらの腸内細菌は、食事に含まれる栄養素や体内の分泌物、腸の壁から剥がれた細胞などを養分として増殖します。
腸内フローラとは、人間の腸内に存在する細菌の生態系のことです。小腸の終わりから大腸にかけての腸壁には、細菌が種類ごとに密集して分布しています。この様子が花畑のように見えることが「腸内フローラ」または「腸内細菌叢」と呼ばれている理由です。
腸内フローラの構成は人それぞれ異なり、食事や生活習慣、年齢などによって変化する特徴があります。
肌と腸内細菌の関係
皮膚には腸と同じように、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、アクネ桿菌などの常在菌が存在し、これらは「皮膚フローラ」と呼ばれます。黄色ブドウ球菌は傷の化膿、アクネ桿菌はニキビの原因となることで知られていますが、通常は皮膚に悪影響を及ぼすことはありません。
近年の研究では、腸内フローラの状態が皮膚の健康に影響を与えることが示唆されています。腸内フローラのバランスが乱れると腸管のバリア機能が低下し、有害な微生物や物質が体内に侵入しやすくなります。その結果、免疫システムが過剰に反応し、全身の炎症や免疫異常を引き起こし、皮膚の炎症の発生や悪化につながると考えられているのです。
アレルギーと腸内細菌の関係
腸は食べ物を消化・吸収しながら、体にとって異物となるものに直接触れるため、免疫機能が非常に発達しています。体内の免疫細胞の約60%が腸に集まり、病原菌や異物から体を守る役割を果たしているのです。腸には「腸管免疫」と呼ばれる高度な免疫システムが備わっており、これは食べ物と病原菌を適切に区別して対処する仕組みです。アレルギー体質の人は、この免疫システムに偏りが生じやすいと考えられています。
2型ヘルパーT細胞
免疫には、「1型ヘルパーT細胞(Th1)」と「2型ヘルパーT細胞(Th2)」という二つの司令塔が存在しています。Th1は外敵を直接排除する細胞性免疫、Th2は抗体を使って攻撃する液性免疫が担当です。アレルギー体質の人はTh2の働きが強くなりすぎることで、本来無害な物質にも過剰に反応してしまいます。そのため、Th1を活性化させ、Th2の働きを抑えることがアレルギーの改善につながると考えられています。
悪玉菌の増加
腸内にはさまざまな細菌が共存しており、細菌のバランスが免疫機能に影響を与えます。悪玉菌が増えると腸内環境が乱れ、免疫全体が過敏になり、アレルギー反応を引き起こしやすくなります。
乳酸菌と免疫機能の関係
乳酸菌がどのように免疫機能と関係しているのか見ていきましょう。
腸内細菌の種類
腸内細菌には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類があり、それぞれ異なる働きを持ちます。
善玉菌
| 代表的な菌 | 乳酸菌、ビフィズス菌、フェカリス菌 |
| 主な作用 | ビタミンの合成 消化吸収の補助 免疫刺激 感染防御 |
| 役割 | 健康維持や老化防止 |
悪玉菌
| 代表的な菌 | ウェルシュ菌、大腸菌(毒性株)ブドウ球菌 |
| 主な作用 | 腸内腐敗
細菌毒素や発ガン物質の産生 ガス発生 |
| 役割 | 身体に害を与える |
日和見菌
| 代表的な菌 | 大腸菌(無毒株)、連鎖球菌 |
| 役割 | 通常は無害。体調が悪化すると腸内で悪い働きをする |
乳酸菌の役割
腸内フローラのバランスが崩れると、免疫機能が正常に維持できません。乳酸菌は、発酵によって糖類から乳酸を作り出す微生物です。腸内で悪玉菌の繁殖を抑えることで、腸内環境を整える役割を果たしています。
最近の研究では、腸内フローラの乱れが自己免疫疾患やアレルギー、がん、肥満などの発症に関わることがわかっています。理想的な腸内フローラのバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」です。善玉菌を優位に保つことで、日和見菌を味方にし、悪玉菌の増殖を抑えられます。
乳酸菌はヨーグルトやチーズ、漬け物、日本酒などの発酵食品に多く含まれています。乳酸菌が腸に届いて働くためには、生きたままで腸に届くことが重要です。乳酸菌がより増えるためには、オリゴ糖などの栄養源が必要になります。
善玉菌が作り出す酸
善玉菌が作り出す酸の中には、酪酸や酢酸、プロピオン酸といった「短鎖脂肪酸」があります。この短鎖脂肪酸が、体の免疫機能を保つ重要なカギです。
短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えることで腸内フローラを整える働きがあります。また、便秘を防いだり、軟便を改善したりと、腸内の健康をサポートします。
最近の研究では、短鎖脂肪酸が全身の免疫機能にも関わっていることが分かってきました。そのため、免疫機能の維持に欠かせません。酪酸は、小腸の腸壁に存在するT細胞に働きかけて免疫機能をコントロールします。
腸内環境を整える方法
腸内環境を整える方法として、食事、ストレス管理、運動習慣の3つを意識することが重要です。
食事
シンバイオティクスを意識しましょう。シンバイオティクスというのは、腸に良い微生物(プロバイオティクス)とその微生物が元気に育つための栄養(プレバイオティクス)を一緒に摂ることです。
例えば、ヨーグルトや納豆には腸に良い微生物が含まれており、これがプロバイオティクスです。そして、オリゴ糖や食物繊維(大麦やめかぶなどに含まれるもの)は、これらの微生物が増えやすくなるための栄養素、つまりプレバイオティクスです。
オリゴ糖や大麦、めかぶなどを食べながら、ヨーグルトや納豆などを取り入れると、シンバイオティクスの効果を実感できるでしょう。
運動
肥満や座りがちな生活は腸内フローラに悪影響を与えることが知られています。活動的な生活を送ることで、腸内細菌の多様性が増し、腸内環境が改善されます。日常的に歩いたり動いたりすることが、健康な腸内フローラを育むポイントです。
ストレス管理
腸と脳は相互に影響し合っており、ストレスを感じていると腸内フローラのバランスが崩れやすくなります。特に高脂肪食とストレスが重なると、腸内環境がさらに乱れる可能性があるため、揚げ物やお菓子をストレス解消に使うことは避けましょう。リラックスやリフレッシュする時間を取り、心身の健康を保つことが大切です。
アトピー性皮膚炎をコントロールするには医師のサポートも必要
乳酸菌などの善玉菌が増えることで腸内環境が整い、免疫機能の調整が進むため、アトピー性皮膚炎の症状の軽減に繋がる可能性があります。しかし、腸内環境の改善だけでは完全にコントロールすることは難しく、医師のサポートが必要です。腸内環境を整えることと、適切な治療が組み合わさることで、症状をより効果的に管理できると言えます。
忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ
軽い症状や定期的なフォローアップが必要な場合、オンライン診療を活用すれば効率的に健康管理ができるため、忙しい方にはおすすめの方法です。
オンライン診療とは
オンライン診療とは、インターネットを利用して自宅にいながら医師と診察を受けられるサービスです。スマートフォン、タブレット、パソコンを使って、ビデオチャットで医師と直接話せます。このサービスでは、診察の予約、問診、診断、薬の処方箋発行、支払いまで、すべてオンラインで完結できることが特徴です。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をよりスムーズに行えるサービスです。アプリを操作して、診察の予約からお薬の受け取りまで、すべてのステップを簡単に行えます。
特徴としては、専門スタッフのサポートが受けられたり、お気に入りのクリニックや薬局を登録する機能があります。また、お薬手帳をデジタル化できるため、管理が便利です。お薬は全国どこでも、当日または翌日に受け取れます。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒
まとめ
腸内フローラのバランスを整えることが、アトピー性皮膚炎の改善に効果をもたらす可能性があります。腸内環境を健やかに保つためには、食事、運動、ストレス管理に気を付けることが重要です。しかし、症状の適切なコントロールには医師のサポートが欠かせません。自己判断せず専門医と相談しながら、内側から健康的な肌を目指しましょう。

アトピー性皮膚炎と腸内環境には密接なつながりがあることをご存じでしょうか。近年、腸内フローラのバランスが、免疫機能やアレルギー反応に影響を及ぼすことが明らかになっています。特に乳酸菌をはじめとする善玉菌は、腸内環境を整え、アレルギー症状の軽減に役立つ可能性があると注目されています。本記事では、腸と肌の関係や乳酸菌の役割、腸内環境を整える方法について詳しく解説します。
腸内フローラとは
私たちの腸内には、約500〜1000種類、100兆個以上の細菌が存在し、それぞれが勢力を保ちながら共存しています。これらの腸内細菌は、食事に含まれる栄養素や体内の分泌物、腸の壁から剥がれた細胞などを養分として増殖します。
腸内フローラとは、人間の腸内に存在する細菌の生態系のことです。小腸の終わりから大腸にかけての腸壁には、細菌が種類ごとに密集して分布しています。この様子が花畑のように見えることが「腸内フローラ」または「腸内細菌叢」と呼ばれている理由です。
腸内フローラの構成は人それぞれ異なり、食事や生活習慣、年齢などによって変化する特徴があります。
肌と腸内細菌の関係
皮膚には腸と同じように、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、アクネ桿菌などの常在菌が存在し、これらは「皮膚フローラ」と呼ばれます。黄色ブドウ球菌は傷の化膿、アクネ桿菌はニキビの原因となることで知られていますが、通常は皮膚に悪影響を及ぼすことはありません。
近年の研究では、腸内フローラの状態が皮膚の健康に影響を与えることが示唆されています。腸内フローラのバランスが乱れると腸管のバリア機能が低下し、有害な微生物や物質が体内に侵入しやすくなります。その結果、免疫システムが過剰に反応し、全身の炎症や免疫異常を引き起こし、皮膚の炎症の発生や悪化につながると考えられているのです。
アレルギーと腸内細菌の関係
腸は食べ物を消化・吸収しながら、体にとって異物となるものに直接触れるため、免疫機能が非常に発達しています。体内の免疫細胞の約60%が腸に集まり、病原菌や異物から体を守る役割を果たしているのです。腸には「腸管免疫」と呼ばれる高度な免疫システムが備わっており、これは食べ物と病原菌を適切に区別して対処する仕組みです。アレルギー体質の人は、この免疫システムに偏りが生じやすいと考えられています。
2型ヘルパーT細胞
免疫には、「1型ヘルパーT細胞(Th1)」と「2型ヘルパーT細胞(Th2)」という二つの司令塔が存在しています。Th1は外敵を直接排除する細胞性免疫、Th2は抗体を使って攻撃する液性免疫が担当です。アレルギー体質の人はTh2の働きが強くなりすぎることで、本来無害な物質にも過剰に反応してしまいます。そのため、Th1を活性化させ、Th2の働きを抑えることがアレルギーの改善につながると考えられています。
悪玉菌の増加
腸内にはさまざまな細菌が共存しており、細菌のバランスが免疫機能に影響を与えます。悪玉菌が増えると腸内環境が乱れ、免疫全体が過敏になり、アレルギー反応を引き起こしやすくなります。
乳酸菌と免疫機能の関係
乳酸菌がどのように免疫機能と関係しているのか見ていきましょう。
腸内細菌の種類
腸内細菌には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類があり、それぞれ異なる働きを持ちます。
善玉菌
| 代表的な菌 | 乳酸菌、ビフィズス菌、フェカリス菌 |
| 主な作用 | ビタミンの合成 消化吸収の補助 免疫刺激 感染防御 |
| 役割 | 健康維持や老化防止 |
悪玉菌
| 代表的な菌 | ウェルシュ菌、大腸菌(毒性株)ブドウ球菌 |
| 主な作用 | 腸内腐敗
細菌毒素や発ガン物質の産生 ガス発生 |
| 役割 | 身体に害を与える |
日和見菌
| 代表的な菌 | 大腸菌(無毒株)、連鎖球菌 |
| 役割 | 通常は無害。体調が悪化すると腸内で悪い働きをする |
乳酸菌の役割
腸内フローラのバランスが崩れると、免疫機能が正常に維持できません。乳酸菌は、発酵によって糖類から乳酸を作り出す微生物です。腸内で悪玉菌の繁殖を抑えることで、腸内環境を整える役割を果たしています。
最近の研究では、腸内フローラの乱れが自己免疫疾患やアレルギー、がん、肥満などの発症に関わることがわかっています。理想的な腸内フローラのバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」です。善玉菌を優位に保つことで、日和見菌を味方にし、悪玉菌の増殖を抑えられます。
乳酸菌はヨーグルトやチーズ、漬け物、日本酒などの発酵食品に多く含まれています。乳酸菌が腸に届いて働くためには、生きたままで腸に届くことが重要です。乳酸菌がより増えるためには、オリゴ糖などの栄養源が必要になります。
善玉菌が作り出す酸
善玉菌が作り出す酸の中には、酪酸や酢酸、プロピオン酸といった「短鎖脂肪酸」があります。この短鎖脂肪酸が、体の免疫機能を保つ重要なカギです。
短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えることで腸内フローラを整える働きがあります。また、便秘を防いだり、軟便を改善したりと、腸内の健康をサポートします。
最近の研究では、短鎖脂肪酸が全身の免疫機能にも関わっていることが分かってきました。そのため、免疫機能の維持に欠かせません。酪酸は、小腸の腸壁に存在するT細胞に働きかけて免疫機能をコントロールします。
腸内環境を整える方法
腸内環境を整える方法として、食事、ストレス管理、運動習慣の3つを意識することが重要です。
食事
シンバイオティクスを意識しましょう。シンバイオティクスというのは、腸に良い微生物(プロバイオティクス)とその微生物が元気に育つための栄養(プレバイオティクス)を一緒に摂ることです。
例えば、ヨーグルトや納豆には腸に良い微生物が含まれており、これがプロバイオティクスです。そして、オリゴ糖や食物繊維(大麦やめかぶなどに含まれるもの)は、これらの微生物が増えやすくなるための栄養素、つまりプレバイオティクスです。
オリゴ糖や大麦、めかぶなどを食べながら、ヨーグルトや納豆などを取り入れると、シンバイオティクスの効果を実感できるでしょう。
運動
肥満や座りがちな生活は腸内フローラに悪影響を与えることが知られています。活動的な生活を送ることで、腸内細菌の多様性が増し、腸内環境が改善されます。日常的に歩いたり動いたりすることが、健康な腸内フローラを育むポイントです。
ストレス管理
腸と脳は相互に影響し合っており、ストレスを感じていると腸内フローラのバランスが崩れやすくなります。特に高脂肪食とストレスが重なると、腸内環境がさらに乱れる可能性があるため、揚げ物やお菓子をストレス解消に使うことは避けましょう。リラックスやリフレッシュする時間を取り、心身の健康を保つことが大切です。
アトピー性皮膚炎をコントロールするには医師のサポートも必要
乳酸菌などの善玉菌が増えることで腸内環境が整い、免疫機能の調整が進むため、アトピー性皮膚炎の症状の軽減に繋がる可能性があります。しかし、腸内環境の改善だけでは完全にコントロールすることは難しく、医師のサポートが必要です。腸内環境を整えることと、適切な治療が組み合わさることで、症状をより効果的に管理できると言えます。
忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ
軽い症状や定期的なフォローアップが必要な場合、オンライン診療を活用すれば効率的に健康管理ができるため、忙しい方にはおすすめの方法です。
オンライン診療とは
オンライン診療とは、インターネットを利用して自宅にいながら医師と診察を受けられるサービスです。スマートフォン、タブレット、パソコンを使って、ビデオチャットで医師と直接話せます。このサービスでは、診察の予約、問診、診断、薬の処方箋発行、支払いまで、すべてオンラインで完結できることが特徴です。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をよりスムーズに行えるサービスです。アプリを操作して、診察の予約からお薬の受け取りまで、すべてのステップを簡単に行えます。
特徴としては、専門スタッフのサポートが受けられたり、お気に入りのクリニックや薬局を登録する機能があります。また、お薬手帳をデジタル化できるため、管理が便利です。お薬は全国どこでも、当日または翌日に受け取れます。
まとめ
腸内フローラのバランスを整えることが、アトピー性皮膚炎の改善に効果をもたらす可能性があります。腸内環境を健やかに保つためには、食事、運動、ストレス管理に気を付けることが重要です。しかし、症状の適切なコントロールには医師のサポートが欠かせません。自己判断せず専門医と相談しながら、内側から健康的な肌を目指しましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。