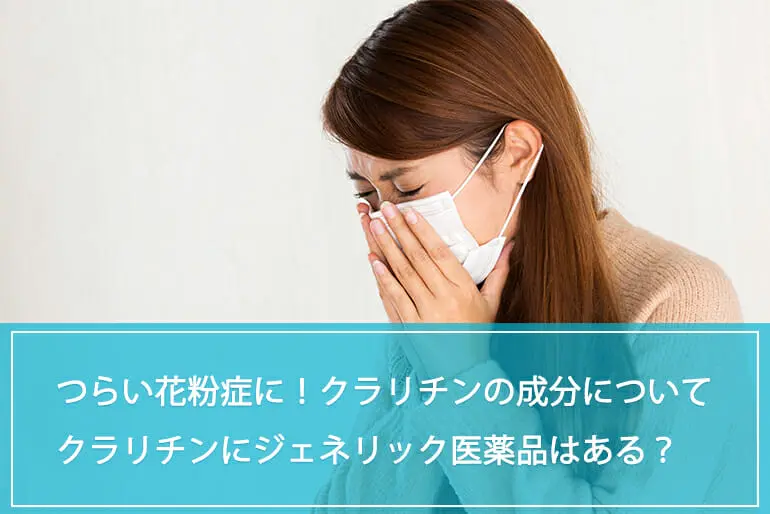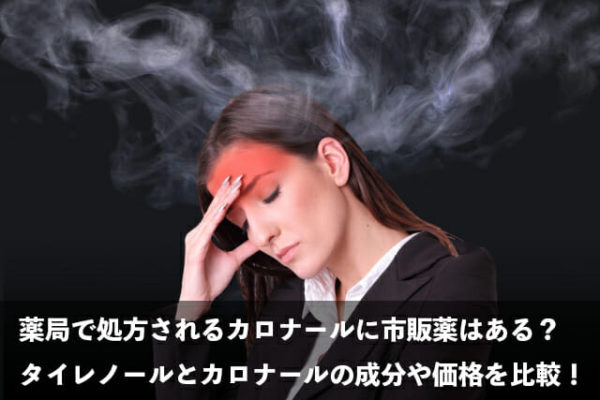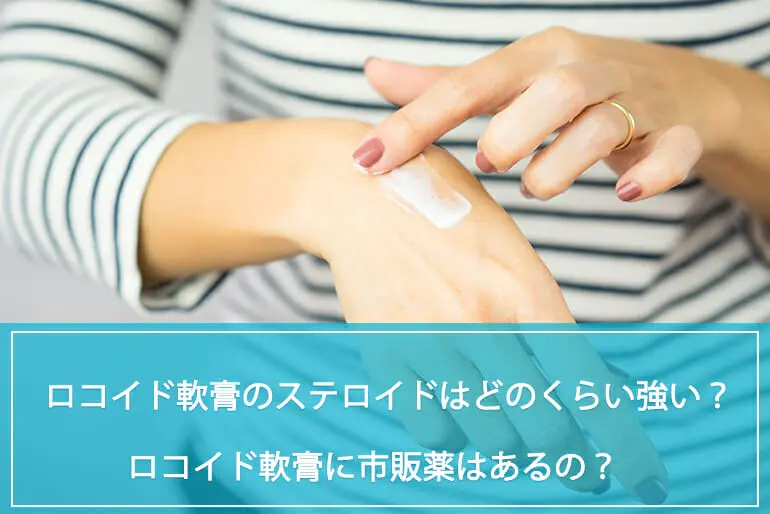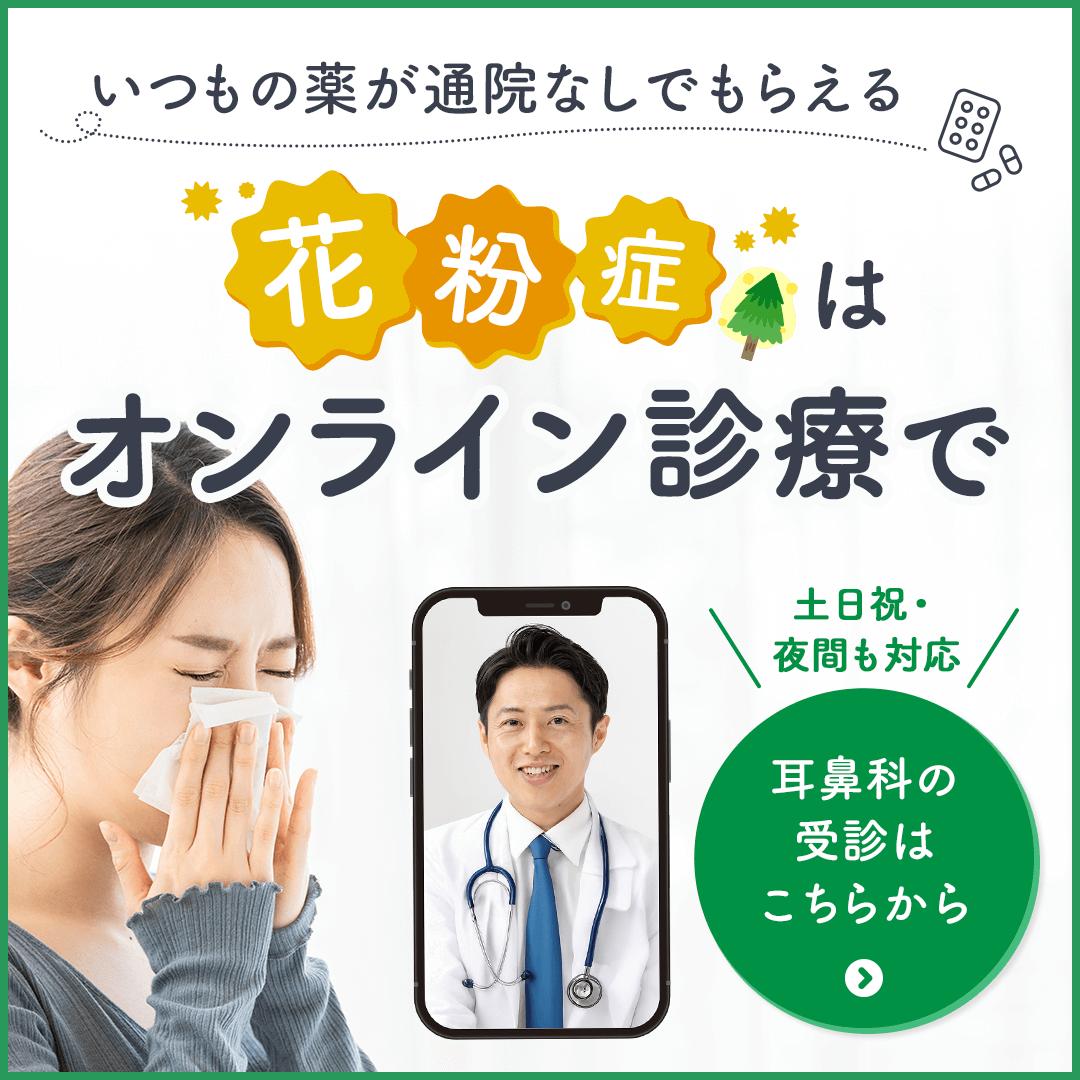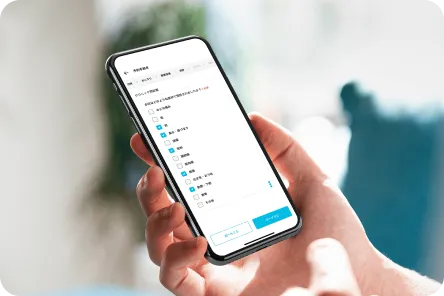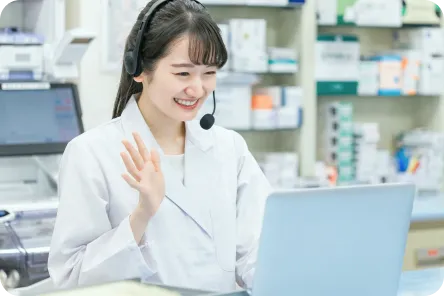【医師監修】アトピーとアレルギーの違いは?両方が共存することも。特徴を詳しく解説
アトピーとは
アトピーは、かゆみを伴う湿疹が主な症状で、良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性的な病気です。皮膚の内部で炎症が起こり、本来備わっているバリア機能が低下します。その結果、外部からの刺激を受けやすくなり、かゆみが生じます。
アトピーのしくみ
アトピーの原因には、体質的な要因と環境的な要因が関係しています。体質的な要因としては、アトピー素因や皮膚のバリア機能が低下している状態が要因です。
人間の皮膚には、外部からの刺激や細菌の侵入を防ぎ、体内の水分が逃げないようにするバリア機能が備わっています。アトピーの方の皮膚は、バリア機能が低下しているため、角層を構成する角質細胞間脂質や水分を保持する天然保湿因子が減少し、角層のバランスが崩れています。その結果、外部からの刺激やアレルゲンが侵入しやすくなるのです。
アレルゲンが皮膚から侵入すると、免疫細胞が反応し、ヒスタミンという物質を放出することで炎症が起こります。
原因となるもの
アトピー性皮膚炎の悪化要因は人によって異なります。多くの場合、1つの要因だけでなく、複数の要因が重なり合って症状が悪化します。代表的な悪化要因は、汗やストレス、ハウスダストやダニ、細菌・カビ、食べ物などです。
アレルギーとは
私たちの体には、ウイルスや細菌などの異物が侵入した際に、それを排除するために「抗体」が作られ、外敵と戦う「免疫」という仕組みが備わっています。しかし、この免疫が本来害のない食べ物や花粉などに対しても「有害なもの」と誤って認識し、過剰に反応してしまうのがアレルギーです。本来は体を守るはずの免疫反応が、逆にかゆみやくしゃみ、炎症などの症状を引き起こし、自分自身を傷つけてしまいます。
アレルギーのしくみ
アレルゲンが侵入すると、体内ではIgE抗体というタンパク質が作られ、これが皮膚や粘膜にあるマスト細胞の表面に付着します。再び同じアレルゲンが体内に入ると、IgE抗体と結合し、マスト細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出されます。
このヒスタミンが神経を刺激し、かゆみやくしゃみ、炎症などのアレルギー症状を引き起こします。アレルギー反応は、体を守るための仕組みがかえって自分自身を攻撃する形となり、さまざまな症状を引き起こします。
原因となるもの
食物アレルゲンには、卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、大豆、魚類、肉類、果物などがあります。吸入性アレルゲンは、ダニやホコリ、カビ、ペットの毛、寝具や衣類の素材、花粉などです。接触性アレルゲンは、化粧品、塗料、衣服、金属、うるし、ゴム(ラテックス)、洗剤などがあり、肌に触れることで、かぶれや炎症を引き起こすことがあります。
アトピーとアレルギーの違い
| アトピー | アレルギー | |
| 発症の仕組み | 遺伝的に皮膚のバリア機能が弱く、アレルギーを起こしやすい体質 | 免疫が本来無害な物質に対して過剰に反応 |
| 原因 | 遺伝的要因に、環境要因が症状を引き起こす | 環境要因(アレルゲン)が主な原因 |
| 免疫反応 | Ⅰ型アレルギー | Ⅰ型~Ⅳ型アレルギー |
| 症状 | 皮膚の乾燥、湿疹、かゆみ、鼻炎、気道の炎症 | 蕁麻疹、くしゃみ、鼻水、喘息、アナフィラキシーなど |
アトピーとアレルギーの関係
アレルギーによる病気そのものは遺伝しませんが、アレルギーを起こしやすい体質は親から子へ受け継がれることがあります。アトピー素因を持つ親がアトピー性皮膚炎だったとしても、その子どもが必ず同じ病気になるわけではありません。しかし、受け継いだ体質の影響で、喘息やアレルギー性鼻炎、食物アレルギーなど、別のアレルギー疾患を発症する可能性があります。
アレルギーマーチとは
幼少期にアトピー性皮膚炎を発症し、成長とともに症状が落ち着いた後、今度は喘息やアレルギー性鼻炎を発症するケースもあります。一つのアレルギー性疾患が治まった後に、別のアレルギー疾患が続けて現れる現象が「アレルギーマーチ」です。
アトピー性皮膚炎と併存することがあるアレルギー疾患
アトピー性皮膚炎の方は、他のアレルギー性疾患を発症しやすい傾向があります。
気管支喘息
気管支喘息は気道に慢性的な炎症が続き、さまざまな刺激に対して過敏になり発作的に気道が狭くなる病気です。炎症が持続することで気道が敏感になり、ちょっとした刺激でも強く反応し、呼吸がしにくくなる発作を繰り返します。
炎症の主な原因は、ダニやハウスダスト、ペットのフケ、カビなどのアレルゲンです。喘息発作が起こると、突然咳が出たり、痰が出て、ゼーゼー・ヒューヒューという音を伴いながら息苦しさを感じます。特に夜間や早朝に症状が出やすいのが特徴です。
アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎は、アレルゲンが原因となり、鼻の粘膜が過剰に反応することで発症する疾患です。原因となるアレルゲンの種類によって、通年性アレルギー性鼻炎と季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)に分けられます。
通年性アレルギー性鼻炎は、ダニやホコリ、ペットの毛などが原因となり、一年を通して鼻炎の症状が現れます。主な症状は、くしゃみ、透明で水っぽい鼻水、鼻づまりです。通常、鼻を通して空気を吸うことで湿度が調整され、体内に入りやすい状態になります。
食物アレルギー
食物アレルギーとは、摂取した食物が原因となり、免疫の仕組みを介して蕁麻疹、湿疹、下痢、咳、呼吸困難などの症状が引き起こされる状態を指します。アレルギー反応の対象となるのは、主に動植物由来のタンパク質です。食物アレルギーは免疫の働きを介して発症するため、食物が原因で体に異常が出る場合でも、すべてが食物アレルギーとは限りません。
花粉症
花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となり、免疫反応によって鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの症状が引き起こされるアレルギー疾患です。季節性アレルギー性鼻炎とも呼ばれ、特定の時期に症状が現れるのが特徴です。
アレルギーマーチを予防する方法は
体質そのものを変えることは難しいですが、日常生活に注意することで予防につながります。
環境を整える
ダニやホコリ、カビを減らすことで、アレルギー症状の悪化を防げます。布団やシーツなどの寝具は、ダニが繁殖しやすいため、清潔に保つことが重要です。
布団専用の掃除機や、掃除機用の布団アタッチメントを使用し、ダニやホコリを吸い取るようにしましょう。また、シーツやカバーは週1回程度洗濯し、できれば天日干しをするのが理想的です。
スキンケアを行う
皮膚のバリア機能が低下すると、アレルゲンが体内に侵入しやすくなり、アレルギー症状が悪化する原因になります。乳幼児は皮膚が薄く、皮脂の分泌が少ないため、バリア機能が未熟で注意が必要です。
バリア機能を守るためには、清潔と保湿が重要です。毎日の入浴やシャワーで汗や汚れを落とし、入浴後はすぐに保湿剤を塗って皮膚の乾燥を防ぎましょう。肌を傷つけないために、ナイロンタオルは避け、低刺激の石鹸やボディーソープを使い、泡で包み込むようにやさしく洗うのが理想的です。
腸内環境を整える
腸内環境を整えることで免疫のバランスが整い、アレルギー症状の軽減につながります。悪玉菌が増えると免疫機能が低下し、アレルギー性疾患を発症しやすくなるため注意しましょう。
腸内細菌は、食べたものをエサにして生きています。食物繊維やオリゴ糖は善玉菌のエサになり、肉類のタンパク質や揚げ物などの脂質は悪玉菌のエサになります。アレルギー症状を悪化させないためには、発酵食品(ヨーグルト・納豆・味噌など)や食物繊維を含む野菜・果物を積極的に摂ることが大切です。
病院を受診する
アレルギー症状が続く場合や、自己管理だけでは改善が見られないときは、病院を受診することが大切です。適切な治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質を向上させることが可能です。
気になる症状があれば放置せず医療機関を受診しよう
アレルギー症状は軽いものから重いものまでさまざまですが、放置すると悪化することがあります。かゆみや湿疹、くしゃみ、鼻づまり、咳が続く場合は、自己判断せずに病院を受診するのがおすすめです。気になる症状がある場合は早めに受診し、適切な診断と治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ快適な生活を維持しましょう。
忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ
慢性的な症状では、定期的な診察が必要になることがほとんどです。通院が難しい場合はオンライン診療を利用することで、適切な治療を継続しやすくなります。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットに接続できるスマートフォンやタブレット、パソコンを使い、自宅にいながら医師の診察を受けられる医療サービスです。ビデオチャットを通じて医師と直接相談できます。このサービスでは、診察の予約、問診、診断、薬の処方箋の発行、支払いまでをすべてオンラインで完結することが可能です。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をアプリで簡単に利用できるサービスになります。診察の予約、オンライン診療、処方箋の発行、決済、薬の受け取りまでをアプリで完結できるのが最大の特徴です。
専門スタッフによるサポート、お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能や、お薬手帳のデジタル管理機能もあり、継続的な治療がしやすくなっています。当日または翌日に処方薬を受け取ることが可能です。
オンラインで受診できる医療機関を探す⇒
まとめ
アトピーとアレルギーは異なる仕組みを持ちながらも密接に関連しています。アトピー性皮膚炎の方は、気管支喘息やアレルギー性鼻炎、食物アレルギーを併発することがあり、これを「アレルギーマーチ」と呼びます。症状の進行を防ぐためには、早めの対策が重要です。アレルゲンを減らすための環境整備、適切なスキンケア、腸内環境の改善を意識することで、症状の予防や軽減につながります。気になる症状がある場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診しましょう。

「アトピー」と「アレルギー」は似たように思われがちですが、それぞれ異なる特徴を持っています。アトピーとは体質的な要因によって引き起こされる皮膚炎で、アレルギーは免疫の過剰反応による症状です。別のものですが、アトピー性皮膚炎の方がアレルギー疾患を併発することも珍しくありません。この記事では、アトピーとアレルギーの違い、それぞれの関係性、そして予防のポイントについて詳しく解説します。
アトピーとは
アトピーは、かゆみを伴う湿疹が主な症状で、良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性的な病気です。皮膚の内部で炎症が起こり、本来備わっているバリア機能が低下します。その結果、外部からの刺激を受けやすくなり、かゆみが生じます。
アトピーのしくみ
アトピーの原因には、体質的な要因と環境的な要因が関係しています。体質的な要因としては、アトピー素因や皮膚のバリア機能が低下している状態が要因です。
人間の皮膚には、外部からの刺激や細菌の侵入を防ぎ、体内の水分が逃げないようにするバリア機能が備わっています。アトピーの方の皮膚は、バリア機能が低下しているため、角層を構成する角質細胞間脂質や水分を保持する天然保湿因子が減少し、角層のバランスが崩れています。その結果、外部からの刺激やアレルゲンが侵入しやすくなるのです。
アレルゲンが皮膚から侵入すると、免疫細胞が反応し、ヒスタミンという物質を放出することで炎症が起こります。
原因となるもの
アトピー性皮膚炎の悪化要因は人によって異なります。多くの場合、1つの要因だけでなく、複数の要因が重なり合って症状が悪化します。代表的な悪化要因は、汗やストレス、ハウスダストやダニ、細菌・カビ、食べ物などです。
アレルギーとは
私たちの体には、ウイルスや細菌などの異物が侵入した際に、それを排除するために「抗体」が作られ、外敵と戦う「免疫」という仕組みが備わっています。しかし、この免疫が本来害のない食べ物や花粉などに対しても「有害なもの」と誤って認識し、過剰に反応してしまうのがアレルギーです。本来は体を守るはずの免疫反応が、逆にかゆみやくしゃみ、炎症などの症状を引き起こし、自分自身を傷つけてしまいます。
アレルギーのしくみ
アレルゲンが侵入すると、体内ではIgE抗体というタンパク質が作られ、これが皮膚や粘膜にあるマスト細胞の表面に付着します。再び同じアレルゲンが体内に入ると、IgE抗体と結合し、マスト細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出されます。
このヒスタミンが神経を刺激し、かゆみやくしゃみ、炎症などのアレルギー症状を引き起こします。アレルギー反応は、体を守るための仕組みがかえって自分自身を攻撃する形となり、さまざまな症状を引き起こします。
原因となるもの
食物アレルゲンには、卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、大豆、魚類、肉類、果物などがあります。吸入性アレルゲンは、ダニやホコリ、カビ、ペットの毛、寝具や衣類の素材、花粉などです。接触性アレルゲンは、化粧品、塗料、衣服、金属、うるし、ゴム(ラテックス)、洗剤などがあり、肌に触れることで、かぶれや炎症を引き起こすことがあります。
アトピーとアレルギーの違い
| アトピー | アレルギー | |
| 発症の仕組み | 遺伝的に皮膚のバリア機能が弱く、アレルギーを起こしやすい体質 | 免疫が本来無害な物質に対して過剰に反応 |
| 原因 | 遺伝的要因に、環境要因が症状を引き起こす | 環境要因(アレルゲン)が主な原因 |
| 免疫反応 | Ⅰ型アレルギー | Ⅰ型~Ⅳ型アレルギー |
| 症状 | 皮膚の乾燥、湿疹、かゆみ、鼻炎、気道の炎症 | 蕁麻疹、くしゃみ、鼻水、喘息、アナフィラキシーなど |
アトピーとアレルギーの関係
アレルギーによる病気そのものは遺伝しませんが、アレルギーを起こしやすい体質は親から子へ受け継がれることがあります。アトピー素因を持つ親がアトピー性皮膚炎だったとしても、その子どもが必ず同じ病気になるわけではありません。しかし、受け継いだ体質の影響で、喘息やアレルギー性鼻炎、食物アレルギーなど、別のアレルギー疾患を発症する可能性があります。
アレルギーマーチとは
幼少期にアトピー性皮膚炎を発症し、成長とともに症状が落ち着いた後、今度は喘息やアレルギー性鼻炎を発症するケースもあります。一つのアレルギー性疾患が治まった後に、別のアレルギー疾患が続けて現れる現象が「アレルギーマーチ」です。
アトピー性皮膚炎と併存することがあるアレルギー疾患
アトピー性皮膚炎の方は、他のアレルギー性疾患を発症しやすい傾向があります。
気管支喘息
気管支喘息は気道に慢性的な炎症が続き、さまざまな刺激に対して過敏になり発作的に気道が狭くなる病気です。炎症が持続することで気道が敏感になり、ちょっとした刺激でも強く反応し、呼吸がしにくくなる発作を繰り返します。
炎症の主な原因は、ダニやハウスダスト、ペットのフケ、カビなどのアレルゲンです。喘息発作が起こると、突然咳が出たり、痰が出て、ゼーゼー・ヒューヒューという音を伴いながら息苦しさを感じます。特に夜間や早朝に症状が出やすいのが特徴です。
アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎は、アレルゲンが原因となり、鼻の粘膜が過剰に反応することで発症する疾患です。原因となるアレルゲンの種類によって、通年性アレルギー性鼻炎と季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)に分けられます。
通年性アレルギー性鼻炎は、ダニやホコリ、ペットの毛などが原因となり、一年を通して鼻炎の症状が現れます。主な症状は、くしゃみ、透明で水っぽい鼻水、鼻づまりです。通常、鼻を通して空気を吸うことで湿度が調整され、体内に入りやすい状態になります。
食物アレルギー
食物アレルギーとは、摂取した食物が原因となり、免疫の仕組みを介して蕁麻疹、湿疹、下痢、咳、呼吸困難などの症状が引き起こされる状態を指します。アレルギー反応の対象となるのは、主に動植物由来のタンパク質です。食物アレルギーは免疫の働きを介して発症するため、食物が原因で体に異常が出る場合でも、すべてが食物アレルギーとは限りません。
花粉症
花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となり、免疫反応によって鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの症状が引き起こされるアレルギー疾患です。季節性アレルギー性鼻炎とも呼ばれ、特定の時期に症状が現れるのが特徴です。
アレルギーマーチを予防する方法は
体質そのものを変えることは難しいですが、日常生活に注意することで予防につながります。
環境を整える
ダニやホコリ、カビを減らすことで、アレルギー症状の悪化を防げます。布団やシーツなどの寝具は、ダニが繁殖しやすいため、清潔に保つことが重要です。
布団専用の掃除機や、掃除機用の布団アタッチメントを使用し、ダニやホコリを吸い取るようにしましょう。また、シーツやカバーは週1回程度洗濯し、できれば天日干しをするのが理想的です。
スキンケアを行う
皮膚のバリア機能が低下すると、アレルゲンが体内に侵入しやすくなり、アレルギー症状が悪化する原因になります。乳幼児は皮膚が薄く、皮脂の分泌が少ないため、バリア機能が未熟で注意が必要です。
バリア機能を守るためには、清潔と保湿が重要です。毎日の入浴やシャワーで汗や汚れを落とし、入浴後はすぐに保湿剤を塗って皮膚の乾燥を防ぎましょう。肌を傷つけないために、ナイロンタオルは避け、低刺激の石鹸やボディーソープを使い、泡で包み込むようにやさしく洗うのが理想的です。
腸内環境を整える
腸内環境を整えることで免疫のバランスが整い、アレルギー症状の軽減につながります。悪玉菌が増えると免疫機能が低下し、アレルギー性疾患を発症しやすくなるため注意しましょう。
腸内細菌は、食べたものをエサにして生きています。食物繊維やオリゴ糖は善玉菌のエサになり、肉類のタンパク質や揚げ物などの脂質は悪玉菌のエサになります。アレルギー症状を悪化させないためには、発酵食品(ヨーグルト・納豆・味噌など)や食物繊維を含む野菜・果物を積極的に摂ることが大切です。
病院を受診する
アレルギー症状が続く場合や、自己管理だけでは改善が見られないときは、病院を受診することが大切です。適切な治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質を向上させることが可能です。
気になる症状があれば放置せず医療機関を受診しよう
アレルギー症状は軽いものから重いものまでさまざまですが、放置すると悪化することがあります。かゆみや湿疹、くしゃみ、鼻づまり、咳が続く場合は、自己判断せずに病院を受診するのがおすすめです。気になる症状がある場合は早めに受診し、適切な診断と治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ快適な生活を維持しましょう。
忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ
慢性的な症状では、定期的な診察が必要になることがほとんどです。通院が難しい場合はオンライン診療を利用することで、適切な治療を継続しやすくなります。
オンライン診療とは
オンライン診療は、インターネットに接続できるスマートフォンやタブレット、パソコンを使い、自宅にいながら医師の診察を受けられる医療サービスです。ビデオチャットを通じて医師と直接相談できます。このサービスでは、診察の予約、問診、診断、薬の処方箋の発行、支払いまでをすべてオンラインで完結することが可能です。
SOKUYAKUとは
SOKUYAKUは、オンライン診療をアプリで簡単に利用できるサービスになります。診察の予約、オンライン診療、処方箋の発行、決済、薬の受け取りまでをアプリで完結できるのが最大の特徴です。
専門スタッフによるサポート、お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能や、お薬手帳のデジタル管理機能もあり、継続的な治療がしやすくなっています。当日または翌日に処方薬を受け取ることが可能です。
まとめ
アトピーとアレルギーは異なる仕組みを持ちながらも密接に関連しています。アトピー性皮膚炎の方は、気管支喘息やアレルギー性鼻炎、食物アレルギーを併発することがあり、これを「アレルギーマーチ」と呼びます。症状の進行を防ぐためには、早めの対策が重要です。アレルゲンを減らすための環境整備、適切なスキンケア、腸内環境の改善を意識することで、症状の予防や軽減につながります。気になる症状がある場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診しましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1.
当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。
2.
当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。
3.
当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。
4.
前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。